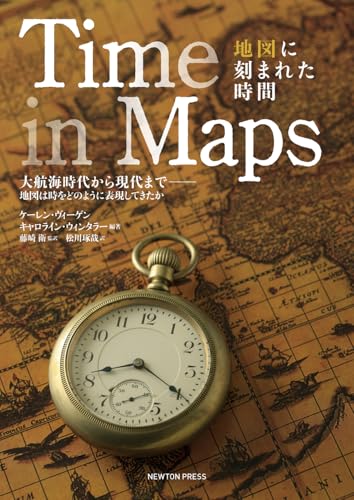書評
『大戦略論: 戦争と外交のコモンセンス』(早川書房)
歴史の転換点、指導者の戦略思考
日本人の歴史はぬるま湯のようだとはしばしば聞く。海に囲まれた島国であるために外敵に脅かされることがほとんどなかったからだろう。そのせいか「戦略」などという言葉を聞くだけでも、異様な気分になる。まして「大戦略」となると、心おだやかではない。名門イェール大学の人気講座「グランド・ストラテジー・プログラム」から生まれた本書によれば、大戦略(グランド・ストラテジー)とは「無限になりうる願望と必ず有限の能力とを釣り合わせること」である。大戦略は国家だけでなく人々にも必要であり、「生き方としての大戦略」でもあると著者は提唱する。
西洋文明の根底には、二つの大戦略があるという。キリスト教はローマ滅亡の原因だったのか、それともローマ帝国を不滅の存在にしたのか、それは決着のつかない難問である。そこには「魂」と「国家」の対立があり、千年の時を隔てて練り上げられた。聖なるアウグスティヌスは地上の無秩序と地獄の業火を避ける戦略を立て、罪深いマキアヴェリは不出来な支配者と彼らが運営する失敗国家に対処する戦略を練った。
アウグスティヌスは、全能の神と人間の自由意志とがどうすれば共存できるか、を説明しようとしたが、できなかった。マキアヴェリは、神はすべてを自らなそうとはしないとして問題を片づけてしまった。だが、神のなすことはほとんどないという別の問題を引き起こした。16世紀のエリザベス朝の史料には四〇〇回以上も「殺人鬼マキアヴェリ」といった表現が見られるというから、人々の困惑気味な表情が目に浮かぶ。
これらの問題は宙ぶらりんであったが、20世紀半ば、哲学者I・バーリンは一つの解決案を出した。マキアヴェリは、理想は実現不可能だとはっきり語ったのであり、国家の運営とは理想主義と現実主義のバランスをとることではなく、現実主義同士の戦いにほかならない。国家の統治において、魂を救うキリスト教の教えを尊重するわけにはいかないのだ。
本書のなかでも、とくに目をひくのが「最も偉大な戦略家たち」の章題で比較されるトルストイと『戦争論』の著者クラウゼヴィッツである。『戦争と平和』のなかで、ある戦いの直前に、主人公二人ピエールとアンドレイの前を通り過ぎたのは、プロイセン軍を辞してロシア軍に加わった馬上のクラウゼヴィッツともう一人の士官だった。「戦争は広い空間に拡大せねばならぬ」「目的は敵の力を弱体化させることにあるのだから」と語り合っている。だが、アンドレイは「あいつらドイツ人どもは全ヨーロッパをナポレオンに明け渡し、それでもなおわれわれに教えを垂れにやって来たのだ」と苦々しく吐露する。この場面には、どこにでもある理論と現実の乖離が鮮明に浮かび上がっているという。クラウゼヴィッツとトルストイ以上に、時間、空間、スケールについて深く考えた人物はいないと著者は指摘する。
ペルシャ戦争から無敵艦隊の敗北を経て第2次世界大戦にいたる歴史の転換点において、指導者はどのように決断したのか、その戦略思考の基本とはなにかが実に分かりやすく熱く解説されている。ともすれば戦争を「対岸の火事」としてしか見てこなかった日本人には、グローバル世界の現実が突きつけられているかのような読後感が残った。
ALL REVIEWSをフォローする