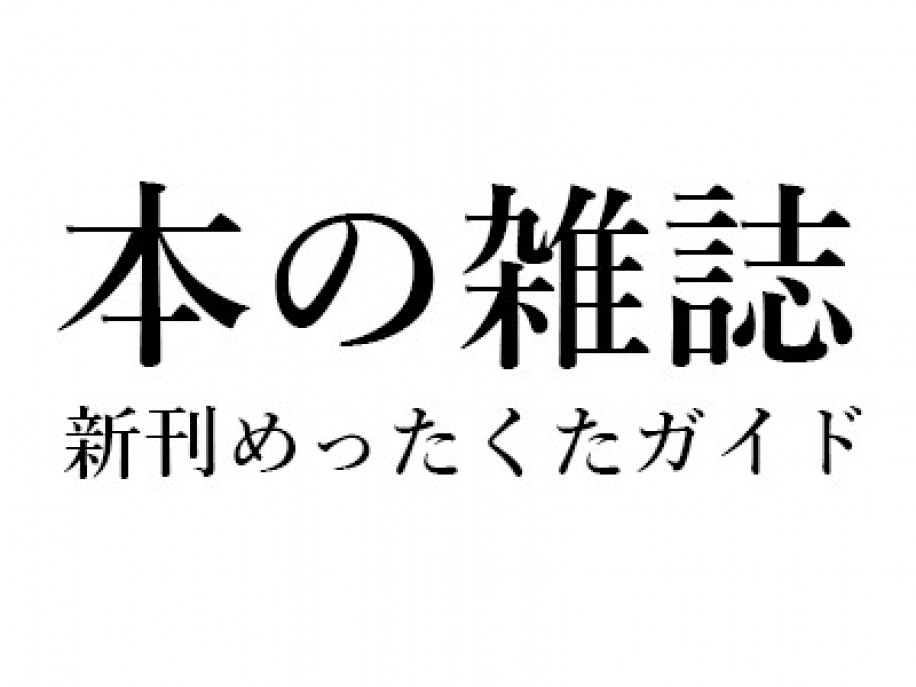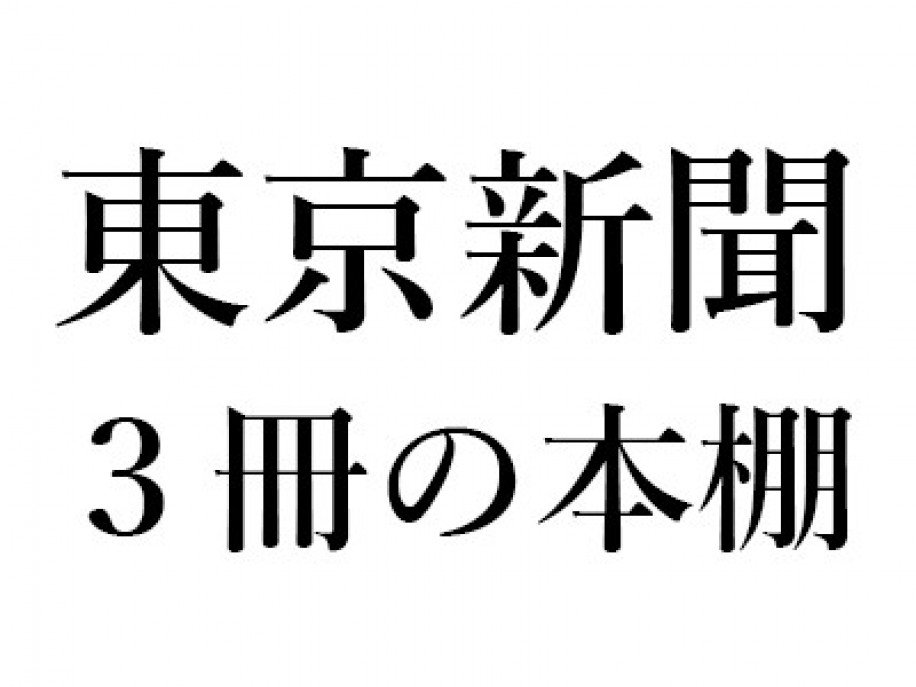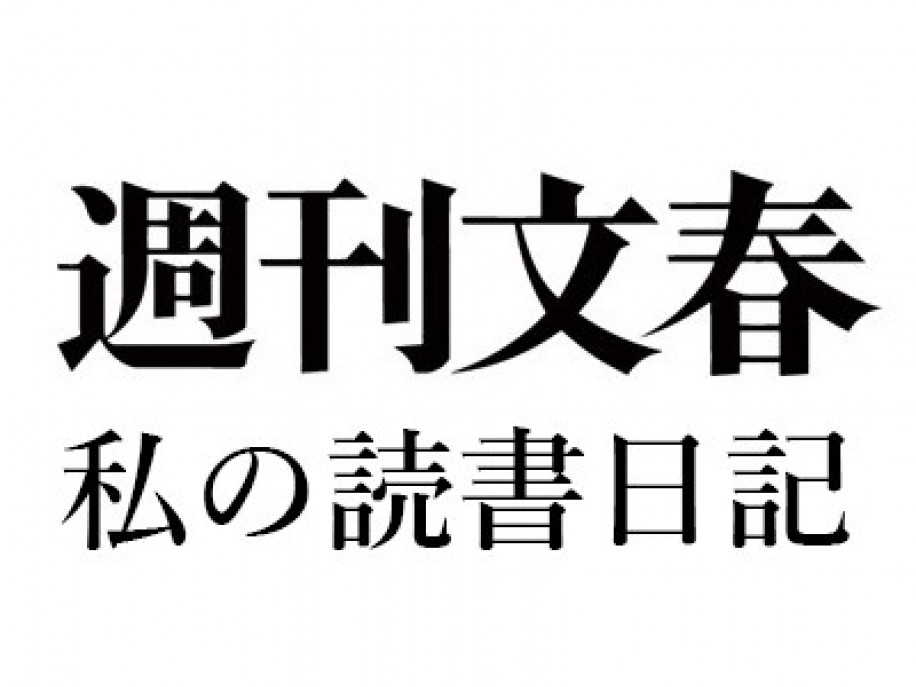書評
『文学的商品学』(文藝春秋)
「モノ」の描写で現代小説がわかる
エミール・ファゲは名著『読書術』のなかで、すべての本に通じる読書術はひとつしかない、と断言した。ゆっくり読むこと。斎藤美奈子も、ゆっくり読むことを提唱する。その結果、小説から何が見えてきたか。ストーリーの面白さ? 登場人物の魅力? 文章の美しさ? 否。「モノ」の描かれ方である。
高度資本主義の現代は、空前の大衆消費社会。暮らしとは、モノを消費することなのだ。モノを見れば人がわかる。だとすれば、モノを見れば作品もわかるにちがいない。
一方、近代小説はモノを抑圧してきた。本書によれば、モノの描写にかんする近代小説の原則はこんなふうに要約できる。
(1)小説に必要不可欠な「内面描写」に関係しないモノの描写は控える。
(2)モノの描写はなるべく手短にすませる。
(3)時間がたっても流行遅れにならないよう、長く残りつづけるモノを選ぶ。
だが、人間の「内面」が信じられなくなった今、モノの方は小説のなかでどんなふうに描写されているのか? ファッション、車、香水、食べ物、ホテル、オートバイ、野球……。そうした種々雑多なアイテムをめぐって、日本小説の現状がこと細かに調査され、分析される。
といって、堅苦しい文芸批評ではない。随所で私はふきだした。著者の引用する文章がすばらしいからだ。すばらしいというのは褒め言葉ではなく、こう、なんというか、凄(すご)いのである。例えば、ファッションの章で、国民的ベストセラー『失楽園』からこんな一文が引かれる。
凛子は淡いピンクのスーツの襟元に花柄のスカーフをそえ、グレーの帽子をかぶって、手にやや大きめのバッグを持っている。
ほかの例文も検討した斎藤の感想は、(1)服がダサい、(2)文章に愛想がない。「凛子という女は、なんだってまた密会デートに、いつもこんな野暮(やぼ)ったい服装で出かけるのでしょうか」。そして、『失楽園』のファッション描写を「色+柄+アイテム名」の報告に尽きると分析し、見たまんまやないけ、と突っ込んでいる。ことほどさようにモノの表現はむずかしい。
あるいは、食べ物の場合。江國香織や川上弘美の描く食べ物がどうしてあんなに誘惑的なのかを軽く解剖し、返す刀で、村上龍や辺見庸は料理を記憶(とくにセックス)の再生装置として利用しているにすぎない、と斬(き)って捨てる。しかし、料理そのものを描こうとして、ほとんどご乱心のような文章を書く作家もいる。
美味しかったが、美味しい、と一言では片づけられない、哲学的な、あるいは祈りそのもののような味があった。(辻仁成)
といわれてもなあ。モノの描写をめぐる作家と作品の悲喜劇。楽しい読み物だが、表象の困難という大きな主題を背負った力作でもある。
朝日新聞 2004年4月11日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする