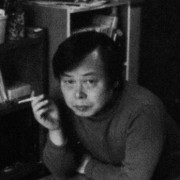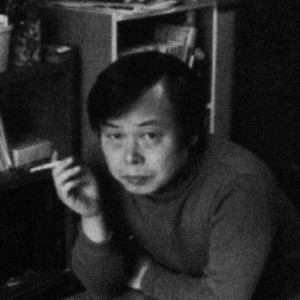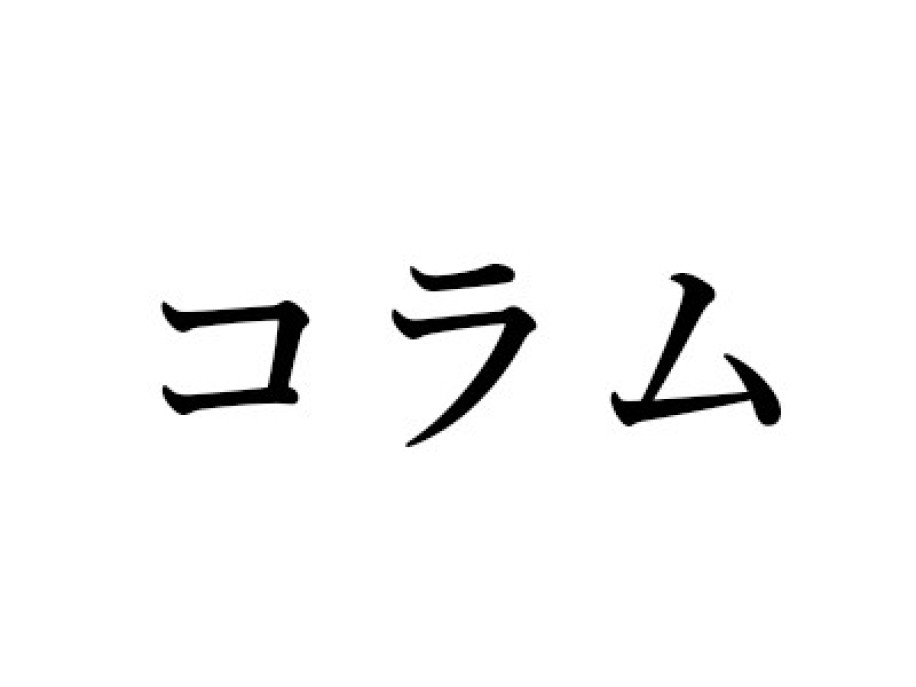書評
『薬草まじない』(晶文社)
大河としての生命
ジャングルのなかの、大きな川のほとりの町に生まれた一人の若者が、石女の妻に子宝を授けてくれる薬草をもとめて、遠い旅に出る。行き先は「全知全能の聖母」とも呼ばれる女薬草まじない師の住む「さい果ての街」。若者は途上のジャングルやサバンナで、おそろしい悪鬼や怪物どもに出合い、襲われ、戦い、うち勝って、めでたく薬草を手に入れる。その往還の物語である。『西遊記』の孫悟空が沙悟浄や猪八戒と道連れなように、チュツオーラの主人公も、何人もの分身と一緒に旅に出る。分身たちのうち「第二の心」はおおむね正しい助言をくれるが、「第一の心」はときどきへまをする。のみならず両者ともに、主人公が危なくなると、さっさと逃げてしまう。けれどもそういうときには、「記憶力」が二人の罪状を記録しながら主人公に出口を教え、それでも主人公に勝ち目のないときには、「第二の最高神」が出現して助太刀してくれる。
こんなふうに主人公は、一人でありながら、複数なのだ。この人格の複数性・多層性は他の人物の上にもくり返され、たとえば終章近く、主人公に薬草を授けるセレモニーに現れる女薬草まじない師は、美しくもあれば、二目と見られぬほどグロテスクでもあり、聖母でもあれば、悪鬼でもあって、しかもいく通りもの獣や人間の声色を使う。
いや、多層性といえば、森のなかで主人公を襲う、「頭の取りはずしのきく狂暴な野性の男」とか、「アブノーマルな蹲踞の姿勢の男」とか「乳房の長い山の女」とか、のような悪鬼や怪物どももまた、主人公自身の悪の分身であり、小説全体は、魂のジャングルにひそむそれらさまざまの怪物を退治して、真の自己に到達する自己実現の物語ともいえそうである。
けれども、魂の変遷というモチーフだけでいえば、西欧の幻想小説のなかにもいくらもモデルがあるが、このナイジェリア人作家に特徴的なのは、同時にそれが、類としての肉体の永遠の死と再生の物語でもあることだ。それは、物語の大筋が、不毛な石女を生殖と豊饒へとめざめさせる薬草探しであることとも無縁ではない。
とりわけ主人公が「生まれながらにして死んでいる赤ん坊」族の果実を食べて、自分の腹のなかから赤ん坊のようにとび出したり、空腹のあまり妻の不妊を治す薬草を食べたために、夫の自分までも妊娠したりするエピソードが、ふしぎなユーモアのうちに豊饒信仰をくっきりと浮かび上がらせる。生命発生の根源であるジャングルへの恐怖と愛とが、大きな川のようにとうとうと流れている、アフリカの幻想小説である。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1983年7月25日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする