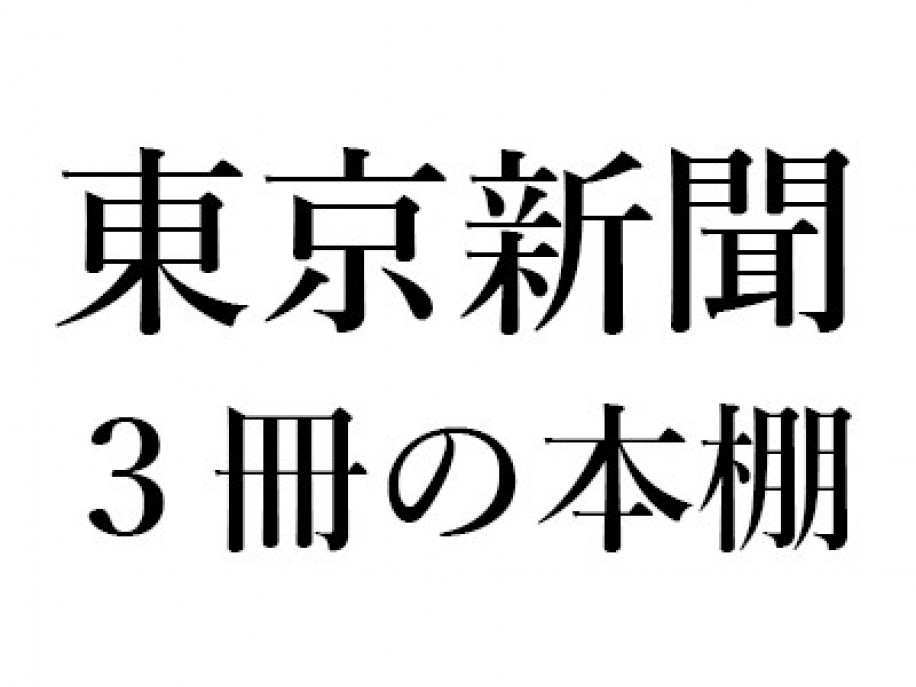書評
『メッセージ トーベ・ヤンソン自選短篇集』(フィルムアート社)
ムーミンにはない、もう一つの顔
フィンランドの作家トーベ・ヤンソンが八十六歳で亡くなってから今年で二十年。ヤンソンといえば日本だけでなく世界中で愛されてきたトロールという不思議な生きものが活躍するムーミン・シリーズをどうしても挙げざるをえないのだが、彼女にはもうひとつ、一九九〇年代半ばから、「トーベ・ヤンソン・コレクション」(筑摩書房、冨原眞弓訳)として紹介されてきた小説家の顔がある。本書はそのヤンソンが生前最後にまとめた自選短篇集で、未紹介の七篇を含む全三一篇からなっている。フィンランドの作家ではあるけれど、父がスウェーデン語系フィンランド人の彫刻家、母がスウェーデン人の挿絵画家という出自によって、彼女の母語はフィンランドにおける少数派言語のスウェーデン語となった。
二つの芸術領域、二つの国、二つの言語のあいだに育った自伝的な要素がここには反映されており、個々に独立した作品で、舞台も国内に限定されているわけでもないのに、最後まで通して読んでみると、一冊の長篇小説であったかのような趣がある。
特徴的なのは、登場人物たちが他者を見つめる眼差しにそなわった独特の距離感だ。人肌のぬくもりをあえて遠ざける冷淡さと、それをおびやかす人恋しさが微妙にまじりあう。一人一人が真に自由を獲得するためには、同程度の厳しさで自由を求める他者の存在が必要になる。
フィリップ・テイルがまえがきのなかで指摘しているように、それは二人という関係性のなかであぶり出されてくる。親子、夫婦、友人、恋人、男性もしくは女性のカップル。ここにもう一人加わったとき、二人の単位に亀裂が走り、私の、私たちの、という所有形容詞が軋(きし)みだす。これらはムーミン谷の住人たちにも通じる要素かもしれない。彼らの関係性にも、しばしば誤解や嫉妬による傷が生じた。しかしそれらを解毒する知恵もあって、いつまでも苦みが残ることはない。他方、ヤンソンの小説からは、ところどころで自我の胆汁が染み出し、なかなか消えてくれないのだ。
その染みを染みのまま受け入れることを可能にしているのは、芸術への頑なな信頼に支えられた孤独である。一九七一年に発表された「リス」の冒頭がその意味で印象深い。
風のない十一月のある日、夜明け近くに、ボートの浜に一匹のキタリスがいるのが見えた。
岩だらけの島へ、板きれに乗り、風に吹かれて渡ってきたリスは、それを見ている者の分身である。餌を与えて安易に手なずけ、「責任や良心を伴う存在にしてはいけない」。登場人物たちは、自身をも他者として凝視する。その瞬間、「作品は無言であるべき」(「コニコヴァへの手紙」)という芸術の力強い沈黙が浮かびあがるのだ。
幼少時から慣れ親しみ、自身も同性の伴侶と長年にわたって夏を過ごした島々がよく舞台に選ばれている。島ほど自由で厳しい場所はない。孤絶していることを他者に認められないかぎり、島にはならないからだ。タイトルになった『メッセージ』とは、外にいる自分への投壜(とうびん)通信だと言ってもいいだろう。
ALL REVIEWSをフォローする