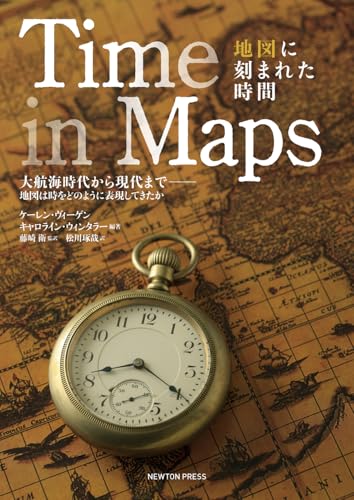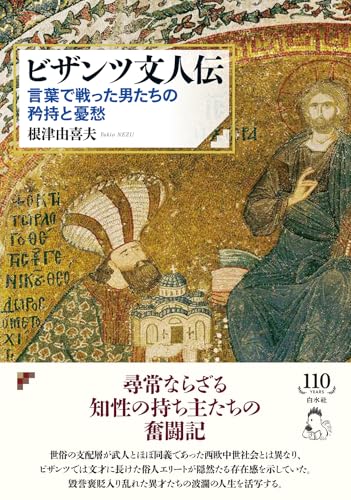書評
『「社会」の底には何があるか 底の抜けた国で〈私〉を生きるために』(講談社)
腕っぷしが幅利かせる国際政治
ときどき子供の頃を思い出すと、とくに男児の世界では腕っぷしの強い子が一目おかれていた。歳(とし)を経るにつれて、勉学のできる子、思いやりある優しい子、陽気で面白い子などが人気者になっていた。ところが、国際関係の問題になると、今日でも腕っぷしの強い国が幅を利かせるという幼児化現象が目立っている。どうしてなのかという素朴な疑問は消えそうもない。
ところで、菊谷和宏氏の『「社会」の底には何があるか』は、もともと日本の「社会」をあつかった「社会三部作」の一冊であるが、たまたま民主主義を論じるなかでフランス近代史に深くふれざるをえなくなった歴史書になっている。
フランス貴族の家系に生まれ、創成期のアメリカを旅して観察し、名著『アメリカのデモクラシー』を出したトクヴィルにとって、民主主義は称揚されるものではなかったという。望むと望まざるとにかかわらず、避けられない進展であり、神の摂理だった。合衆国では諸条件の「平等」こそが根源的な事実であり、個々の事実はそこから生じるにすぎないという。
20世紀初頭以降にパリ大学文学部(ソルボンヌ)で「道徳教育論」を語ったデュルケームにとって、社会的存在であるかぎり、人間は道徳生活ができるのだ。そのような社会的個人すなわち人々が形成する「人間社会」の到達点が民主主義(デモクラシー)にほかならないという。だが、ここで語られている民主主義(デモクラシー)は、通常の制度としての民主主義とは異なり、それを超えてその根底を示唆しているかのようだ。
ところで、トクヴィルの没年に生まれたベルクソンは、ナポレオン三世の第二帝政崩壊後に勢力をもった第三共和制を生きている。この時代は初期にはとくに反宗教性によって特徴づけられる。
ベルクソンはデュルケームと同世代だが、もっと長命だった。第一次世界大戦がおこると、祖国防衛のため国内の対立・抗争を一時棚上げにする挙国一致体制の確立が叫ばれるのだった。この呼びかけに応えて、カトリック勢力(王党派)も聖職者や関係者を前線に派遣して共和制に協力をおしまなかった。
このころから、ベルクソンは、神を彷彿させる生命原理について語るようになり、やがてカトリシズムをとり入れ、さらには第三共和制を本来的に宗教的(カトリシズム的)でありえたものとして理解するに至った。
こうして、共和主義と教権主義、世俗性と神性は、相反するものではなく、むしろ一つのつながりのある連続するものとなった。しかし、社会思想・実証科学のとらえる真理は、キリスト教というよりも「超越性一般」を志向していると言えるだろう。
ところが、民主主義の基礎となる「皆等しく人間」という通念は、日常経験とは「ほとんど合致しない」のだ。このような「神を欠いた」超越性はどのようなものなのか。その近代民主主義では、最大多数の最大幸福が目指されるのではなく、むしろ多様な少数意見が並存しそれらが自由に表明されることが肝要であるのだ。
ここに、今なお腕っぷしの強さを誇示する軍事力や戦争が、国際舞台にあっては幅を利かせる余地が残っているのではないだろうか。国際政治の幼児化現象が消失しない背景には実は近代の民主主義がある、とは言い過ぎだろうか。
ALL REVIEWSをフォローする