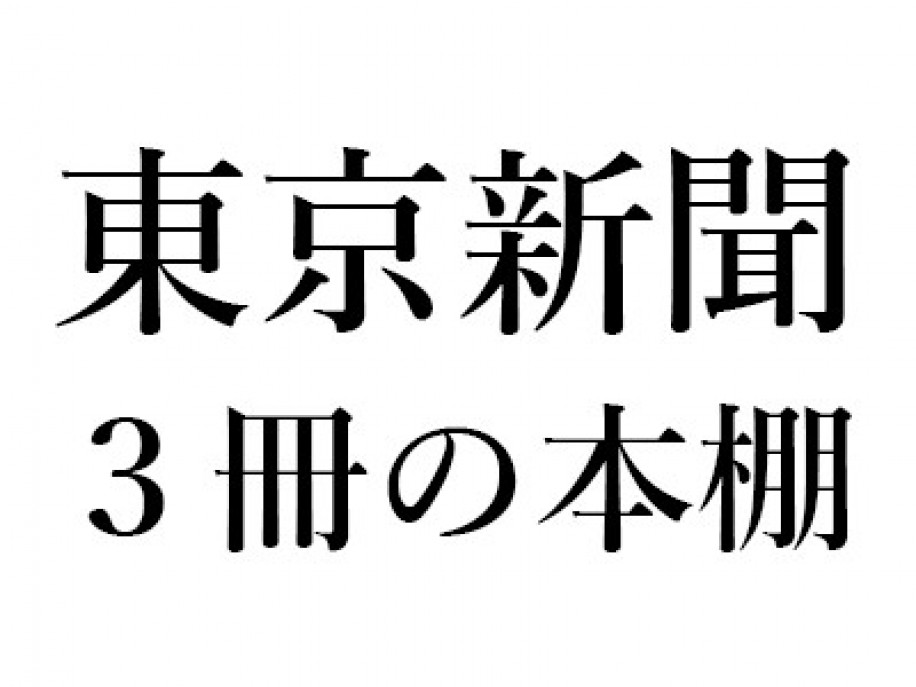解説
『白樺たちの大正』(文藝春秋)
白樺派について、こんなに面白く書けるのか。本書を読み終わったときの、率直な感想であった。
わたしは関川夏央さんと面識はないが、文学批評の新刊が出ると、必ずといっていいほど読んでいる。関心が近いこともあるが、最大の理由は、内容が興味を引き、しかもユーモアがあるからだ。これまで知らなかった事実を明らかにし、あるいは新しい解釈を示すだけではない。自由闊達な筆致と、よく練られた文章が魅力的である。文学批評には難解なもの、退屈なもの、読むに堪えないものが少なくないが、関川夏央さんの本は文句なしに面白くて、ためになる。
文学批評はたんに「真相究明」で事足りるわけではない。「言葉の芸術」を批評するのに、それにふさわしい文体を持っているかどうかが問われている。それが文学批評と文学研究の違いであり、また、批評が批評たるゆえんでもある。取り上げられる作品に比肩し、あるいはそれを凌駕する知性と文章力がないと、優れた批評とはいえない。しかし、それができる人はそう多くない。関川夏央さんはまちがいなくその一人である。批評の美しさとは何かを、端正な文章と見事なレトリックで雄弁に示している。白樺という、ときには退屈に感じさせる文学流派も、その手にかかると俄然面白くなる。並々ならぬ批評の力量が成せる技であろう。
わたしは白樺派の小説をずいぶん前から読んでいた。初めは文学としてではなく、日本語の教材としてである。そのためか、作品の出来映えをほとんど気にしなかった。とはいっても、最初に読んだのは武者小路実篤の小説ばかりだ。文章が平明でわかりやすい、中級の教材にはぴったりの作品である。日本語を少し勉強しただけでも小説が読めるのは、大きな感動であった。ところが、語学力がつくにつれ、徐々に倦怠しはじめた。ときには、読んでいて気恥ずかしくなることもある。
日本語の学習者は白樺派の世話になることが多い。志賀直哉の文章も上級日本語の教科書には必ずと言っていいほど出ている。作文の手本とされ、多読の材料としても勧められていた。志賀直哉の作品になると、さすがに「気恥ずかしい」とは思わなかった。それどころか、短編小説の出来映えには感心した。しかし、『暗夜行路』の冗長さには辟易した。
白樺派の不人気は日本でも同じだ。来日してそのことを知ってほっとした。明治文学や昭和文学に比べて、大正文学は独立した時代区分の文学として語られることは少ない。「明治・大正文学」のように、明治文学のシッポとして扱われるか、さもなければ昭和文学の「前史」として、軽く言及されることが多い。
時代が短いということもあるであろう。四十四年も続いた明治と、六十三年続いた昭和のあいだに挟まって、十四年で終わった大正はいかにも「短命」のように見える。しかも、これといった特色もない、という印象を拭いきれない。大正前期にはまだ明治の面影が残っており、一方、大正後期には昭和を思わせる徴候がすでに現れていた。明治期の開拓精神が欠如していながら、昭和期の情熱も蛮勇もない。大正時代は何となくそんな中途半端なイメージがあった。
じっさい、文芸批評において、大正文学を対象とするものは少ない。とりわけ白樺派については、いわゆる文学研究の領域でもほとんど関心が寄せられていない。文芸批評家にとっては面白みに欠けるし、研究者にとっては業績を挙げにくい。大正作家とはいっても、多くの場合、明治の作家か、昭和の作家として語られている。だが、わたしは、関川夏央さんならいつかはきっと白樺派を論じるだろう、と予感していた。
そう思うのには、根拠がある。団塊の世代として、関川夏央さんは戦後の貧しさと、高度経済成長後の豊かさをともに体験した。貧富の時代は強烈なコントラストをなしており、しかも、豊かな社会への変化は短い期間のあいだに急激に起きている。
あらゆる過去と同じように、高度経済成長がアウラとともに語られるようになったのは、消費社会が成熟した後のことである。多感な青春期に劇的な社会変化を経験した者にとって、文明化への「登頂」は、旧来の習俗とその精神的根拠の消去とともに記憶される。貧しさから脱し、豊かさへと離陸した瞬間は、必ずしも事後に想像されたように、歓呼の声に包まれたとは限らない。団塊の世代にとって、むしろ自らの身体と精神に大きな罅(ひび)が入ったような痛みとして経験したのであろう。昭和時代とは何だったのか。多くの人は疑問を持っていたはずだ。
恐らく精神史の大きな断絶を感じたのであろう、関川夏央さんの文筆活動において、昭和という時代はずっと主旋律になっている。昭和文学の批評をはじめ、『昭和が明るかった頃』(文藝春秋)のような映画評論や、『砂のように眠るむかし「戦後」という時代があった』(新潮社)、『昭和時代回想』(日本放送出版協会)に見られる世相批評にいたるまで、さまざまな視点から思索を重ねてきた。
昭和について考えると、必然のように現代人のメランコリーの由来という問題に行き着く。じっさい、『二葉亭四迷の明治四十一年』(文藝春秋)や『「ただの人」の人生』(文藝春秋)にあるように、本書が執筆されるまでに、明治の作家たちについて多くのことが検討されている。関川夏央さんの言葉を借りれば、明治の人たちは「現代日本人のさきがけだった」からだ。
明治と昭和という、二つの離れた時代について多く語られているのに対し、関川夏央の仕事では、大正時代が一つの空白であった。それも意識的に空けられた、批評の空き地のようだ。それだけに、関川夏央さんが大正文学について果たしてどう考えているのかは、非常に興味を惹かれた。
白樺派が大正文学の「代表選手」として取り上げられたのは、ある程度、予想できることだ。 関川夏央さんがいう憂国の人、完全主義の人、自己嫌悪の人、放蕩の人、親孝行の人、愛情に拘泥する人は明治の文学者に多い。自意識過剰で、友達にはしたくない人ばかりだ。その線で考えると、白樺派の作家たちに照準を合わせたのは、必然的な選択というべきなのかもしれない。同じ大正時代でも、白樺派というファインダーを通して見ると、それまでと違った風景が見えてきた。
文学批評といえば、テクストの精細な読みと、作家についてのスコラ的な考究が思い出される。それ自体は必ずしもまちがっているわけではない。一方、そうすることによって、文学が「世間」から切り離されたことも否めない。
関川夏央さんは世間の「体温」には敏感であった。文学は社会から隔絶した事象としてではなく、連綿たる精神史の流れにおいて捉えられている。小説は時代精神の表徴として読み解かれているから、個々の作品よりも、文学的な感性が醸成される土壌にまなざしが向けられている。
大正五(一九一六)年から大正九年までの三年半、日本経済は第一次大戦景気で驚くほどの成長を遂げた。イギリスの国民所得との比較、高等教育普及率、中学校、高等女学校や実業学校の生徒数などについて、正確な統計値を示しての論証は鮮やかだ。大衆が登場する過程は、観念でたどるのではなく、数字の精査を通して読み解かれている。
日露戦争の後、日本社会は急速に膨張した。文官の数が倍増し、陸軍や海軍はさらなる拡張を求めた。群衆たちも「大日本」への道を熱狂的に支持した。白樺派の理想主義は一見、社会の流れに逆行しているようだ。しかし、関川夏央さんは両者のあいだの共通点を見事に見いだした。武者小路実篤は芸術至上主義の立場から「世界に伍すべき日本」を語ったが、重税と戦後不況は「大日本」の強さによって打開されるべきだと考えた人たちも、別の意味で「世界に伍すべき日本」をイメージしていた。この指摘は同じ作家の、昭和期に入ってからの活動を説明する上でも役立つだろう。大正文学という連結器を入れた途端、前後がつながるようになっただけではなく、明治文学も昭和文学もいっそう明瞭に見えてきた。
関川夏央さんの仕事は多岐にわたるが、その中心を占めているのは、近代精神の表象という問題に対する探究である。それは取りも直さず、「現在」に対する関心であり、今日の日本人の精神構造の由来を知るためのものである。東アジア周辺国に目を転ずるのも、失われた過去を感覚的に把握するのに、横の距離感という参照軸が必要だからであろう。この作家は「いま」から離れて過去を批評したことは一度もない。
そのことを念頭において本書を読むと、いっそう興味を惹かれる。大正時代の精神史の解読は、今日を読み解く鍵になっているからだ。大企業信仰も、左翼と右翼の対立という構図も、大正時代と現代とはよく似ている。大正の人たちは口を開けば「改造」というが、現代人は「改革」をまるで宗教のように崇めている。大正時代には「自我確立」が個人にとって最大の課題であったが、現代人は「自分探し」に、パラノイア的な偏愛を示している。大正こそ現代の発端した時代だ。この指摘も、現在に対して強い関心があったからこそ導き出された結論であろう。本書が一見、重たい主題を扱いながら、読んでいて興味が尽きないのは、地に足がついているからだ。
白樺派も大正という時代も、雲の彼方に消えた歴史的な過去ではない。現在と地続きになり、現代の基盤となるものである。上品な文章を読みながら、そんな過去へとタイムスリップできるのは幸せなことだ。
【この解説が収録されている書籍】
わたしは関川夏央さんと面識はないが、文学批評の新刊が出ると、必ずといっていいほど読んでいる。関心が近いこともあるが、最大の理由は、内容が興味を引き、しかもユーモアがあるからだ。これまで知らなかった事実を明らかにし、あるいは新しい解釈を示すだけではない。自由闊達な筆致と、よく練られた文章が魅力的である。文学批評には難解なもの、退屈なもの、読むに堪えないものが少なくないが、関川夏央さんの本は文句なしに面白くて、ためになる。
文学批評はたんに「真相究明」で事足りるわけではない。「言葉の芸術」を批評するのに、それにふさわしい文体を持っているかどうかが問われている。それが文学批評と文学研究の違いであり、また、批評が批評たるゆえんでもある。取り上げられる作品に比肩し、あるいはそれを凌駕する知性と文章力がないと、優れた批評とはいえない。しかし、それができる人はそう多くない。関川夏央さんはまちがいなくその一人である。批評の美しさとは何かを、端正な文章と見事なレトリックで雄弁に示している。白樺という、ときには退屈に感じさせる文学流派も、その手にかかると俄然面白くなる。並々ならぬ批評の力量が成せる技であろう。
わたしは白樺派の小説をずいぶん前から読んでいた。初めは文学としてではなく、日本語の教材としてである。そのためか、作品の出来映えをほとんど気にしなかった。とはいっても、最初に読んだのは武者小路実篤の小説ばかりだ。文章が平明でわかりやすい、中級の教材にはぴったりの作品である。日本語を少し勉強しただけでも小説が読めるのは、大きな感動であった。ところが、語学力がつくにつれ、徐々に倦怠しはじめた。ときには、読んでいて気恥ずかしくなることもある。
日本語の学習者は白樺派の世話になることが多い。志賀直哉の文章も上級日本語の教科書には必ずと言っていいほど出ている。作文の手本とされ、多読の材料としても勧められていた。志賀直哉の作品になると、さすがに「気恥ずかしい」とは思わなかった。それどころか、短編小説の出来映えには感心した。しかし、『暗夜行路』の冗長さには辟易した。
白樺派の不人気は日本でも同じだ。来日してそのことを知ってほっとした。明治文学や昭和文学に比べて、大正文学は独立した時代区分の文学として語られることは少ない。「明治・大正文学」のように、明治文学のシッポとして扱われるか、さもなければ昭和文学の「前史」として、軽く言及されることが多い。
時代が短いということもあるであろう。四十四年も続いた明治と、六十三年続いた昭和のあいだに挟まって、十四年で終わった大正はいかにも「短命」のように見える。しかも、これといった特色もない、という印象を拭いきれない。大正前期にはまだ明治の面影が残っており、一方、大正後期には昭和を思わせる徴候がすでに現れていた。明治期の開拓精神が欠如していながら、昭和期の情熱も蛮勇もない。大正時代は何となくそんな中途半端なイメージがあった。
じっさい、文芸批評において、大正文学を対象とするものは少ない。とりわけ白樺派については、いわゆる文学研究の領域でもほとんど関心が寄せられていない。文芸批評家にとっては面白みに欠けるし、研究者にとっては業績を挙げにくい。大正作家とはいっても、多くの場合、明治の作家か、昭和の作家として語られている。だが、わたしは、関川夏央さんならいつかはきっと白樺派を論じるだろう、と予感していた。
そう思うのには、根拠がある。団塊の世代として、関川夏央さんは戦後の貧しさと、高度経済成長後の豊かさをともに体験した。貧富の時代は強烈なコントラストをなしており、しかも、豊かな社会への変化は短い期間のあいだに急激に起きている。
あらゆる過去と同じように、高度経済成長がアウラとともに語られるようになったのは、消費社会が成熟した後のことである。多感な青春期に劇的な社会変化を経験した者にとって、文明化への「登頂」は、旧来の習俗とその精神的根拠の消去とともに記憶される。貧しさから脱し、豊かさへと離陸した瞬間は、必ずしも事後に想像されたように、歓呼の声に包まれたとは限らない。団塊の世代にとって、むしろ自らの身体と精神に大きな罅(ひび)が入ったような痛みとして経験したのであろう。昭和時代とは何だったのか。多くの人は疑問を持っていたはずだ。
恐らく精神史の大きな断絶を感じたのであろう、関川夏央さんの文筆活動において、昭和という時代はずっと主旋律になっている。昭和文学の批評をはじめ、『昭和が明るかった頃』(文藝春秋)のような映画評論や、『砂のように眠るむかし「戦後」という時代があった』(新潮社)、『昭和時代回想』(日本放送出版協会)に見られる世相批評にいたるまで、さまざまな視点から思索を重ねてきた。
昭和について考えると、必然のように現代人のメランコリーの由来という問題に行き着く。じっさい、『二葉亭四迷の明治四十一年』(文藝春秋)や『「ただの人」の人生』(文藝春秋)にあるように、本書が執筆されるまでに、明治の作家たちについて多くのことが検討されている。関川夏央さんの言葉を借りれば、明治の人たちは「現代日本人のさきがけだった」からだ。
明治と昭和という、二つの離れた時代について多く語られているのに対し、関川夏央の仕事では、大正時代が一つの空白であった。それも意識的に空けられた、批評の空き地のようだ。それだけに、関川夏央さんが大正文学について果たしてどう考えているのかは、非常に興味を惹かれた。
白樺派が大正文学の「代表選手」として取り上げられたのは、ある程度、予想できることだ。 関川夏央さんがいう憂国の人、完全主義の人、自己嫌悪の人、放蕩の人、親孝行の人、愛情に拘泥する人は明治の文学者に多い。自意識過剰で、友達にはしたくない人ばかりだ。その線で考えると、白樺派の作家たちに照準を合わせたのは、必然的な選択というべきなのかもしれない。同じ大正時代でも、白樺派というファインダーを通して見ると、それまでと違った風景が見えてきた。
文学批評といえば、テクストの精細な読みと、作家についてのスコラ的な考究が思い出される。それ自体は必ずしもまちがっているわけではない。一方、そうすることによって、文学が「世間」から切り離されたことも否めない。
関川夏央さんは世間の「体温」には敏感であった。文学は社会から隔絶した事象としてではなく、連綿たる精神史の流れにおいて捉えられている。小説は時代精神の表徴として読み解かれているから、個々の作品よりも、文学的な感性が醸成される土壌にまなざしが向けられている。
大正五(一九一六)年から大正九年までの三年半、日本経済は第一次大戦景気で驚くほどの成長を遂げた。イギリスの国民所得との比較、高等教育普及率、中学校、高等女学校や実業学校の生徒数などについて、正確な統計値を示しての論証は鮮やかだ。大衆が登場する過程は、観念でたどるのではなく、数字の精査を通して読み解かれている。
日露戦争の後、日本社会は急速に膨張した。文官の数が倍増し、陸軍や海軍はさらなる拡張を求めた。群衆たちも「大日本」への道を熱狂的に支持した。白樺派の理想主義は一見、社会の流れに逆行しているようだ。しかし、関川夏央さんは両者のあいだの共通点を見事に見いだした。武者小路実篤は芸術至上主義の立場から「世界に伍すべき日本」を語ったが、重税と戦後不況は「大日本」の強さによって打開されるべきだと考えた人たちも、別の意味で「世界に伍すべき日本」をイメージしていた。この指摘は同じ作家の、昭和期に入ってからの活動を説明する上でも役立つだろう。大正文学という連結器を入れた途端、前後がつながるようになっただけではなく、明治文学も昭和文学もいっそう明瞭に見えてきた。
関川夏央さんの仕事は多岐にわたるが、その中心を占めているのは、近代精神の表象という問題に対する探究である。それは取りも直さず、「現在」に対する関心であり、今日の日本人の精神構造の由来を知るためのものである。東アジア周辺国に目を転ずるのも、失われた過去を感覚的に把握するのに、横の距離感という参照軸が必要だからであろう。この作家は「いま」から離れて過去を批評したことは一度もない。
そのことを念頭において本書を読むと、いっそう興味を惹かれる。大正時代の精神史の解読は、今日を読み解く鍵になっているからだ。大企業信仰も、左翼と右翼の対立という構図も、大正時代と現代とはよく似ている。大正の人たちは口を開けば「改造」というが、現代人は「改革」をまるで宗教のように崇めている。大正時代には「自我確立」が個人にとって最大の課題であったが、現代人は「自分探し」に、パラノイア的な偏愛を示している。大正こそ現代の発端した時代だ。この指摘も、現在に対して強い関心があったからこそ導き出された結論であろう。本書が一見、重たい主題を扱いながら、読んでいて興味が尽きないのは、地に足がついているからだ。
白樺派も大正という時代も、雲の彼方に消えた歴史的な過去ではない。現在と地続きになり、現代の基盤となるものである。上品な文章を読みながら、そんな過去へとタイムスリップできるのは幸せなことだ。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする