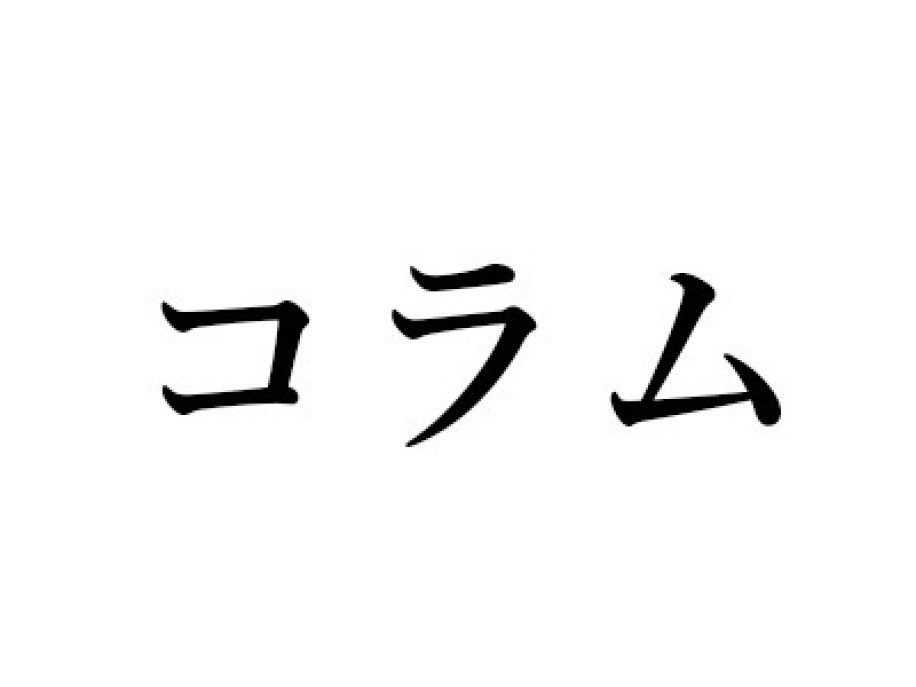書評
『きみは、どこへ行くのか』(新潮社)
「腹の虫」には泣かされて来た。
いったいどういう因果でそうなったのかわからないが、物心ついた頃にはもう妙な虫が棲みついていた。わけもわからず偉そうにコメントせずにはいられない。半可通の虫。一言居士の虫。
私はこの虫を恥じて、たびたび撲滅をはかって来たが、自分で思っていた以上にこの虫はしぶとく、あくどく、いつのまにか(十二、三年前からだろうか)私は時評的なエッセーを書くようになっていた。私自身は自分の無知無学無教養を身にしみてわかっているので、そういう僭越なことは絶対にしたくないと思っているのだが、私自身の意志や美学を踏みにじって、虫のほうが何かを書かせてしまうのだ。
私は自分の体内の虫の声を聴いて、それを活字にするべく手を動かしているだけである。虫の言うことが正しいのかどうかはよくわからないのだ。いや、正確に言うと私にとっては正しいのだが、世間一般においては正しいのかどうかはわからない。
高校時代のあの厭な一言がチラチラと頭をかすめる。生意気な女子高生だった私に担任教師は真剣なおももちで言ったものだ。
「そういう考えではクラスをミスリードします」
あのときは「ミスリードだなんて大げさな。私の影響力がそんなにあるはずないじゃないの。いちいちうるさいなあ」としか思わなかったのにもかかわらず……時評的な文章を書くようになって以来、あの一言がほとんどトラウマの如く強力に迫って来て、私を苦しめるのだ。影響力の大小はさておいて、私の書くものは世間をミスリードするような内容なんじゃないか、と。
ただ、私の書くものは時評と言っても天下国家方面のではなく下世話方面が中心、というのがまだしも救いだ。ミスリードの被害は相対的に少なめにくいとめていると思う。
天下国家方面のことに関心がないわけではないが、新聞の社説やコラム、いわゆるオピニオン雑誌の評論などは、もうひとつ読む気が起きない。その第一の理由は私の頭が悪い(=ああいう硬い文章を楽に読みこなす力がない)せいだが、第二にはああいう文章には書く人の虫の存在が感じられなくて、正しいことを言ってるのかもしれないが面白くはないからだ。
しかし、徳岡孝夫さんのコラムや評論は私にも読める。私にも楽しめる。私には欠けている学問と教養と、それから長年の新聞記者体験という厚ぼったい裏付けがあるうえに、やっぱり体内に妙な虫を飼っている人のようだから。それは、『きみは、どこへ行くのか』(新潮社)の中のこの一行に凝縮されている。
『きみは、どこへ行くのか』は一九九〇年から一九九七年までの時評集である。ゴルバチョフからエリツィンへ。ブッシュからクリントンへ。自民党単独政権から連立政権へ。時代は大きく移り変わって来たが、今、こうして一冊になったのを通して読んでみると、徳岡さんの予測や危惧がほとんど的中していることに驚かされる。最終章「もっと暗い日がくるぞ」の最後の一言なぞ、こわいですね。「山一廃業など比較にならぬ、もっと暗い日が必ず来る。日本が”官”に食い殺されて野垂死する日だ」
ジャーナリストとしてのカンというのも大きいのだろうが、そもそも人間という生きものの生態に関する眼力がものを言っているような気がする。特にファシズムに流れる人の心、独裁者に惹かれる人の心について語られるとき、いちだんと冴える。
私が最も面白く読んだのは「独裁者モブツを弔う」の章である。いきなり「もし独裁者がいなければ、この世はどんなにつまらなかったことだろう」という、ちょっとギョッとする一言で始まる。
という人間のややこしく不条理な心がよく見えているからこそ、徳岡さんの全体主義批判、独裁批判は説得力があるのだ。徳岡さんの腹の虫は、ジャーナリストというよりも古風な文学者の顔をしている。
【この書評が収録されている書籍】
いったいどういう因果でそうなったのかわからないが、物心ついた頃にはもう妙な虫が棲みついていた。わけもわからず偉そうにコメントせずにはいられない。半可通の虫。一言居士の虫。
私はこの虫を恥じて、たびたび撲滅をはかって来たが、自分で思っていた以上にこの虫はしぶとく、あくどく、いつのまにか(十二、三年前からだろうか)私は時評的なエッセーを書くようになっていた。私自身は自分の無知無学無教養を身にしみてわかっているので、そういう僭越なことは絶対にしたくないと思っているのだが、私自身の意志や美学を踏みにじって、虫のほうが何かを書かせてしまうのだ。
私は自分の体内の虫の声を聴いて、それを活字にするべく手を動かしているだけである。虫の言うことが正しいのかどうかはよくわからないのだ。いや、正確に言うと私にとっては正しいのだが、世間一般においては正しいのかどうかはわからない。
高校時代のあの厭な一言がチラチラと頭をかすめる。生意気な女子高生だった私に担任教師は真剣なおももちで言ったものだ。
「そういう考えではクラスをミスリードします」
あのときは「ミスリードだなんて大げさな。私の影響力がそんなにあるはずないじゃないの。いちいちうるさいなあ」としか思わなかったのにもかかわらず……時評的な文章を書くようになって以来、あの一言がほとんどトラウマの如く強力に迫って来て、私を苦しめるのだ。影響力の大小はさておいて、私の書くものは世間をミスリードするような内容なんじゃないか、と。
ただ、私の書くものは時評と言っても天下国家方面のではなく下世話方面が中心、というのがまだしも救いだ。ミスリードの被害は相対的に少なめにくいとめていると思う。
天下国家方面のことに関心がないわけではないが、新聞の社説やコラム、いわゆるオピニオン雑誌の評論などは、もうひとつ読む気が起きない。その第一の理由は私の頭が悪い(=ああいう硬い文章を楽に読みこなす力がない)せいだが、第二にはああいう文章には書く人の虫の存在が感じられなくて、正しいことを言ってるのかもしれないが面白くはないからだ。
しかし、徳岡孝夫さんのコラムや評論は私にも読める。私にも楽しめる。私には欠けている学問と教養と、それから長年の新聞記者体験という厚ぼったい裏付けがあるうえに、やっぱり体内に妙な虫を飼っている人のようだから。それは、『きみは、どこへ行くのか』(新潮社)の中のこの一行に凝縮されている。
差し障りがあるかもしれないが、自分を欺いて賢人ぶるより、たとえ浅薄でも感じたことを正直に書くべきだと思う。――
『きみは、どこへ行くのか』は一九九〇年から一九九七年までの時評集である。ゴルバチョフからエリツィンへ。ブッシュからクリントンへ。自民党単独政権から連立政権へ。時代は大きく移り変わって来たが、今、こうして一冊になったのを通して読んでみると、徳岡さんの予測や危惧がほとんど的中していることに驚かされる。最終章「もっと暗い日がくるぞ」の最後の一言なぞ、こわいですね。「山一廃業など比較にならぬ、もっと暗い日が必ず来る。日本が”官”に食い殺されて野垂死する日だ」
ジャーナリストとしてのカンというのも大きいのだろうが、そもそも人間という生きものの生態に関する眼力がものを言っているような気がする。特にファシズムに流れる人の心、独裁者に惹かれる人の心について語られるとき、いちだんと冴える。
私が最も面白く読んだのは「独裁者モブツを弔う」の章である。いきなり「もし独裁者がいなければ、この世はどんなにつまらなかったことだろう」という、ちょっとギョッとする一言で始まる。
独裁者は違う。虫ケラのような民衆を憚らない。自己の信じるところを行う。日本の総理大臣や銀行の頭取や証券会社の社長みたいに、紙を見て喋らない。メモなしで好きなことを言う。強い独裁者は、人さえ平気で殺す。許せないヤツが多いが、われわれはヤンキースの伊良部の成績が気になるように、なぜか独裁者から目を離せない
という人間のややこしく不条理な心がよく見えているからこそ、徳岡さんの全体主義批判、独裁批判は説得力があるのだ。徳岡さんの腹の虫は、ジャーナリストというよりも古風な文学者の顔をしている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする