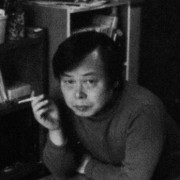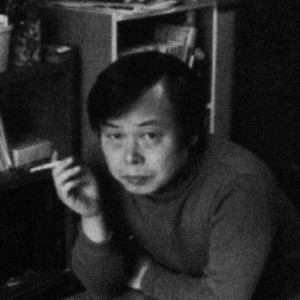書評
『楽園のイングランド―パラダイスのパラダイム』(河出書房新社)
楽園としての書物
無限にひろがる外の世界に対してそこだけ囲われた小宇宙。それが洋上にあれば島の楽園であり、陸上にあれば庭の楽園、不安な生そのものに対して最終的に囲われた小宇宙であれば墓の楽園である。島、庭、墓は、いずれも外界の激動から逃れた先で無為寂滅の至福をゆあみしている、ほとんどあられもない胎内還帰願望の対象としてのトポス(場所)といえよう。しかしそれ自体が島国であってデフォーからスティーヴンソンにいたるおびただしい島冒険小説に恵まれ、十八世紀の文人の多くが造園家・庭師であり、グレイのような詩人の墓畔詩のみならず、幽霊小説が御家芸であるような英国では、それがいわばコモンセンスだった。といって本書は楽園的トポスとしての島、庭、墓のありきたりの文学的観光案内ではない。楽園は、それが楽園であるべきはずでありながら、かえって両価感情の対象となる。王党派が囲われた小世界としての島にあこがれたのに対して、清教徒にとっても、三〇年代のオーデンにとっても、島は行動の障害となる小さな安息の場として嫌悪の対象でしかなかった。「庭園」の詩人マーヴェルは、清教徒陣営に移行した時期から島の楽園性に微妙なかげりを投じる。ことほど左様に、本来無時間的な場所であったはずの楽園は、一転してはげしい政治的抗争の場となった。しかし楽園の閉鎖性を踏破した英国の帝国主義的拡張が極限に達すると、皮肉にも、ふたたび庭や島は収縮しはじめて、ちいさなガラス箱や靴墨の空き瓶のなかのミニチュア庭園となってしまう。
以上、英文学史の細部に則して楽園表象の転変を明らかにしてゆく、『マーヴェルの庭』以来の著者の筆は、一段とたのしげにもあざやかである。ただしエスキスのままのこされた部分もある。著者は過ぐる一九八九年に物故されたからだ。巻末に友人出淵博氏によるトルソを補うような懇切な解説がある。生前の著者のひそやかながら手堅い読者はすくなくなかった。もはや次著の期待できないのは惜しみてあまりあるとはいえ、ここに端正で気品の高い「楽園としての書物」がある。読者にとってのせめてものなぐさめである。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1991年4月14日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする