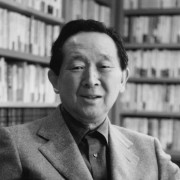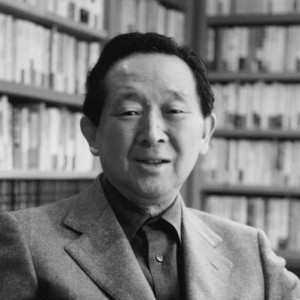書評
『中世の秋』(中央公論新社)
昨今のアメリカや日本、そしてEU社会の動きを見ていると、僕は歴史家ヨハン・ホイジンガ(一八七二-一九四五)が書いた『中世の秋』を思い出してしまうのだ。
僕がはじめてこの本に接したのは七〇年代のはじめ、兼岩正夫、里見元一郎の訳(創文社)によってである。五〇年代の終りに邦訳が出てから十刷以上になっているから、かなり多くの人に読まれたのだと思う。
僕がなぜこの本を読むようになったのか、自分の動機は覚えていない。ただ、今になって振返ってみれば、六〇年安保の大きな波の後、新憲法感覚と、内容よりもやり方の穢(きたな)さ、狡さの方が人々を怒らすという、しいて言えば昔ながらの儒教的感性に基く判断の前に岸内閣が倒れ、六四年頃から高度成長路線に入って、人々が精神的なものよりもっぱら豊かさを追い求めるようになったことに僕自身大きな矛盾を感じていたことは確かである。自分が勤めているところがその豊かさを演出する百貨店のような業種であったことが、二重に僕の気持を圧迫していたのだった。七〇年安保も六〇年に較べれば静かで、よく識っていた三島由紀夫が日本の行く末に絶望して自裁したのは七〇年であった。
ホイジンガはこの本の第二章、「美しい生活への憧れ」の冒頭で、「いつの時代も一層美しい世界へと憧れるものである。混乱した現在への絶望と苦痛が深まるほど、ますますその憧れは激しい」と書き、第十七章「日常生活の思想形式」では、「中世末期の人間の皮相浅薄、でたらめ、軽信に絶えず示されている独特の軽佻浮薄さは結局どう考えるべきものだろう。彼等は屢(しばしば)々(しばしば)真の思考というものを全然必要としない様だし、またそこはかとない幻像をかいま見ることだけで精神の満足を覚えている如く思われる」と分析している。
僕はこれを読んだ時、ひとつの体制の終りの時はいつもそうなのだ、という感想を抱き、現代を「産業社会の秋」と呼んでいいのではないか、と考えた。これは歴史というものを教わった著作として忘れ難い。
【この書評が収録されている書籍】
僕がはじめてこの本に接したのは七〇年代のはじめ、兼岩正夫、里見元一郎の訳(創文社)によってである。五〇年代の終りに邦訳が出てから十刷以上になっているから、かなり多くの人に読まれたのだと思う。
僕がなぜこの本を読むようになったのか、自分の動機は覚えていない。ただ、今になって振返ってみれば、六〇年安保の大きな波の後、新憲法感覚と、内容よりもやり方の穢(きたな)さ、狡さの方が人々を怒らすという、しいて言えば昔ながらの儒教的感性に基く判断の前に岸内閣が倒れ、六四年頃から高度成長路線に入って、人々が精神的なものよりもっぱら豊かさを追い求めるようになったことに僕自身大きな矛盾を感じていたことは確かである。自分が勤めているところがその豊かさを演出する百貨店のような業種であったことが、二重に僕の気持を圧迫していたのだった。七〇年安保も六〇年に較べれば静かで、よく識っていた三島由紀夫が日本の行く末に絶望して自裁したのは七〇年であった。
ホイジンガはこの本の第二章、「美しい生活への憧れ」の冒頭で、「いつの時代も一層美しい世界へと憧れるものである。混乱した現在への絶望と苦痛が深まるほど、ますますその憧れは激しい」と書き、第十七章「日常生活の思想形式」では、「中世末期の人間の皮相浅薄、でたらめ、軽信に絶えず示されている独特の軽佻浮薄さは結局どう考えるべきものだろう。彼等は屢(しばしば)々(しばしば)真の思考というものを全然必要としない様だし、またそこはかとない幻像をかいま見ることだけで精神の満足を覚えている如く思われる」と分析している。
僕はこれを読んだ時、ひとつの体制の終りの時はいつもそうなのだ、という感想を抱き、現代を「産業社会の秋」と呼んでいいのではないか、と考えた。これは歴史というものを教わった著作として忘れ難い。
【この書評が収録されている書籍】
中央公論 2006年12月
雑誌『中央公論』は、日本で最も歴史のある雑誌です。創刊は1887年(明治20年)。『中央公論』の前身『反省会雑誌』を京都西本願寺普通教校で創刊したのが始まりです。以来、総合誌としてあらゆる分野にわたり優れた記事を提供し、その時代におけるオピニオン・ジャーナリズムを形成する主導的役割を果たしてきました。
ALL REVIEWSをフォローする