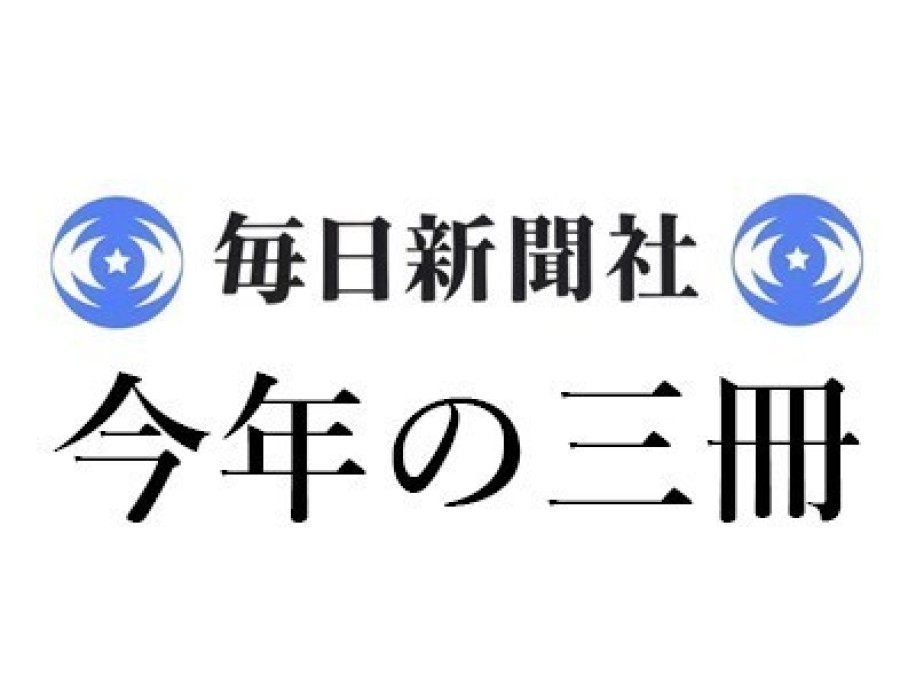解説
『カワハギの肝』(光文社)
『カワハギの肝』は食物随筆としては異彩を放っている。それはなぜかといえば、世にさきわう食物随筆の多くが、自らの味覚がどれほど繊細であるかを暗黙の諒解事項として、あるいは、料理というのはきわめればきわめるほど一流の芸術に近づくという、西洋、いや、もっとはっきり言えば、フランス料理の理想を前提として書かれているのに対して、杉浦明平の随筆はいうなれば、老人の繰り言、ないし老人の一徹な思いこみがどれだけ読者の心に訴えるかという証明となっているからである。
たとえば、ビフテキについて彼はこう書く。
鶏肉についてはこうだ。
柔らかなものを蛇蝎のごとく嫌い、甘いものを極力排するという杉浦明平のこうした発想は、軟弱な私などからすると、まさに文字通りの硬骨漢ならではのものであり、他の食物随筆では味わえない言葉のつらなりである。硬骨漢だからこそ妥協とは無縁である。京都の味についてはまさに一刀両断。こんな言葉を堂々と書きつける。
昔、この本を最初に手にしたとき、私は随所に見られる杉浦明平の一徹ぶりにほとんど嫉妬していたといっていい。こんな「へつらわない」生き方ができたらどんなにすてきだろう。
干麺はうどんとは別物だと言ったあとで、彼は次のように書きつける。
その店としても「詐欺」呼ばわりは心外であろう。何も生のうどんですと言って「干麺」を出したわけではないからである。しかし、この啖呵は胸がすく。べつにそのうどん屋でなくとも、これに似た思いは誰だって味わったことがあるのではなかろうか。外で食べたときに、よくこれで金を取るねえとか、こんなもの出して恥ずかしくないのかしら、と言いたくなったことがない人は、よほど仏のごとく人がいいか、舌莫迦かのどちらかである。
結局、うまいかまずいかは本人の好き好きというほかない。それを痛烈に味わわせてくれる食物随筆というのがほかにあっただろうか。たいていのものは、読者を唸らせることで成り立っている。うーん、さすが繊細な舌の持ち主だこと、いっぺん食べて見たいね、というように。そういう随筆はそれはそれで愉しいけれど、そういつもひとさまの味談義を聞いてばかりはいられない。自分だって日に三度は食べるからである。そういうとき、杉浦明平のこんな言葉は、私たちにどこかで勇気を与えてくれる。
これに匹敵するのは、群馬のある駅前の安食堂で食べたトンカツが旨いという吉田健一の食物随筆くらいしかない。
ただ、杉浦明平にあって吉田健一にないものは、まさに「老いの一徹」で野菜をつくり、蜂蜜をつくってしまう実践家としての姿勢である。たとえば、安心できるおいしい野菜をふんだんに食べるために、みずから畑を耕してつくらないではいられないというのは、他の随筆家には見られないことだ。料理の天才というべき檀一雄すら、そこまではしなかったような気がする。なにしろ、杉浦明平は「若ゴボウを食べたいばかりに、毎年毎年失敗しながらも、秋蒔をやめない」のだ。あるいは、年中辛い大根おろしを食べるためには「自分で栽培するよりほかはない」と悟って、青首大根をつくってしまうのである。晴耕雨読という文人の理想の具現というより、まずはうまいものを食べたいがゆえの「晴耕」。プラス、好きであるがゆえの読書。それにまして貪欲な食生活、精神生活というものがあるだろうか。
貪欲に食べるというのは、生きる原点である。と同時に、時代がつねに変転するかぎり、料理や食べ物はどこかでかならず失われた楽園の記憶をのこしている。人生は失われた楽園を背後にもつがゆえに美しく、いとおしい。そして、たとえ偏屈と言われようと、世に迎合せず、媚びないほうが、結局は生きていて愉しい。生のナマコやフノリ、ローストチキン、チョコレート、一夜漬けの辛いラッキョウ、筍と梅酢、ヤマモモ、そして言うまでもなく、カワハギの肝……。杉浦明平は本書で、自由闊達で気取らない文章を駆使しつつ、さまざまな食べ物の魅力について語りながら、そのことをさりげなく教えてくれるだろう。
たとえば、ビフテキについて彼はこう書く。
ビフテキとは脂っ気がなく、歯ごたえがあるどころか歯痛をおこすほどかたい肉をかみしめているうちに甘い肉汁がにじみ出てくるものだという観念がわたしの中に深く植えつけられてしまったようである。
鶏肉についてはこうだ。
いつか名古屋コーチン系の老牝鶏を水炊きにしてたのしんでいるさいちゅう、かたい肉を骨から引きはがそうとしたとたん、入れ歯の方が折れてしまったという苦い経験をもっているにもかかわらず、柔らかな、しまりのない鶏肉はまっぴら、入れ歯が折れるくらいのこわい肉の方が好きなのである。
柔らかなものを蛇蝎のごとく嫌い、甘いものを極力排するという杉浦明平のこうした発想は、軟弱な私などからすると、まさに文字通りの硬骨漢ならではのものであり、他の食物随筆では味わえない言葉のつらなりである。硬骨漢だからこそ妥協とは無縁である。京都の味についてはまさに一刀両断。こんな言葉を堂々と書きつける。
京都は海から遠くて、海の幸にめぐまれていない。(略)うまい料理がつくれぬかわり、目でごまかそうとして、いわゆる四季の色をそえた日本料理が発達したのであろうが、肝心の味については、文化の中心地京都で、うまいものといったら、漬け物だけということになった。
一千年もまずいものばかり食っていたら、味覚も衰弱してしまう。今でも京都の古い家の家庭料理のまずいこと、とてもお話にも何にもならぬ。
昔、この本を最初に手にしたとき、私は随所に見られる杉浦明平の一徹ぶりにほとんど嫉妬していたといっていい。こんな「へつらわない」生き方ができたらどんなにすてきだろう。
干麺はうどんとは別物だと言ったあとで、彼は次のように書きつける。
最近も東京駅地下街で、釜揚げうどんの名前に釣られて注文したところ、干麺をゆでたものが出てきた。まさに詐欺にひっかかったのである。それ以来その店の前を通るときはペッと唾を吐くことにしている。
その店としても「詐欺」呼ばわりは心外であろう。何も生のうどんですと言って「干麺」を出したわけではないからである。しかし、この啖呵は胸がすく。べつにそのうどん屋でなくとも、これに似た思いは誰だって味わったことがあるのではなかろうか。外で食べたときに、よくこれで金を取るねえとか、こんなもの出して恥ずかしくないのかしら、と言いたくなったことがない人は、よほど仏のごとく人がいいか、舌莫迦かのどちらかである。
結局、うまいかまずいかは本人の好き好きというほかない。それを痛烈に味わわせてくれる食物随筆というのがほかにあっただろうか。たいていのものは、読者を唸らせることで成り立っている。うーん、さすが繊細な舌の持ち主だこと、いっぺん食べて見たいね、というように。そういう随筆はそれはそれで愉しいけれど、そういつもひとさまの味談義を聞いてばかりはいられない。自分だって日に三度は食べるからである。そういうとき、杉浦明平のこんな言葉は、私たちにどこかで勇気を与えてくれる。
さらに高級な店ともなれば、その店特製のソースが上品微妙すぎて、わたしの荒っぽい舌には適しない。わたしには、カゴメ・ソースとかブルドッグ・ソースとか市販のソースが一番いいようである。
これに匹敵するのは、群馬のある駅前の安食堂で食べたトンカツが旨いという吉田健一の食物随筆くらいしかない。
ただ、杉浦明平にあって吉田健一にないものは、まさに「老いの一徹」で野菜をつくり、蜂蜜をつくってしまう実践家としての姿勢である。たとえば、安心できるおいしい野菜をふんだんに食べるために、みずから畑を耕してつくらないではいられないというのは、他の随筆家には見られないことだ。料理の天才というべき檀一雄すら、そこまではしなかったような気がする。なにしろ、杉浦明平は「若ゴボウを食べたいばかりに、毎年毎年失敗しながらも、秋蒔をやめない」のだ。あるいは、年中辛い大根おろしを食べるためには「自分で栽培するよりほかはない」と悟って、青首大根をつくってしまうのである。晴耕雨読という文人の理想の具現というより、まずはうまいものを食べたいがゆえの「晴耕」。プラス、好きであるがゆえの読書。それにまして貪欲な食生活、精神生活というものがあるだろうか。
貪欲に食べるというのは、生きる原点である。と同時に、時代がつねに変転するかぎり、料理や食べ物はどこかでかならず失われた楽園の記憶をのこしている。人生は失われた楽園を背後にもつがゆえに美しく、いとおしい。そして、たとえ偏屈と言われようと、世に迎合せず、媚びないほうが、結局は生きていて愉しい。生のナマコやフノリ、ローストチキン、チョコレート、一夜漬けの辛いラッキョウ、筍と梅酢、ヤマモモ、そして言うまでもなく、カワハギの肝……。杉浦明平は本書で、自由闊達で気取らない文章を駆使しつつ、さまざまな食べ物の魅力について語りながら、そのことをさりげなく教えてくれるだろう。
ALL REVIEWSをフォローする