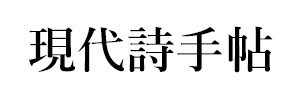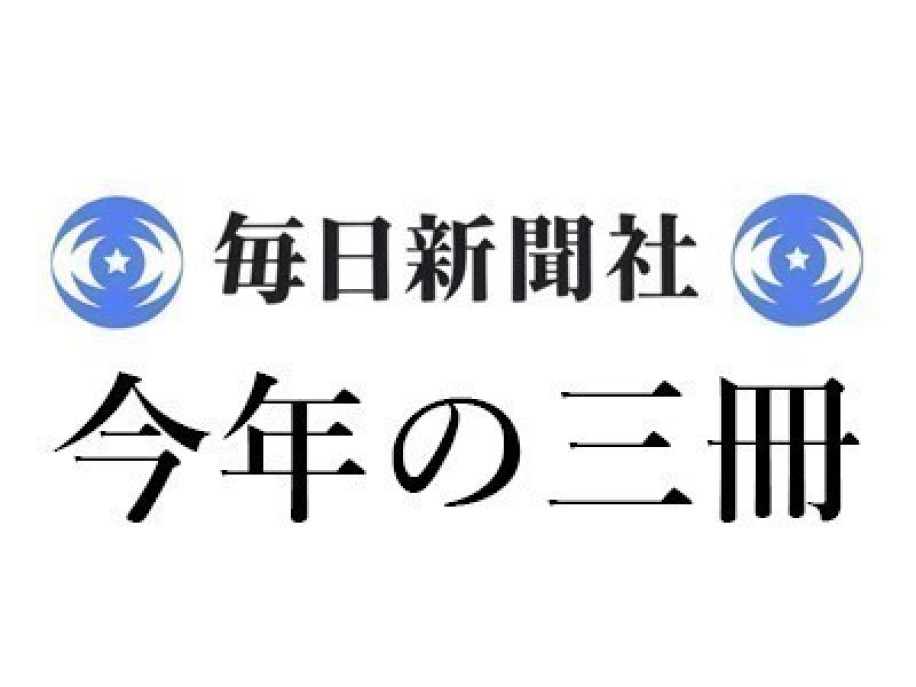書評
『ロギカ/レトリカ』(砂子屋書房)
よく書きこまれた一冊である。思索のひだが著者の生理的な等身大に息づいている。誠実な筆致。昔なつかしい小路にふと舞いもどったような気がした。
著者は、詩という名のことばの極限へ、果敢な漸近をはかる。素材はニーチェであり、一遍であり、ハイデガーであり、賢治・埴谷その他存在を見つめた日本の作家たちである。そして議論の要所では吉本隆明が、後見人の姿をあらわす。
素材の色濃い宗教性に、なにより注目すべきだろう。著者もまた求道者である。ほとんど書けそうにないことだけを、己れに課すとみえる。どの行も模索と呻吟に満ちている。こうした倫理的苦行の果てに、著者は救済の輪郭を望見しようとする。それは解放であってよいはずだ。だが私はかすかに、閉塞感と報われない疲労のほうを感じてしまう。気のせいだろうか?
現代詩に縁のない私は、本書がどれほど現下の詩人たちの切実な懊悩に応えるものか、見当がつかない。社会学者として見取った限りをのべるしかない。
著者菅谷氏がドイツ文学者としてどのような境位をえているかに、興味をひかれる。
たとえば著者は、ハイデガーの章句に自分の訳を充てる。ことばと存在をめぐる西欧の思索が日本語に置き換わる/換わらぬことに批評の根拠をおくようだ。そしてたとえば、ザイン(普遍存在の概念)を駆使してついに見逃される可能性が、ある/いるの区別によればわれわれにひらかれるという。神がいなくともよい。有情との交響。自然との和解。ーこのみちすじはよく解る。だが問おう、著者は何語でこれを考えたのか?
著者は日本語で思索し、書を著す。日本の風土に根ざし、それを引き受けるべく。よろしい。安直な舶来屋より格段ましだ。が、それにしては、この風土に対する異和の角度と方法が不足していないか。あるいは、著者の想い描く西欧が、日本語に置き換えたがために不用意に変歪していないか。あるいは、同じ思想をドイツ語で表現する普遍性よりも、吉本言語論に内属する自足を選んでいないか。
吉本氏は当代の国学者である。氏は、マルクス主義のロシア的変歪に抗して、己れの肉声でマルクスを思索することからはじめ、ついに浄土教的な共和思想を結実した。これはなおさらの変歪であるが、そうとう自覚的になされ、それゆえの世界性をもつ。しかし著者は吉本氏を権威とするあまり、この変歪をしかと見据えていない気がする。そのため西欧思想本来の恰幅が、著者の手のなかでいくぶん痩せてしまう。惜しむべきである。
中程度の異論(ハイデガーの「ことばがはなす」は喩でなく、文字通り機械論では?/トラークルの詩の乞食は、晩餐に臨むイエスその人では?/啓示宗教でことばはまず法なのでは?/要するに本書のキリスト教は浄土教と似すぎていないか?……)のゆえに、私は著者の結論を留保するが、詳論の紙幅はない。最後に。書評を機縁に本書に触れえたことを謝し、広く江湖にむかえられんことを祈る。
【この書評が収録されている書籍】
著者は、詩という名のことばの極限へ、果敢な漸近をはかる。素材はニーチェであり、一遍であり、ハイデガーであり、賢治・埴谷その他存在を見つめた日本の作家たちである。そして議論の要所では吉本隆明が、後見人の姿をあらわす。
素材の色濃い宗教性に、なにより注目すべきだろう。著者もまた求道者である。ほとんど書けそうにないことだけを、己れに課すとみえる。どの行も模索と呻吟に満ちている。こうした倫理的苦行の果てに、著者は救済の輪郭を望見しようとする。それは解放であってよいはずだ。だが私はかすかに、閉塞感と報われない疲労のほうを感じてしまう。気のせいだろうか?
現代詩に縁のない私は、本書がどれほど現下の詩人たちの切実な懊悩に応えるものか、見当がつかない。社会学者として見取った限りをのべるしかない。
著者菅谷氏がドイツ文学者としてどのような境位をえているかに、興味をひかれる。
たとえば著者は、ハイデガーの章句に自分の訳を充てる。ことばと存在をめぐる西欧の思索が日本語に置き換わる/換わらぬことに批評の根拠をおくようだ。そしてたとえば、ザイン(普遍存在の概念)を駆使してついに見逃される可能性が、ある/いるの区別によればわれわれにひらかれるという。神がいなくともよい。有情との交響。自然との和解。ーこのみちすじはよく解る。だが問おう、著者は何語でこれを考えたのか?
著者は日本語で思索し、書を著す。日本の風土に根ざし、それを引き受けるべく。よろしい。安直な舶来屋より格段ましだ。が、それにしては、この風土に対する異和の角度と方法が不足していないか。あるいは、著者の想い描く西欧が、日本語に置き換えたがために不用意に変歪していないか。あるいは、同じ思想をドイツ語で表現する普遍性よりも、吉本言語論に内属する自足を選んでいないか。
吉本氏は当代の国学者である。氏は、マルクス主義のロシア的変歪に抗して、己れの肉声でマルクスを思索することからはじめ、ついに浄土教的な共和思想を結実した。これはなおさらの変歪であるが、そうとう自覚的になされ、それゆえの世界性をもつ。しかし著者は吉本氏を権威とするあまり、この変歪をしかと見据えていない気がする。そのため西欧思想本来の恰幅が、著者の手のなかでいくぶん痩せてしまう。惜しむべきである。
中程度の異論(ハイデガーの「ことばがはなす」は喩でなく、文字通り機械論では?/トラークルの詩の乞食は、晩餐に臨むイエスその人では?/啓示宗教でことばはまず法なのでは?/要するに本書のキリスト教は浄土教と似すぎていないか?……)のゆえに、私は著者の結論を留保するが、詳論の紙幅はない。最後に。書評を機縁に本書に触れえたことを謝し、広く江湖にむかえられんことを祈る。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする