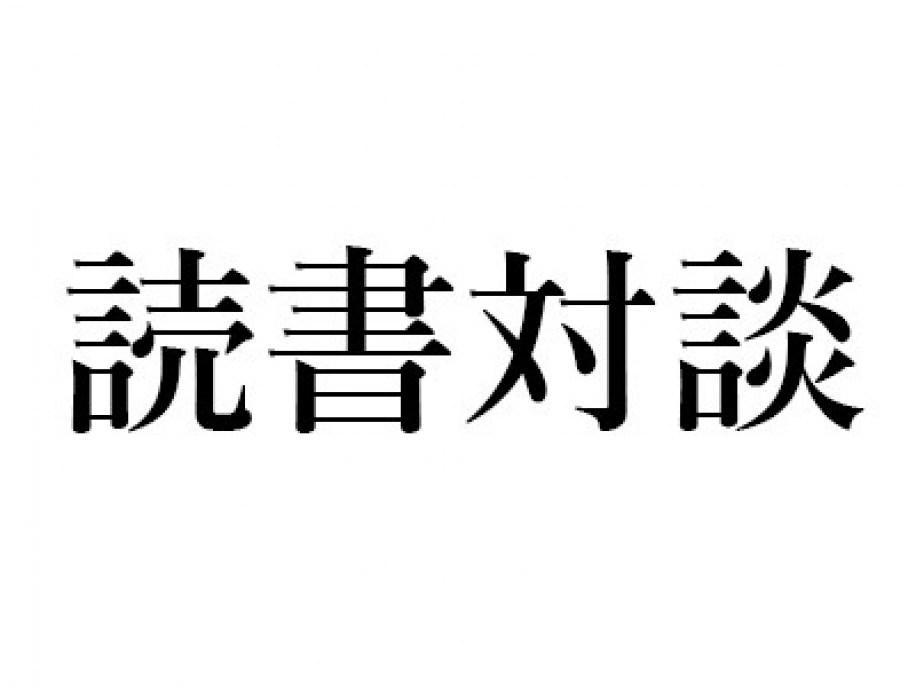解説
『大菩薩峠〈9〉』(筑摩書房)
可哀想に幸内は、主膳が酒乱の犠牲となって、弄り殺しにされなければ納まらないでしょう。弄り殺しにした上に、その屍骸を粉々にしなければ納まりそうにありません。
主膳は悪魔の呻るように、ウンウンと力を籠めて綱を引きました。力余って釣瓶を井戸車の上まではね上げてしまいました。井戸の水は、滝が巌に砕けるように一時にパッと飛び散りました。
「うーん」
その途端に神尾主膳は、どうしたハズミか二三間後ろへドウ(手偏に堂)と尻餅を掲いてしまいました。釣瓶は凄まじい音をして井戸の底へ落ちて行きました。(「伯書の安綱の巻」)
神尾主膳と酒乱と井戸と無辜の犠牲者、そして、その背後に潜むお銀様の影。この五つがそろったとき、突然のように、デーモンが神尾主膳に宿る。
躑躅ケ崎の古屋敷にこれと同じような井戸があった、その井戸で、和女の好きな幸内とやらに、たんと水を呑ましてやったことがあるわい、それから以来、夕方にこの車井戸の軋る音を聞くと、拙者は胸が悪くなってたまらぬ、この車井戸の音が癩にさわる。(「黒業白業の巻」)
どうやら、神尾主膳とお銀様は、「酒と井戸水」という液体とそれが呼びこむ犠牲者という二重のハイフンによって繋がれた関係にあるらしい。実際、物語はその通りに進行し、神尾主膳は、お銀様が腕に針を刺して写経をしている夜、鈴慕の音に誘われて化物屋敷に迷い込んだ弁信を井戸にたたき込もうとする。
その車井戸がギーッと軋る音を聞くと、お銀様はゾッと身の毛を竪てました。お銀様は夜中に車井戸の軋る音を何よりも嫌います。その音がいやだから一旦はゾッとしたけれども、すぐに摘まみ上げた第二本目の針を、何の躊躇もなく、プツリと左の二の腕へ差し込みました。真っ赤な血汐の粒がホロホロと湧き上がりました。お銀様はそれをチクリチクリと深く刺し込みます。その度ごとに少しずつこたえていく痛みが、なんともいえない快感を与えるものらしくあります。その時、車井戸の音がまたキリキリと鳴りました。それと同時にけたたましい物音が、井戸側のあたりで起こりました。
「汝れ夜中、人の住居をうかがうとは怪しからん奴じゃ、誰に頼まれて何しに来た、それを言わぬと、この井戸へ投げ込むからそう思え、さあ、誰に頼まれて何しにきた、真っ直に言え」
こう言って罵っているのは、他ならぬ神尾主膳の声であります。しかも主膳が酔っぱらって酒乱になっているときの声であります。(「小名路の巻」)
さながら、お銀様が腕に刺しこんで湧き上がらせた血汐の粒が、井戸水、犠牲者、酒ときて最後に神尾主膳を呼び寄せたようではないか。そう、ここでは、従来の五点セットに新たに「血」という液体が加わっている。そして、次に、その血は、お銀様から、井戸水と酒と犠牲者を介して、神尾主膳の額の上へと移動する。すなわち、弁信をたたき込もうとした弾みで井戸綱が切れ、凶器となった釣瓶の一端が神尾主膳の額から牡丹餅大の肉を削ぎ取ったのだ。
それだと思ったから、お銀様はいよいよ痛快に堪えませんでした。痛快というよりはこの時のお銀様は、正しく神尾主膳の残忍性が乗りうつったかと思われるほどに、いい心持ちになりました。(「小名路の巻」)
『大菩薩峠』の、外目には見えない構造上の「臍」は、まさにここにある。神尾主膳とお銀様は、たしかに一対のカップル、「夫婦」なのだ。『大菩薩峠』が、他に類を見ないような異常な小説、「変な小説」になっているのは、このお銀さまと神尾主膳という世にも面妖な相似形カップルの生み出す倍加された衝迫のためである。
したがって、物語としての緊張感は、このカップルが直接的に槍と脇差で対峙する「禹門三級の巻」で頂点に達する。ここは、机竜之助のいかなる戦いよりも、はるかに迫力があり、全編のクライマックスと呼んでいい。
樫の木を移ってお銀様が、石燈籠の蔭へ避けた時に、神尾主膳はさながら絵に見る悪鬼の形相です。いかなるところへ逃げ隠れようとも、この怨敵を突き伏せずにしては置かずという意気込みで、燈籠の屋根の上や、台石の横から無二無三に突き立てました。
(……)
お銀様は石燈籠の蔭から追いつめられたのが池の端です。池の汀を伝って逃げると巌石がある。後ろへすされば一歩にして水です。進退谷まったお銀様は、ついに脇差を振り上げて、勢い込んで追いかけて来た神尾主膳の面をのぞんで、その脇差を投げつけました。
その覘いは過たず、神尾の面上へ飛んで来たから、狂乱の神尾も落ちかかる刃を払わずにはおられません。それを槍の柄で払おうとして、あぶない足許が一層あぶなくなって、ついにたまらずドウ(手偏に堂)と尻餅をついたのが、お銀様にとっては命の親でありました。(「禹門三級の巻」)
これ以降、お銀様と神尾主膳はふたたび相まみえることはない。双方が、それぞれ独立したエンジンとして、物語を駆動させようとする。しかし、この片肺飛行は、必然的に、『大菩薩峠』という飛行機の飛翔力を弱めることになる。
だが、中里介山は、どうやら、物語の最後の最後で、このカップルをもう一度、対峙させようと考えていたらしい。なぜかといえば、神尾主膳は「椰子林の巻」で、探索方として京都に潜入しようとするからである。京都と、お銀様のいる大江山では目と鼻の先である。これはどうあっても、二人は再度、遭遇するほかはない。そうなったら、『大菩薩峠』はふたたび駆動力を得て、とんでもない高みへと舞い上がっていったはずである。そして、さらにさらに「変な小説」となり、最後は、小説ですらなくなってしまうかもしれなかったのだ。中里介山は、『大菩薩峠』を書きつぎながら、きっとこうつぶやいていたに相違ない。
「机竜之助は私だ。いや私だった。いまは神尾主膳が私だ。ということはお銀様も私だということになる。こうなるほかはなかったのだ……」
【『大菩薩峠』1巻はこちら】
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする