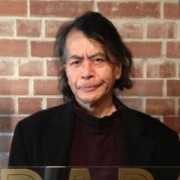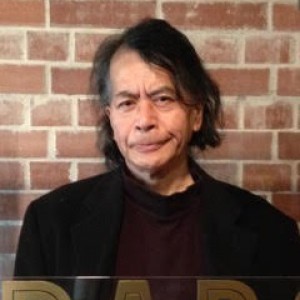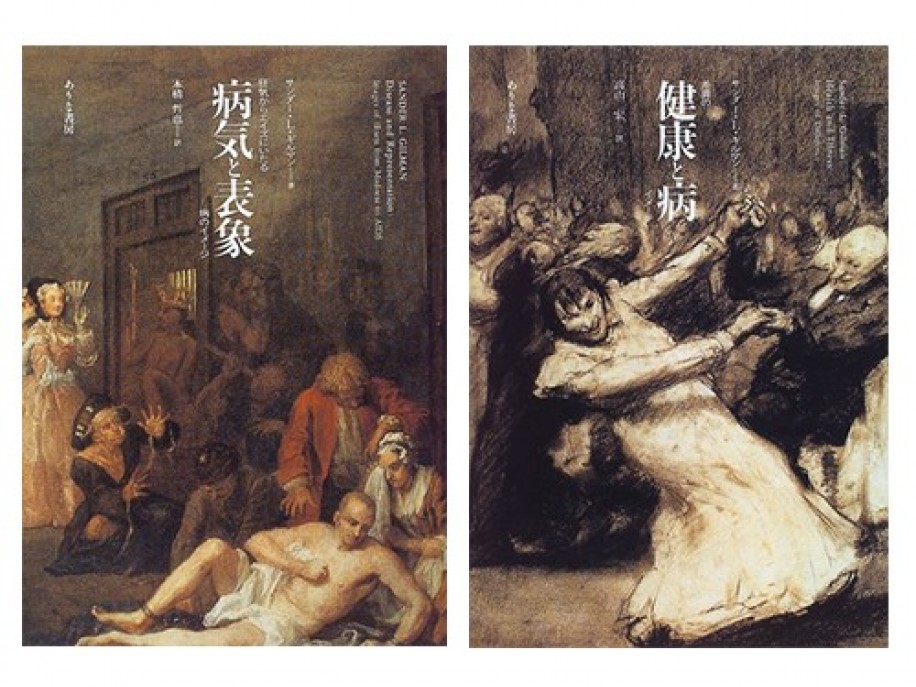後書き
『シェイクスピア・カーニヴァル』(平凡社)
『シエイクスピアはわれらの同時代人』のヤン・コットが、今度はバフチーンを使ってシェイクスピア再読を企てようとしているらしいという噂をもたらしてくれたのは山口昌男氏であった。文字通り鶴首待望していた著作だが、落掌してみるとバフチーンものは二篇で、あと二篇は『嵐』をめぐり、ほぼ『シェイクスピアはわれらの同時代人』中の『嵐』論の主旨をほぼ正確になぞったもので、バフチーンとは直接にはかかわらない。ここでは、ひとつの古典(「ウェルギリウス的コード」)がいかに換骨奪胎されて新しい作品を生みだしていくかを追っていくコットの綿密なテクスト読みの腕前を、じっくりと味わってもらえるだろう。古いものがそうやって新しいものと「対話」しながら文学テクストをつくりだしていく連続性なり伝統なりがもはや存在しなくなったことを、この『嵐』論は言おうとする。伝統の終熄。そう言えばフォースタス博士もプロスペローも、「絶望」し、終りの感覚にうちひしがれた知識人として描かれている。もしかしたら、ふたつのカーニヴァル演劇論とふたつの『嵐』論をつなぐ見えざる主題は「終りの感覚」なのだ、と言うべきなのかもしれない。「断想」に入れられた三篇の小文も、みな一様に断絶と終りのドラマトゥルギーを問題にしているように思われる。緊迫した人間悲劇を描く三文ゆえ、ド手くそな英語原文(ここではむろん英訳者のせい?)を、思いっきり緊迫感のある高密度の訳文に変成(?)してある。翻訳のエクスターシスを感じた、貴重な時間であった。
ヤン・コットは『シェイクスピアはわれらの伺時代人』(一九六一)のあと、主にポーランド演劇を論じたエッセーを集めた『演劇ノート一九四七ー六七年』(一九六八)を出し、レヴィ=ストロースだのジャック・モノー(『偶然と必然』)だのを援用してギリシア悲劇を不条理演劇として読む『神が/を啖(くら)う』(一九七二)を出している。そしてその頃にバフチーン読みが本格化したもののようで、次作『本質の演劇』(一九八四)では、シェイクスピアとはうってかわり、ゴンブロヴィッチやイオネスコをバフチーンのカーニヴァル論で切って見せている。この現代演劇論でジョージ・ジーン:ネイサン賞(一九八五)を受けているが、これもぜひ邦訳さるべき内容の充実を誇る一著である。「すぐれた人類学者マサオ・ヤマグチ」が引き合いに出されていたりして、非常に面白い。
(*)Jan Kott, Przycynek do biografii(Aneks Pub; London, 1990)[のちStill Aliveとして英訳。Yale Univ. Press, 1994. のち邦訳も。『ヤン・コット 私の物語』みすず書房一九九五]
【文庫版】
【この後書きが収録されている書籍】
ヤン・コットは『シェイクスピアはわれらの伺時代人』(一九六一)のあと、主にポーランド演劇を論じたエッセーを集めた『演劇ノート一九四七ー六七年』(一九六八)を出し、レヴィ=ストロースだのジャック・モノー(『偶然と必然』)だのを援用してギリシア悲劇を不条理演劇として読む『神が/を啖(くら)う』(一九七二)を出している。そしてその頃にバフチーン読みが本格化したもののようで、次作『本質の演劇』(一九八四)では、シェイクスピアとはうってかわり、ゴンブロヴィッチやイオネスコをバフチーンのカーニヴァル論で切って見せている。この現代演劇論でジョージ・ジーン:ネイサン賞(一九八五)を受けているが、これもぜひ邦訳さるべき内容の充実を誇る一著である。「すぐれた人類学者マサオ・ヤマグチ」が引き合いに出されていたりして、非常に面白い。
(*)Jan Kott, Przycynek do biografii(Aneks Pub; London, 1990)[のちStill Aliveとして英訳。Yale Univ. Press, 1994. のち邦訳も。『ヤン・コット 私の物語』みすず書房一九九五]
【文庫版】
【この後書きが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする