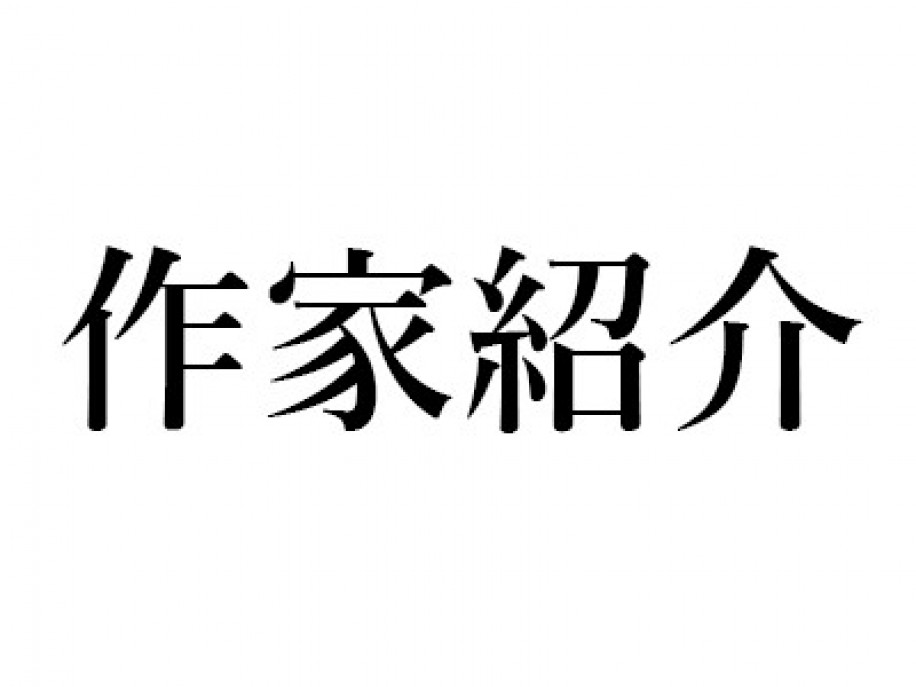書評
『折口信夫』(講談社)
画期的な天皇論、新資料交え分析
総索引が付いた全集ばかりか講義録まで完備している。個人の思想を研究するのに、一見これほど恵まれた環境はない。けれども、いったんその「森」に足を踏み入れるや、あまりに鬱蒼(うっそう)としていて方向感覚を見失ってしまう――折口信夫とは、そんな思想家だ。一体これまで幾人が踏破を試み、失敗を重ねてきただろうか。安藤礼二は、2002年に「神々の闘争――折口信夫論」を世に問うて以来、一貫して批評家としてこの巨人と向き合ってきた。テキストを厳密に読み抜き、読み破った者でなければ見えてくることのない新たな地平を、独力で切り開いてきたのだ。本書は、10年以上にわたる安藤折口論の集大成として大きな意味をもつ。
第1章から劇的である。これまでの研究で空白のままだった大学時代に、折口は本荘幽蘭(ゆうらん)という女性と出会い、神風会という神道系の団体と関わっていたことが、新資料を交えつつ論証される。驚くべきは、同時期に大本教(正式には大本)の出口王仁三郎もまた神風会と関わっていたことである。折口も王仁三郎も、自らをスサノヲになぞらえていた。国家神道が持ち上げた伊勢=アマテラスでなく、出雲=スサノヲが神道の中心に据えられたのだ。さらに折口の場合は、本荘との関係がアマテラスとスサノヲに重ね合わされる。何という大胆な解釈だろうか。
柳田国男との出会い以前に、折口の思想はすでに固まっていたのである。あえていえば、柳田は折口の思想をさらに発展させる触媒としての役割を果たしたにすぎないことが説得的に論じられる。例えば、柳田は天皇については直接言及しなくなるが、折口は積極的に言及し、ついには「天皇霊」という、万世一系のイデオロギーを原理的に否定するところまでたどりついてしまった。柳田も折口も南西諸島に出掛けたが、折口の場合は琉球王国で宗教的権威を担う聞得大君(きこえおおぎみ)の「秘儀」に触れたことが、神と天皇の中間に中天皇(ナカツスメラミコト)と呼ばれる女性がいるという画期的な天皇制論につながっていった。
こうした論の運びを追ってゆくと、折口は本荘幽蘭のほかに、同時代を生きた別の女性を意識していたのではないかと思いたくなる。その女性とは、大正天皇の妃で、折口が中天皇と見なした神功皇后に強い思い入れをもち、折口の最晩年に当たる1950年と51年の歌会始で相まみえた皇太后節子(さだこ)(貞明皇后)である。
なぜ折口だけが、現実の天皇制にこれほど深く迫ることができたのか。この謎はいまだ完全に解かれたとはいえない。が、本書が多くのヒントを与えてくれたことだけは間違いない。
朝日新聞 2015年01月25日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする