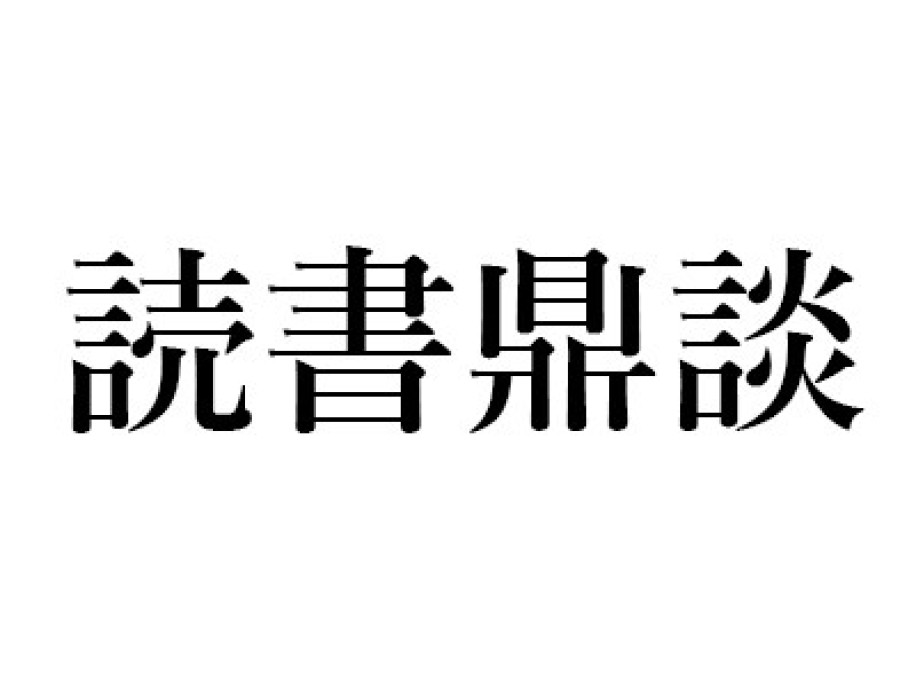書評
『作家は移動する』(新書館)
文学の世界では創作と批評はほんらい飛行機の左右のエンジンのようなものだ。しかし、長いあいだ片肺飛行の状態が続いている、ここ十数年来、読者の心に残る文学作品は少なくない。だが、魂が揺さぶられるような名批評は果たしてあったか。むろんときにははっとさせられるような秀作もないわけではない。批評界が全体として活気がないのは否めない。「外部」の声のほうがより思索力の深みを見せた場合もある。果たして文学批評はどこへ行くのか。そう自問するときに、本書に出会えたのは幸運だ。
書名は江藤淳『作家は行動する』をもじったものだが、内容的な関連はほとんどない。両者のあいだに想像力の呼応があり、また、探索する心の響きもあったのであろう。というのは、江藤淳の文体論は示唆に富むものである。つまり、文体は装飾性の枠に束縛されるのではなく、生の意味を見いだす上で能動的な役割を果たすべきだ。日常語の世界は不確かでルーティン的な事象把握しかできない。文学的な言語こそ真の〈世界〉に到達する架け橋になる。日常のことばを無造作に書くと、たとえ文学の衣裳で包まれても、消耗品のように消費されるだけだ。
今日、言語にまつわる状況は気になることばかりだ。ツイッター、スカイプ、フェイスブックの利用者数が急増し、プログでは言葉のインフレ状況が幾何級数的に進んでいる。理性よりも情緒に流されやすく、伝達する内容よりも伝達行為に情熱が傾けられている。江藤淳は作家が文体で行動すべきだというのに対し、著者は作家が「移動」し、「移動」を描くことを通して、生をとらえようとしていることに着目した。
この発想はおそらく文化人類学から由来したのであろう。「移動」というファインダーから覗くと、目の前には思わぬ景色が繰り広げられてきた。それは必ずしも未踏の地の壮大なパノラマではない。テクストが踏査の対象になっているから、「移動」を背景とする心象風景が現前した。地球の表面を共有する人類の一員として、虚構世界の内部に仮想の足を踏み入れ、場所から場所へと飛翔する想像力を追いかける。
取り上げられた作家は多和田葉子、リービ英雄、堀江敏幸、宮内勝典、池澤夏樹と村上春樹の六人。ヨーロッパかアメリカに定住し、またはかつて定住していた日本人作家もいれば、日本に在住し、中国での見聞を小説に書くアメリカ出身の作家もいる、あるいは定期的に海外に居住する小説家や、パリを定点観測地とする作家も考察の対象となる。いずれも自分が生まれ育った言語の外にいったん出ていき、異文化・異空間のなかで創作の意欲が触発される。文字通り「移動」を経験し、「移動」の過程で生じた魂の火花を文章に結晶させる。空間の変化はたんに創作の背景ではなく、作品のなかにそのまま描かれている。それを著者はひたすら読者の目線で丁寧に読み解いていく。
「越境」という言葉は使われていない、というより、著者はそのような捉え方を嫌っている。「越境」は結果的に境界の作用を肯定し、防壁の存続を黙認し加担する。文化人類学者は仕切りを嫌う。境界をなくすために、仕切りを超えていく。
現代社会において、生をとらえるのになぜ「移動」という視点が必要なのか。おそらくポスト工業社会の窮状が念頭にあったのであろう。
現代では変化は速すぎて、人々の想像力は追いついていくのが難しい。貿易の自由化、経済のボーダレス化、情報通信技術の高度化によって、産業革命以来の仕切りが押し流され、社会の経済構造は確実にしかも加速度的に変わりつつある。一方、十九世紀に出来上がった上部構造は以前にもまして顕在化し、強迫観念として人々の大脳皮質を人質にしている。そこで、情緒の錯乱的な漂流が始まったのである。
そのようなときこそ、「移動」という視点は大切になってくる、と著者は言いたいのであろう。現代は文学が無力の時代である、小説が読まれなくなったというのではない。文学的想像力がかつてないほど希薄になっているからだ。今日、かりに文学作品がまだ何がしかの存在感を示すことができるとすれば、それは小説の商品的価値を、もっとも俗物的な形で誇示する以外にないであろう、しかし、いくら市場で蛮勇をふるっても、文学の無力さをさらけ出す以外の何物でもない。空前絶後の想像力を取り戻すためには、「移動」することが必要である、
ただ、「移動」とはたんに、空間的な移り動きを意味するだけではない。現実と空想のあいだの往来も、ひいては過去と現在のあいだの交響も「移動」である。堀江敏幸「静かの海」について著者が語ったように「移動が現実を創り出し、さらに現実を超える現実体験を可能にする」。それ以上に重要なのは、思考の「移動」、方法としての「移動」であると著者は言いたいのではないか。
作家が移動し、作中人物が移動する。さらに、作品が移動し、文体でさえ移動する。だから、批評も「移動」しなければならない。というより、「移動」しないかぎり、批評の再生はないのかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
書名は江藤淳『作家は行動する』をもじったものだが、内容的な関連はほとんどない。両者のあいだに想像力の呼応があり、また、探索する心の響きもあったのであろう。というのは、江藤淳の文体論は示唆に富むものである。つまり、文体は装飾性の枠に束縛されるのではなく、生の意味を見いだす上で能動的な役割を果たすべきだ。日常語の世界は不確かでルーティン的な事象把握しかできない。文学的な言語こそ真の〈世界〉に到達する架け橋になる。日常のことばを無造作に書くと、たとえ文学の衣裳で包まれても、消耗品のように消費されるだけだ。
今日、言語にまつわる状況は気になることばかりだ。ツイッター、スカイプ、フェイスブックの利用者数が急増し、プログでは言葉のインフレ状況が幾何級数的に進んでいる。理性よりも情緒に流されやすく、伝達する内容よりも伝達行為に情熱が傾けられている。江藤淳は作家が文体で行動すべきだというのに対し、著者は作家が「移動」し、「移動」を描くことを通して、生をとらえようとしていることに着目した。
この発想はおそらく文化人類学から由来したのであろう。「移動」というファインダーから覗くと、目の前には思わぬ景色が繰り広げられてきた。それは必ずしも未踏の地の壮大なパノラマではない。テクストが踏査の対象になっているから、「移動」を背景とする心象風景が現前した。地球の表面を共有する人類の一員として、虚構世界の内部に仮想の足を踏み入れ、場所から場所へと飛翔する想像力を追いかける。
取り上げられた作家は多和田葉子、リービ英雄、堀江敏幸、宮内勝典、池澤夏樹と村上春樹の六人。ヨーロッパかアメリカに定住し、またはかつて定住していた日本人作家もいれば、日本に在住し、中国での見聞を小説に書くアメリカ出身の作家もいる、あるいは定期的に海外に居住する小説家や、パリを定点観測地とする作家も考察の対象となる。いずれも自分が生まれ育った言語の外にいったん出ていき、異文化・異空間のなかで創作の意欲が触発される。文字通り「移動」を経験し、「移動」の過程で生じた魂の火花を文章に結晶させる。空間の変化はたんに創作の背景ではなく、作品のなかにそのまま描かれている。それを著者はひたすら読者の目線で丁寧に読み解いていく。
「越境」という言葉は使われていない、というより、著者はそのような捉え方を嫌っている。「越境」は結果的に境界の作用を肯定し、防壁の存続を黙認し加担する。文化人類学者は仕切りを嫌う。境界をなくすために、仕切りを超えていく。
現代社会において、生をとらえるのになぜ「移動」という視点が必要なのか。おそらくポスト工業社会の窮状が念頭にあったのであろう。
現代では変化は速すぎて、人々の想像力は追いついていくのが難しい。貿易の自由化、経済のボーダレス化、情報通信技術の高度化によって、産業革命以来の仕切りが押し流され、社会の経済構造は確実にしかも加速度的に変わりつつある。一方、十九世紀に出来上がった上部構造は以前にもまして顕在化し、強迫観念として人々の大脳皮質を人質にしている。そこで、情緒の錯乱的な漂流が始まったのである。
そのようなときこそ、「移動」という視点は大切になってくる、と著者は言いたいのであろう。現代は文学が無力の時代である、小説が読まれなくなったというのではない。文学的想像力がかつてないほど希薄になっているからだ。今日、かりに文学作品がまだ何がしかの存在感を示すことができるとすれば、それは小説の商品的価値を、もっとも俗物的な形で誇示する以外にないであろう、しかし、いくら市場で蛮勇をふるっても、文学の無力さをさらけ出す以外の何物でもない。空前絶後の想像力を取り戻すためには、「移動」することが必要である、
ただ、「移動」とはたんに、空間的な移り動きを意味するだけではない。現実と空想のあいだの往来も、ひいては過去と現在のあいだの交響も「移動」である。堀江敏幸「静かの海」について著者が語ったように「移動が現実を創り出し、さらに現実を超える現実体験を可能にする」。それ以上に重要なのは、思考の「移動」、方法としての「移動」であると著者は言いたいのではないか。
作家が移動し、作中人物が移動する。さらに、作品が移動し、文体でさえ移動する。だから、批評も「移動」しなければならない。というより、「移動」しないかぎり、批評の再生はないのかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする