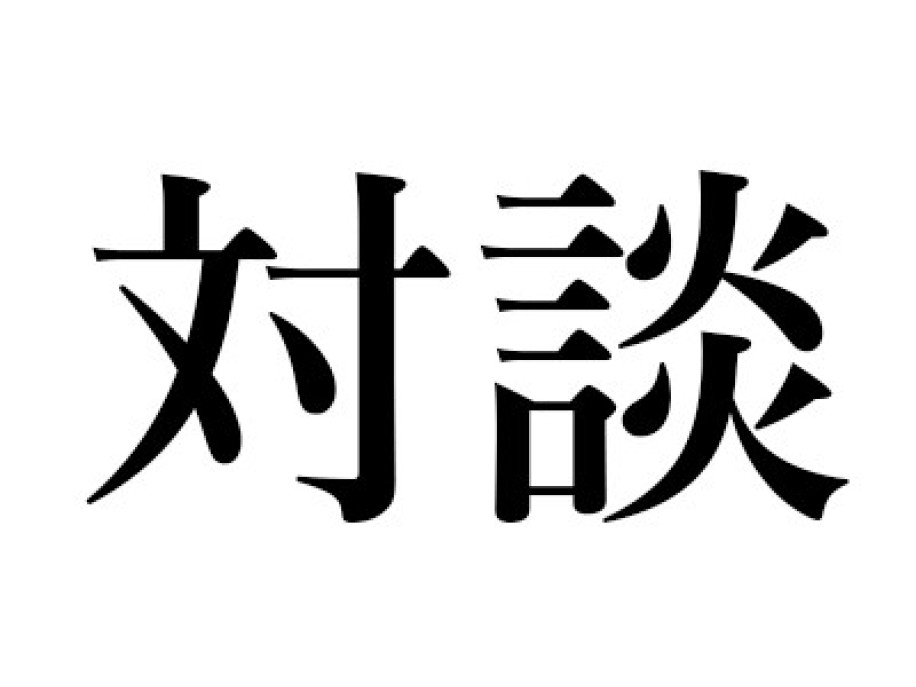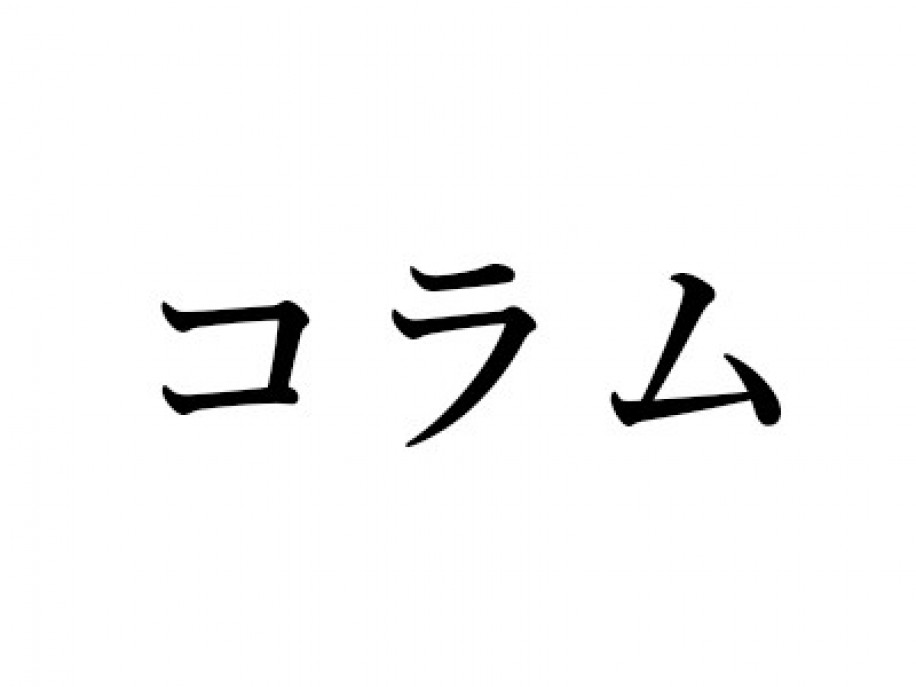書評
『肖像の眼差し』(人文書院)
向こうから「乗りだして」くる顔
むかし、私は空いた時間に絵を、それも人物画ばかりを描いていた。三時間ほどモデルを凝視しながら、しかしまったく違う顔を描こうとしていた。海を見つめながら、小川で水浴びしている裸婦の絵を描いていたルノワールにこれをなぞらえるのはおこがましいが、そのときのあがきは今もよく憶(おぼ)えている。顔をもっと近くにたぐりよせたかったのか、顔をちりぢりに遠ざけたかったのか……。肖像はだれかの顔を描いたものである。あるいは、だれかの面影をとどめようとして描かれる。このあたりまえの了解を、ナンシーの語りはばっさり切る。
考えてみれば、肖像とはいえ、そこに描かれた人物をじかに知っている人はだれもいない。だが、だれかが描かれている。そのときの「だれか」とはだれか。
ナンシーは、肖像においてはつねに三つの関係性が生まれるという。「似ている」「呼びかける」「まなざす」ということ。が、一見分かりよさそうなこの規定は、常識をぐいと抉(えぐ)るものだ。
「似ている」ということは肖像の出現とともになりたつと、ナンシーはいう。肖像はだれかに似せて描かれるのではなく、似るという関係が絵のなかに生成することで「主体」が誕生する、と。
よく考えてみれば、だれも自分の顔を見たことがない。他人の顔を観察しようにも眼(め)が合えば視線はつい逸(そ)れる。そのなかで、対象としてではなく、眼差(まなざ)しとして向こうから「乗りだして」くるのが顔であり、描かれたこの顔、この眼差しのなかで絵画自体が、眼差し、つまりは肖像となる。肖像において「だれか」(主体)が生まれるというのは、だから奇異な議論ではない。「だれか」が生まれることと画面が絵になることとは、同じ構造をもった出来事だからだ。
その眼差しを「激化させ、突出させ」たピカソ、「はるか彼方(かなた)から眼差しを孤立したものとして画布のなかに到来させ」たジャコメッティ、「眼差しをねじり苛(さいな)む」ベーコン……。ぞくぞくするような解釈の予感とともに、肖像論は閉じられる。もっと読みたいという恨みを残して。
朝日新聞 2005年1月23日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする