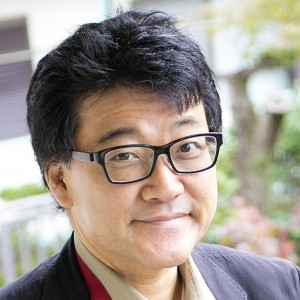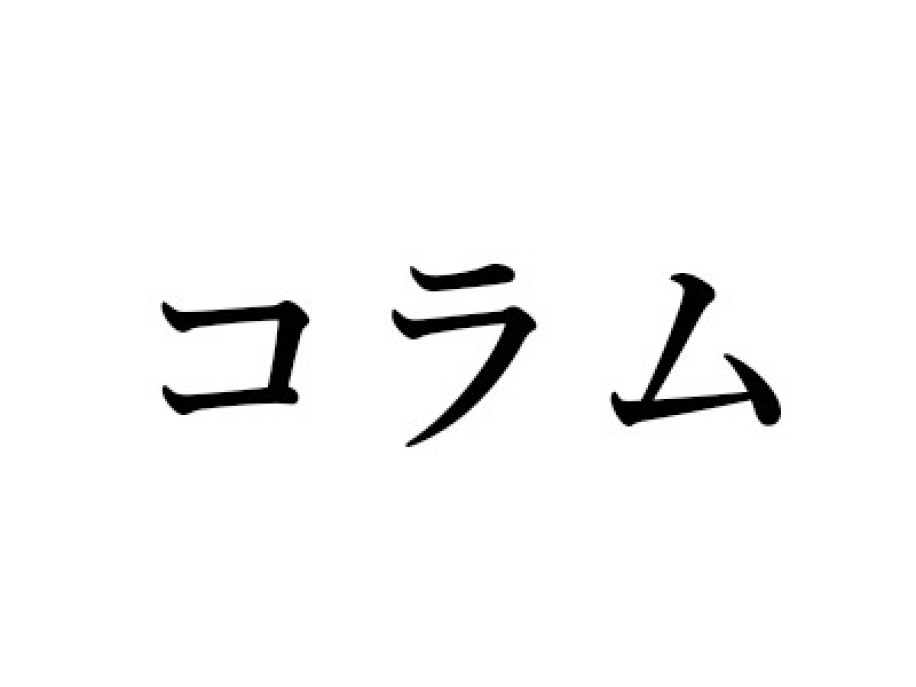書評
『ロクス・ソルス』(平凡社)
レーモン・ルーセル(Raymond Roussel 1877-1933)
フランスの作家。生前の単行本はすべて自費出版。のちに高い評価を得る『アフリカの印象』(1910)も『ロクス・ソルス』(1914)も、当時は世間からことごとく無視される。演劇にも関わるが、観客間の争いというスキャンダラスな話題を得ただけであった。晩年は財産を失い、旅先で睡眠薬の大量摂取によって自殺を遂げた。そのほかの作品に、戯曲『額の星/無数の太陽』(1925/1927、邦訳は合本)がある。introduction
ぼくが最初にルーセルを読んだのは、白水社の〈小説のシュルレアリスム〉で出た『アフリカの印象』である。大学二年か三年のころだった。ヘンテコな小説を求めて彷徨いあるいていた(!)ぼくにとって、〈小説のシュルレアリスム〉という叢書はまさに宝の山だった。もっとも、ルーセルの作品は、シュルレアリストたちから高く評価はされたものの、めざしていた方向はかなりちがう。シュルレアリスムが狂気や無意識に依拠していたのに対し、ルーセルの足場はあくまで正気と論理にあった。むしろ、非現実なまでに論理的だったというべきか。それがどういうことかは、ここに紹介した『ロクス・ソルス』の内容からもわかっていただけるだろう。▼ ▼ ▼
おもしろいことだけを手がかりにして小説を読んできたので、文学の意義が「人生を考えさせる」とか「作品を鑑にして自己を陶冶する」だという教条には鳥肌がたつ。「人間を描く」にいたっては、笑止というしかない。そんなことは文学の本質とは無関係だ。うわっ、いけね、つい“本質”なんて言っちゃったよ。ぼくもだいぶヤキがまわったな。ま、たかが文学じゃないか、どんどん勝手をすればいい、というのがホントのところだ。
ルーセルという人は、文学とはこういうものだという通念や常識にとらわれなかった。というよりも、自分が興味のあること以外にはとことん無頓着だったのだろう。彼の作品には、愛の意味とか生きる勇気とか思いやりの大切さとか、人生の道しるべとか心の栄養とか、そういうものは一切ない。あるのは、尋常ならざる想像力だけである。
彼が残した長篇小説には『アフリカの印象』と『ロクス・ソルス』があるが、ここでは後者をとりあげよう。
この作品をひとことで表現するなら、「小説のかたちをした見世物」である。富豪にして天才科学者であるマルシャル・カントレルが、パリ郊外の閑静な別荘に友人・知人を招いて、広大な敷地に設置した驚異的な発明・秘蔵品の数々を披露する――それだけの話だ。舞台となる大邸宅の名がロクス・ソルス。「人里離れた場所」という意味である。
発明といっても、青色発光ダイオードのように産業界に革命をおこすとか、携帯電話のように生活を便利にするというものとは、まったくちがう。ふつうの意味ではぜんぜん役にたたない。いや、使い方によっては役にたつようにできるのだろうが、そんな発想がカントレル氏にはない。ひたすら珍奇で不思議で、観る人たちを驚嘆させるばかりである。
たとえば、抜いた歯を素材にモザイク画を制作する装置。その構造は「撞槌」(歩道をならすのに使う突き棒)を思わせ、それが気球に吊されて宙に浮くようになっている。撞槌の上端には、アルミニウム製の自動バルブが施され、その隣には小さなクロノメーターがついている。そのほか、こまごまとした機構がこらされていて、本文中ではいちいち説明がくわえられている。
この撞槌がどんなふうに動作するかというと、日光をレンズで集め内部の薬品を気化させ、これで気球の浮力を得る。風に吹かれて所定の場所におかれた歯のところまで行き、これを下端の鉤爪で拾いあげ、また風を利用して作成中のモザイク画の上空へと移動する。そして、あらかじめ決められた位置に歯を嵌めこむ。この繰りかえしで、徐々にモザイク画がつくられていくのである。
なぜ歯が素材なのか? じつはカントレル氏は人間の歯のなかの石灰分にのみ作用する特殊な磁力を発見しており、これによって可能となった無痛の抜歯法で、多くの患者の虫歯治療をおこなっていた。そうやって抜いた歯が溜まっていたのである。白い歯、黄ばんだ歯、鮮血にまみれた歯、鉛の詰め物が施された歯、金歯……色とりどりの素材がざくざくある。ちなみに撞槌が歯を拾いあげる仕組みにも、この特殊磁力が応用されている。
さて、撞槌の移動は風まかせだが、カントレル氏は長年の研究によって大気の動き完璧に予測できるようになっていたので、まったく問題はない。むしろたいへんなのは、予測した動きにしたがって、あらかじめ歯を正確な位置を置いておくことだ。この複雑な作業には、撞槌を動かせない夜の時間をあて、たいへんな集中力をもって準備にあたった。
こうした一連の記述は、さながら技術解説書のようだ。最初に読んだときは、呆気にとられ、すぐに吹きだした。笑うしかないよ、これ、おかしいったらない。そうするうちに、撞槌の精巧さと無用さをしみじみ思って、なんだか嬉しくなってきた。子どもの時分、勉強机の抽斗に、壊れた時計やラジオ、由来も知れないガラクタじみた部品、色ガラス、日光写真、セミの抜け殻……なんてものを大切にしまっていた。そのはかない憧れを無制限に拡大したさきに、ロクス・ソルスの秘宝がある。
しかし、ルーセルはどうやって、こんな途方もないアイデアを思いついたのか。彼の遺言のかたちで公表された『私はいかにして或る種の本を書いたか』で、その秘密の一端があかされている。ルーセルは、ふたつの単語を前置詞でつないだうえで、はじめとちがう意味をとる、ということからはじめる。たとえば、「Demoiselle a pretendent(婚約者のいるお嬢さん)」が、「Demoiselle a reitre en dents(歯でできた傭兵の撞槌)」になる。つまり、まったくの言葉遊びなのだ。しかし、遊びとはいえ、それは厳密なルールである。ルーセルは「規則マニア」を自認していたが、その規則とは外から与えられるものではなく、彼自身のなかに、あるいは作品のなかに内在している秩序であった。そうしたルーセルの変人ぶりも好ましいのだが、読者にとってとりあえず重要なのは、背後にどんなルールがあるかということではなく、おもてにあらわれた奇想の輝きである。だいたいおなじルールに則ったとしても、ふつうの人があんなことを考えつくはずがない。
それにしても、カントレル氏の超俗ぶりは徹底している。彼の発明のなかには、死んだ人間に作用して生前とそっくりの行動をさせる方法というのがある。蘇生薬を施したうえで電気的な刺激を与えると、その人の生涯でもっとも忘れがたい瞬間の動作を精確に繰りかえすのだ。べつに精神が復活するのではなく、記憶に操られるだけのゾンビなのだが、それでもいいと遺族からの依頼がある。そうすると、カントレル氏は凝りに凝って、甦ったときの動作にあうように生前どおりの状況を整えるのだ。ふつうの神経からすれば、なんともグロテスクで倫理的に許されるものとは思えないのだが、この作品の描写には陰惨さはみじんもない。あっけらかんとしたものだ。
カントレル氏は、どう見てもマッドサイエンティストである。しかし、世界征服をめざしたり、世の中に復讐しようとしたり、人を脅したりはしない。そういうのは貧しい者のすることだ。ルーセルの文学もまたしかり。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする