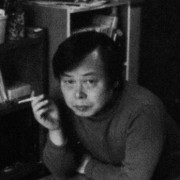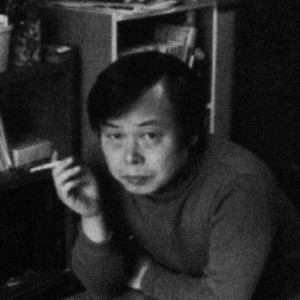書評
『相撲変幻』(ベースボール・マガジン社)
旅をする巨鳥
相撲の本なのに旅のにおいがする。まずガルーダという巨鳥が旅をする。翼をひろげれば三百万里に達し、那羅延天(ならえんてん)という力士をのせて宇宙の端から端までをとびまわる鳥だ。げんにモンゴルの力士がそれにあやかって、両腕を翼のようにひらひらさせながら闘技場に登場してくる写真が、本書の口絵にもみえる。インド=モンゴル産のガルーダははるばるわが国にも渡来した。国技館の「東西の力士が、仕切りに先立って掌を打ち合わせたあと、両手を左右にひろげる仕種をおこなうのは、ガルーダのスピリットを喚起しようとするマジックの名残りであろう」。なるほど、飛鳥のような土俵さばきをみせる力士がいるわけだ。一方、相撲は、古代中国の牛の角をはやして戦う格闘技の系譜も継いだ。いずれも、はるかなるアジア大陸から渡来してこの島国で習合し、それに「原始の『荒あらしさ』から平安の『みやび』、さらには江戸の『粋』にいたる数かずの美意識が、重層的に詰めこまれて」、今日の相撲になったという。したがってまずは前著『力士漂泊』についで、民俗学や宗教学の方法を援用しつつそのルーツにさかのぼる旅である。
並行してもう一つ、もっとささやかな、著者自身の少年期の相撲熱にさかのぼる記憶の旅がある。地方都市の巡業相撲にきた男女ノ川が、特大のうな丼をあっという間に七杯ぺろりと平らげるエピソード。同じ町の三人の力自慢が中央の角界に入門するが、二人は落伍し、その一人が著者たち少年力士のコーチをつとめながら故郷の町に埋もれる。そんな短篇小説を読むような一章もある。
ガルーダなみの大旅行と少年時へのささやかな記憶の旅。その大小のすべてを、やや審美趣味的文体の様式美のなかにきっちり抑えこむ。この様式美のマンダラ構造では細部に神が宿っているので、たとえば逆鉾のなにげなく見せる表情が「水の相撲」の権化の河童そっくりであって、海幸彦、山幸彦の神話をいまに語り継ぐ語り部であることの消息が、なんのケレンもなく語りだされ、読むほうも思わず膝を打つのである。巻をとじるとニワカ相撲通になった気になり、シロウト相撲の生兵法がうずうずしはじめる。テレビの相撲中継の前で、受け売りのひとつも口走りたくなるはた迷惑はほどほどに。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1990年7月22日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする