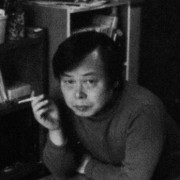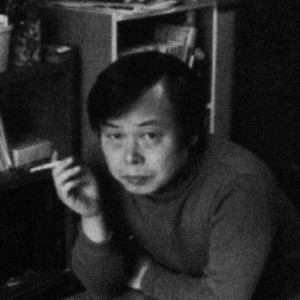書評
『イン・ザ・ペニー・アーケード』(白水社)
とり落とした掌中の珠
少年少女というにはやや大人に近い。少年期をすぎて大人に向かいつつある年ごろ、つまりはアドレッセンス。少年たちは、ここでなにかを、掌中の珠のようなものをとり落して、その代わりに大人の仲間入りをする。そのなにか、少年たちにとっての掌中の珠は、そこを通過してしまえば、ごくたあいのない、つまらないものに見えるだろう。たとえばB級遊園地の、もうとっくに流行後れになってコインの投入口をテープでふさがれた、埃だらけのピンボール・マシーン。それでもそれは、ついいましがた通り過ぎたばかりの世界なので、ふり返ってみれば、顕微鏡的な細部までくきやかに際立っているノスタルジーの国である。
それを、かりにアメリカという巨人的なアドレッセンスの寸法に引き伸ばしてみる。すると埃をかぶった初期アメリカの古ぼけた肖像画になる。いくぶん泥臭いロココ趣味、ベンジャミン・フランクリンの機械嗜好や、E・A・ポーのからくり好み。そういう廃棄物処理寸前の古きアメリカが埃をかぶってうずくまっている。それが魔法の杖の一閃によみがえると、表題作「イン・ザ・ペニー・アーケード」の少年がふり返って見た世界が生きいきと動きだす。機械が大人の分別によって実用化され、資本の奴僕になり下がる以前の、機械のイデアに熱狂していた少年の世界。一方、大人たちの現実をきらって、原型的なイデア機械にこだわり続ければ、もう一つの小説「アウグスト・エッシェンブルク」の主人公のように、古ぼけた機械と同一化して、みずからが廃棄物となってしまうほかない。
ここでは、アメリカの少年期と、ひとりのアメリカ人のありふれた、しかしうしなわれた少年期が重なりあう。重なりあいのつなぎ目に、サリンジャーや『エミリーへの薔薇』のフォクナー、『初恋』のツルゲーネフ、『ヴェニスに死す』のトーマス・マンの文体模倣がすけて見える。ひとによっては、それを小説を学習可能なものとみなす大学創作科文学とみて隔靴掻痒のもどかしさを感じるかもしれず、あるいはそれゆえにこそ、中世ラテン文学風のあらたな僧院文学の可能性を見るひともいるかもしれない。とりあえず、二十世紀アメリカ文学にはあまり類のない、ミニチュアずくめのガジェット蒐集室がたのしめる。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1990年6月10日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする