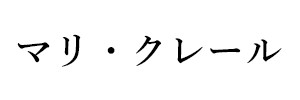書評
『オリエンタリズム』(平凡社)
この本を読んでいると、西欧の歴史、とくに十八世紀以来の近代史にとって、オリエント(東洋)という主題は、ユダヤ人問題や、わが国でいえば被差別部落の問題とおなじように、ひとたびとりこまれると、心理と論理と理念と、その上に植民地政策の歴史までからみあって、執拗に粘りついてくる悪業みたいなものなんだなと、つくづくかんがえさせられた。主題に突っこんでゆけばゆくほど政治、経済、文化の諸領域にまたがった特異な泥沼の姿があらわれてくる。そしてその特異な泥沼の姿を整理し浮き彫りにすることが、とりもなおさず、この本の著者の最大のモチーフになっている。泥沼に足をとられるこの種の主題は、敬して遠ざけ、歴史の自然と歴史の無意識にまかせておくのが、いちばんいい解決法なのだ。
著者がとても丁寧に、歴史家としては繊細すぎるほど情理を尽して解いている西欧にとってのオリエンタリズムの問題は、どうすれば、歴史の自然と無意識にゆだねられ、解決できることになるのか。簡単に言ってしまえばオリエント(東洋)が世界史のうえで、政治、文化、経済などの全域にわたって、西欧と肩をならべ、同等の水準になってしまえばよいことになる。またこの本の著者がかんがえているような言説としての西欧オリエンタリズムが解体してしまうためには、オリエント(東洋、いいかえれば近東・中東・極東)の内部から、オリエンタル(東洋人)の手によって、オリエント(東洋)について、西欧のオリエンタリズム言説史の蓄積と同等の水準をもった内部解析の言説が出現してしまえばよいことになるだろう。わたしには、この何れも時間の問題のようにおもえる。といってもまだまだ沢山の年月がいるだろうが。
この本の著者がやっているのは、ながい歴史の時代にわたり、オリエント(東洋)をあなどり、虐げ、植民地として支配し、じぶんたちの文明と文化を拡張して西欧化の強制と支配と恩恵を、あるいは強制と支配によってはじめて恩恵を施してきた西欧の、政策と意図に添うように繰りひろげられたオリエント(東洋)に関する言説の蓄積物を、十九世紀初頭までの異郷趣味や神秘的な探検や航海や地誌の時代と、十九世紀に入ってからおもにイギリスとフラソスが荷った西欧のオリエント(東洋)にたいする植民地支配と領有の帝国主義膨張の時代と、第二次大戦以後、イギリス、フランスにたいするオリエント(東洋)の脱植民地化の反抗と独立の時期と、現在の、イギリス、フランスに代ったアメリカとソ連による帝国主義的な威圧と、それにたいするオリエント(近東・中東)の複雑な反抗と独立の時代とに区分して整理しながら、西欧のオリエント(東洋)にたいする差別と優越意識を内省し、批判(自己批判)し、それが解体して社会科学の一主題としてオリエント(東洋)というところに落着いてゆく必然を、できるかぎりの繊細さと穏健さで分析している。
もともと西欧のオリエンタリズムの言説が、オリエント(東洋)という区分を成り立たせた根拠は、ひとつには近東や中東や極東の政治、文化、経済の制度が社会習俗にいたる文物から、共通する要素を掴み出せると思い込ませたからだ。そうでなければ、オリエント(東洋)は雑多な種族的な文物が地域別に雑居するだけなはずだ。もうひとつの根拠は、西欧自体のオリエント(東洋)にたいする対応の仕方のなかに、共通する態度があったことだ。そのいちばんわかり易い共通点は、西欧を西欧として自覚的に認知できる以外の文物が棲息し、怪物のように横行する影の世界を、すべてオリエント(東洋)として括りつけて区別する仕方である。オリエント(東洋)は、西欧からは、西欧の支配を黙って甘受している未発達の地域にすぎないとみなされた。そこでは植民地支配が政策の共通性としてあらわれたのだ。このふたつの区分根拠に起源をもつ西欧のオリエンタリズムの言説史から、この本の著者の整理によって掴みだされたオリエント(東洋)の特徴は、つぎのいくつかに要約される。
1 オリエント(東洋)には、政治的な自治の存在した痕跡はない。オリエント(東洋)の偉大だった諸世紀と、その文物の創造は、いつも専制政府の下でおこなわれた。
2 オリエント(東洋)の哲学や思想は、政治的な統治を、下等で汚い領域として侮蔑し、自らを顧みようとしなかった。
3 だから近代になってからの西欧によるオリエント(東洋)の支配と征服と文物の強制を、かれら自身の専制政治(オリエンタル・ディスポチズム)よりも、ずっとましな優れたものとして、甘受するほかなかった。
4 オリエント(東洋)はいつも起源からの呼び声から逃れられず、停滞し退行した(東洋的停滞、下降、退行)。
5 オリエント(東洋)は本質的に、交易、通商、経済的合理性にたいする思慮を欠いていた。
現在のオリエント(東洋)にとって、西欧のオリエンタリストたちが抽出したこれらの特質は、過去の夢物語だろうか。確かに一九五五年のバンドン会議のころには、オリエント(東洋)は西欧(主にイギリス、フランス)の植民地支配から脱して自立し、そればかりか米ソの新しい帝国主義的体制にたいして、武器をとったり(アラブやアフガン)、政治的に武装したり(中国)、科学的な技術によって武装して(日本)対抗しているようにみえる。だが、この本の著者によれば、西欧のオリエンタリズムの基本的なオリエント観が壊れて、社会科学の一分野になったようにみえるのは、顕在的なオリエンタリズムであって、潜在的オリエンタリズムとも言うべきものは、不変の不易の流れと根拠をいまも千年来失なってはいないことになる。
この本の著者の基本理念は、著者自身が引用している比喩をつかえば、簡単に説明できる。じぶんの故郷を甘美なところだと思っている人間は、まだ「未熟者」だ。また世界中のあらゆる場所が故郷だと思える者は「かなりの力をもつ者」だ。だが全世界を異郷だと思える者こそ「完壁な者」だ。そして著者はこの比喩の経路に沿って「完壁な者」の立場を志向しているようにみえる。
ここまできて、わたしは柳田国男が『遠野物語』の冒頭で、「この書を外国にある人々に呈す」という献辞を記したのを思い出した。柳田はべつにその当時、この『物語』が西欧のオリエンタリストに読まれるとかんがえたわけではなかった。『遠野物語』はオリエント(東洋)の内部からオリエント(東洋)について記述されたものだが、その文体と方法のなかで、無意識に滲み込んだ西欧的方法しか、使おうとしなかった。もし西欧のオリエンタリストが、この『物語』を読んだとしたら、東南アジアから東北アジアにわたる大陸に接したヤポネシアの島々の土着の民話の記述資料として読むにちがいない。だが柳田の献辞は、この『遠野物語』の記述の文体と方法を土着の資料以上のものとして、理解するところまで読み込むことを、西欧のオリエンタリストに求めたのだ。献辞は西欧のオリエンタリズムにたいする柳田のそういう挑戦を意味していた。これはわが国の〈一般的にはオリエント(東洋)の〉西洋学が、語学に熟達し、頭脳と方法をオクシデント(西洋)そのものと化して、西洋の文物を主題にする態度と様式の対極をなすものだといえよう。
この観点からすれば、この本の著者がやっていることは、オリエント(東洋)の内部からオリエント(東洋)を主題にして、「完壁な者」を志向する内在的な課題にたいしては、何の意味ももちえない仕事だということになってしまう。この本の著者も、たぶんわたしたちも、それぞれ異なった角度でずれながら、真の命題にたいして真偽を織りまぜた暖昧な態度と様式で、オリエント(東洋)や優位性の解体に向いつつあるオクシデント(西洋)が交叉する命題に直面しているにすぎないのだ。悲しいことにそれが同時に、この本を粘着力のある好著にしている所以でもある。
【この書評が収録されている書籍】
著者がとても丁寧に、歴史家としては繊細すぎるほど情理を尽して解いている西欧にとってのオリエンタリズムの問題は、どうすれば、歴史の自然と無意識にゆだねられ、解決できることになるのか。簡単に言ってしまえばオリエント(東洋)が世界史のうえで、政治、文化、経済などの全域にわたって、西欧と肩をならべ、同等の水準になってしまえばよいことになる。またこの本の著者がかんがえているような言説としての西欧オリエンタリズムが解体してしまうためには、オリエント(東洋、いいかえれば近東・中東・極東)の内部から、オリエンタル(東洋人)の手によって、オリエント(東洋)について、西欧のオリエンタリズム言説史の蓄積と同等の水準をもった内部解析の言説が出現してしまえばよいことになるだろう。わたしには、この何れも時間の問題のようにおもえる。といってもまだまだ沢山の年月がいるだろうが。
この本の著者がやっているのは、ながい歴史の時代にわたり、オリエント(東洋)をあなどり、虐げ、植民地として支配し、じぶんたちの文明と文化を拡張して西欧化の強制と支配と恩恵を、あるいは強制と支配によってはじめて恩恵を施してきた西欧の、政策と意図に添うように繰りひろげられたオリエント(東洋)に関する言説の蓄積物を、十九世紀初頭までの異郷趣味や神秘的な探検や航海や地誌の時代と、十九世紀に入ってからおもにイギリスとフラソスが荷った西欧のオリエント(東洋)にたいする植民地支配と領有の帝国主義膨張の時代と、第二次大戦以後、イギリス、フランスにたいするオリエント(東洋)の脱植民地化の反抗と独立の時期と、現在の、イギリス、フランスに代ったアメリカとソ連による帝国主義的な威圧と、それにたいするオリエント(近東・中東)の複雑な反抗と独立の時代とに区分して整理しながら、西欧のオリエント(東洋)にたいする差別と優越意識を内省し、批判(自己批判)し、それが解体して社会科学の一主題としてオリエント(東洋)というところに落着いてゆく必然を、できるかぎりの繊細さと穏健さで分析している。
もともと西欧のオリエンタリズムの言説が、オリエント(東洋)という区分を成り立たせた根拠は、ひとつには近東や中東や極東の政治、文化、経済の制度が社会習俗にいたる文物から、共通する要素を掴み出せると思い込ませたからだ。そうでなければ、オリエント(東洋)は雑多な種族的な文物が地域別に雑居するだけなはずだ。もうひとつの根拠は、西欧自体のオリエント(東洋)にたいする対応の仕方のなかに、共通する態度があったことだ。そのいちばんわかり易い共通点は、西欧を西欧として自覚的に認知できる以外の文物が棲息し、怪物のように横行する影の世界を、すべてオリエント(東洋)として括りつけて区別する仕方である。オリエント(東洋)は、西欧からは、西欧の支配を黙って甘受している未発達の地域にすぎないとみなされた。そこでは植民地支配が政策の共通性としてあらわれたのだ。このふたつの区分根拠に起源をもつ西欧のオリエンタリズムの言説史から、この本の著者の整理によって掴みだされたオリエント(東洋)の特徴は、つぎのいくつかに要約される。
1 オリエント(東洋)には、政治的な自治の存在した痕跡はない。オリエント(東洋)の偉大だった諸世紀と、その文物の創造は、いつも専制政府の下でおこなわれた。
2 オリエント(東洋)の哲学や思想は、政治的な統治を、下等で汚い領域として侮蔑し、自らを顧みようとしなかった。
3 だから近代になってからの西欧によるオリエント(東洋)の支配と征服と文物の強制を、かれら自身の専制政治(オリエンタル・ディスポチズム)よりも、ずっとましな優れたものとして、甘受するほかなかった。
4 オリエント(東洋)はいつも起源からの呼び声から逃れられず、停滞し退行した(東洋的停滞、下降、退行)。
5 オリエント(東洋)は本質的に、交易、通商、経済的合理性にたいする思慮を欠いていた。
現在のオリエント(東洋)にとって、西欧のオリエンタリストたちが抽出したこれらの特質は、過去の夢物語だろうか。確かに一九五五年のバンドン会議のころには、オリエント(東洋)は西欧(主にイギリス、フランス)の植民地支配から脱して自立し、そればかりか米ソの新しい帝国主義的体制にたいして、武器をとったり(アラブやアフガン)、政治的に武装したり(中国)、科学的な技術によって武装して(日本)対抗しているようにみえる。だが、この本の著者によれば、西欧のオリエンタリズムの基本的なオリエント観が壊れて、社会科学の一分野になったようにみえるのは、顕在的なオリエンタリズムであって、潜在的オリエンタリズムとも言うべきものは、不変の不易の流れと根拠をいまも千年来失なってはいないことになる。
この本の著者の基本理念は、著者自身が引用している比喩をつかえば、簡単に説明できる。じぶんの故郷を甘美なところだと思っている人間は、まだ「未熟者」だ。また世界中のあらゆる場所が故郷だと思える者は「かなりの力をもつ者」だ。だが全世界を異郷だと思える者こそ「完壁な者」だ。そして著者はこの比喩の経路に沿って「完壁な者」の立場を志向しているようにみえる。
ここまできて、わたしは柳田国男が『遠野物語』の冒頭で、「この書を外国にある人々に呈す」という献辞を記したのを思い出した。柳田はべつにその当時、この『物語』が西欧のオリエンタリストに読まれるとかんがえたわけではなかった。『遠野物語』はオリエント(東洋)の内部からオリエント(東洋)について記述されたものだが、その文体と方法のなかで、無意識に滲み込んだ西欧的方法しか、使おうとしなかった。もし西欧のオリエンタリストが、この『物語』を読んだとしたら、東南アジアから東北アジアにわたる大陸に接したヤポネシアの島々の土着の民話の記述資料として読むにちがいない。だが柳田の献辞は、この『遠野物語』の記述の文体と方法を土着の資料以上のものとして、理解するところまで読み込むことを、西欧のオリエンタリストに求めたのだ。献辞は西欧のオリエンタリズムにたいする柳田のそういう挑戦を意味していた。これはわが国の〈一般的にはオリエント(東洋)の〉西洋学が、語学に熟達し、頭脳と方法をオクシデント(西洋)そのものと化して、西洋の文物を主題にする態度と様式の対極をなすものだといえよう。
この観点からすれば、この本の著者がやっていることは、オリエント(東洋)の内部からオリエント(東洋)を主題にして、「完壁な者」を志向する内在的な課題にたいしては、何の意味ももちえない仕事だということになってしまう。この本の著者も、たぶんわたしたちも、それぞれ異なった角度でずれながら、真の命題にたいして真偽を織りまぜた暖昧な態度と様式で、オリエント(東洋)や優位性の解体に向いつつあるオクシデント(西洋)が交叉する命題に直面しているにすぎないのだ。悲しいことにそれが同時に、この本を粘着力のある好著にしている所以でもある。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする