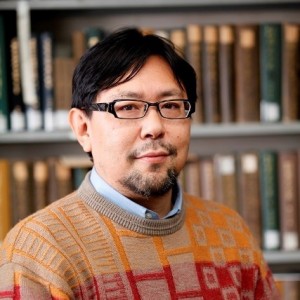書評
『墓石が語る江戸時代: 大名・庶民の墓事情』(吉川弘文館)
墓とどう向き合うかを考えるヒントがある
今に遺(のこ)る墓石は江戸時代の元禄期ごろから急激に増加する。その墓石はいつ造られ、いかなる階層に属していた人が葬られているのか。墓誌がある場合には被葬者の人生の読み込みも重要だ。また墓石はどんな材質の石で、形状はどうか。弘前大学に勤務する著者は、青森県の弘前周辺や北海道の松前・江差、またかかる地域と日本海交易でつながる福井県の三国・敦賀・小浜で丁寧で網羅的な調査(悉皆(しっかい)調査という)を実施した。そのデータを基に「ヒトの動き、モノの動き、情報の動き」を的確に推測し、墓石のナゾに迫っていく。著者の考察はどれも骨太で「地に足が着いている」安心感がある。だから読み進むうちに、研究水準が深化していくさまに立ち会える。
室町時代までの日本人は、よほど特殊な人でもなければ墓石を建てなかった。ところが江戸時代に入ると、1直系家族からなる世帯の形成、2儒教思想に基づく祖先祭祀(さいし)の浸透、この二つの要素が「家族墓」の形成を促し(これ以前には個人墓、ついで夫婦墓が造られた)、さらに寺檀(じだん)制度の確立が作用することにより、墓石が普及していったという。墓石の歴史はまさに近世の伸展を象徴しているのであり、「古墳文化」の概念が既にあるのだから、この時代は「墓石文化」と呼ばれてもおかしくない、と著者は説く。
江戸時代の墓石を考えることは確実に「今」の問題でもある。というのは、現在、江戸時代的な「家」が崩壊の危機に瀕(ひん)しているからだ。檀家を失った地方のお寺は次々につぶれていき、これに従い「墓じまい」が恒常的になっている。墓とどう向き合うか。死後のありようをどうイメージするのか。この「私たちの一大事」を考える際に、この本は必読の書である。
ALL REVIEWSをフォローする