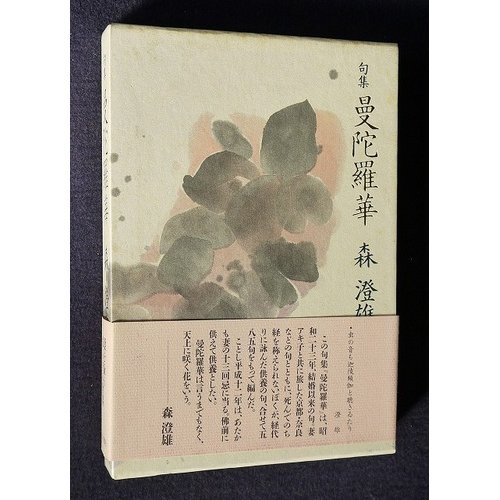書評
『奇蹟』(河出書房新社)
これは哀しく、絢爛たる気配に満ち、息詰まるようなロマンである。
主人公のタイチは、中本の一統七代にわたる仏の因果を背負ってこの世に誕生した。兄貴分のイクオと同じく彼も年頃になると女達がまとわりついて離れないほどの美形である。この肉体的な魅力と彼等が次々にくりひろげる極道の振舞いとは耽美的な刺青(いれずみ)の世界を想わせる豪華さである。
著者の美意識にしっかり支えられているから、どれほど幻想的で色彩と音に満ちている風景が描かれても、それはリアリティを失うことなく、また花鳥諷詠といった「日本的」抒情から自由である。川端康成の世界から感傷が脱色されて、よりいっそう輝かしい魔界が現れたと言うこともできる。その魔界の舞台が、かつて蓮池のあったあたりから路地にかけての一帯なのである。蓮はいま、幻のなかに咲くだけだが、この界隈は産業社会の枠組みから逃れていることで汚辱に満ちた聖域なのであるが、それゆえに指導者はまた滅びる運命をも担ってしまうのである。
著者は、『岬』以来『枯木灘』『鳳仙花』『千年の愉楽』『地の果て 至上の時』『日輪の翼』と、この世ならぬ聖域に生れ、死んでゆく人々を描いてきた。わけても、歌舞音曲をよくする「高貴にして澱んだ血」の一族である中本の一統の歴史を軸に据えて、この作品は路地の変還を語っている。時代は「三朋輩」が支配していた敗戦の頃から、「イクオ」「カツ」「シンゴ」「タイチ」の四人の若衆が中心となる現代へと変化する。かつては三朋輩のひとりで、今は酒に浸り込んで精神病院に入っている「トモノオジ」と、路地の人々の生誕に立合ってきた産婆の「オリュウノオバ」の二人が狂言まわしの役割を演じて、物語は彼等の幻想と回想の形をとって進められてゆく。
殺人、暴行、恐喝と極道を繰返す登場人物は、反俗であることによって稀な輝きに隈取られている。多くの読者は、この作品を読んで、自分が身を置いている〝良識〟の世界が、いかに薄汚く、嘘に塗りこめられ、いじましく、みみっちいかを、身につまされるようにして感じるに違いない。もしかすると、タイチに代表される一族の夭折の宿命は、産業社会と呼ばれている俗の社会では美は生存できないと著者は言おうとしているのかもしれない。これほど徹底して世俗から離れた場所に在って確固とした美の世界を描くには、ゆるぎない世界認識=文体が求められたのであった。この作品のなかでは、仏教でいう輪廻の思想も変身譚も、作品世界の素材としてのみ存在している。だから、作品を分析して、そのなかから既成の思想を抽出してみても、この小説を理解したことには少しもならない。その意味で、この作品は美のカオスの現前であり、破滅と再生の物語であり、宿命に生き、血の命ずるままに滅んでいった青春の讃歌でもある。
【この書評が収録されている書籍】
主人公のタイチは、中本の一統七代にわたる仏の因果を背負ってこの世に誕生した。兄貴分のイクオと同じく彼も年頃になると女達がまとわりついて離れないほどの美形である。この肉体的な魅力と彼等が次々にくりひろげる極道の振舞いとは耽美的な刺青(いれずみ)の世界を想わせる豪華さである。
著者の美意識にしっかり支えられているから、どれほど幻想的で色彩と音に満ちている風景が描かれても、それはリアリティを失うことなく、また花鳥諷詠といった「日本的」抒情から自由である。川端康成の世界から感傷が脱色されて、よりいっそう輝かしい魔界が現れたと言うこともできる。その魔界の舞台が、かつて蓮池のあったあたりから路地にかけての一帯なのである。蓮はいま、幻のなかに咲くだけだが、この界隈は産業社会の枠組みから逃れていることで汚辱に満ちた聖域なのであるが、それゆえに指導者はまた滅びる運命をも担ってしまうのである。
著者は、『岬』以来『枯木灘』『鳳仙花』『千年の愉楽』『地の果て 至上の時』『日輪の翼』と、この世ならぬ聖域に生れ、死んでゆく人々を描いてきた。わけても、歌舞音曲をよくする「高貴にして澱んだ血」の一族である中本の一統の歴史を軸に据えて、この作品は路地の変還を語っている。時代は「三朋輩」が支配していた敗戦の頃から、「イクオ」「カツ」「シンゴ」「タイチ」の四人の若衆が中心となる現代へと変化する。かつては三朋輩のひとりで、今は酒に浸り込んで精神病院に入っている「トモノオジ」と、路地の人々の生誕に立合ってきた産婆の「オリュウノオバ」の二人が狂言まわしの役割を演じて、物語は彼等の幻想と回想の形をとって進められてゆく。
殺人、暴行、恐喝と極道を繰返す登場人物は、反俗であることによって稀な輝きに隈取られている。多くの読者は、この作品を読んで、自分が身を置いている〝良識〟の世界が、いかに薄汚く、嘘に塗りこめられ、いじましく、みみっちいかを、身につまされるようにして感じるに違いない。もしかすると、タイチに代表される一族の夭折の宿命は、産業社会と呼ばれている俗の社会では美は生存できないと著者は言おうとしているのかもしれない。これほど徹底して世俗から離れた場所に在って確固とした美の世界を描くには、ゆるぎない世界認識=文体が求められたのであった。この作品のなかでは、仏教でいう輪廻の思想も変身譚も、作品世界の素材としてのみ存在している。だから、作品を分析して、そのなかから既成の思想を抽出してみても、この小説を理解したことには少しもならない。その意味で、この作品は美のカオスの現前であり、破滅と再生の物語であり、宿命に生き、血の命ずるままに滅んでいった青春の讃歌でもある。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする