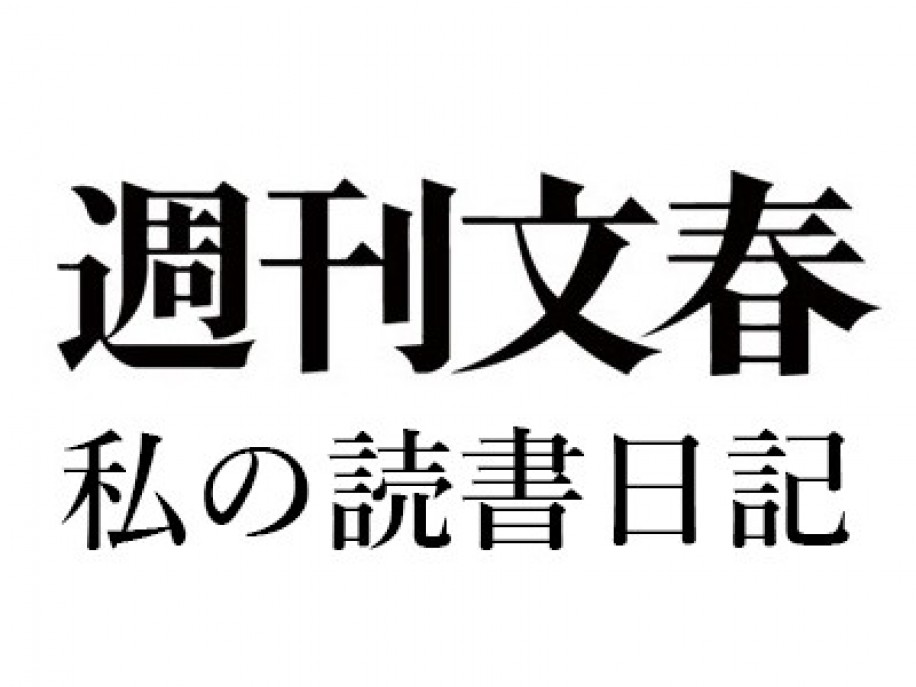書評
『珈琲の世界史』(講談社)
「茶色い貨幣」の歴史
前著『コーヒーの科学 「おいしさ」はどこで生まれるのか』はコーヒーのおいしさを科学的に解明した名著だったが、コーヒーの文化的・社会的歴史は割愛せざるをえなかった。本書はこの割愛部分を復活させながら起源から現代に至るコーヒーの歴史を綴(つづ)った力作である。十四世紀頃、宗教紛争でエチオピアからイエメンに逃れてきた人たちによって伝えられたコーヒーノキの果実はエチオピア発祥の別系統の飲み物「カフワ」とイエメンの地で結びつき、「コーヒーのカフワ」というスーフィー(イスラム教の一派)愛飲の飲み物を生みだす。この飲み物はオスマントルコ帝国の全域に広まり、やがてヨーロッパにも伝播(でんぱ)するが、東インド会社ルートの積み出し港だったイエメンのモカで興味深い変化が起きる。業者が栽培を独占するために発芽能力を失わせた豆だけを輸出したことから、ヨーロッパでは焙煎豆(ばいせんまめ)からエキスを抽出するコーヒーへと変化したのだ。
この後、コーヒーはロンドンのコーヒーハウス、パリのカフェなど土地に根付いた飲食スタイルで楽しまれるが、本書の醍醐味(だいごみ)はむしろ「金のなる木」と化したコーヒーノキがイエメンの禁輸措置をかいくぐったヨーロッパのプラントハンターたちによって植民地に移植され、次いで東南アジアや中南米に広まってゆく過程を活写したところにある。
例えば、イエメンのアデンから盗みだされて蘭領ジャワに渡った苗木は蘭領ギアナ(スリナム)でも育成されるが、隣の仏領ギアナがそれを盗みだしたことから一触即発の危機をつくりだす。このとき仲裁を買って出たのがポルトガル領ブラジルだったが、なんとそのブラジル特使もプラントハンターで、フランス領事夫人を籠絡(ろうらく)して苗木を盗みだすことに成功。かくて、三度の「盗み」を経てコーヒーノキを手に入れたブラジルは世界一のコーヒー大国へと成長する。一方、世界市場から取り残されたイエメンの積み出し港モカは急速に衰退し、ブランド名だけを残して廃港の憂き目をみる。
十九世紀に入り、急拡大した世界需要に応えるためブラジルは焙煎機の改良などで量産態勢を敷くが、十九世紀末に起こった価格暴落で経済危機に見舞われる。このときはサンパウロ州政府の要請で大量買い付けを行ったドイツ系実業家ジールケンが流通調整に成功して莫大(ばくだい)な儲(もう)けを手に入れるが、しかし、このボロ儲けはアメリカ側に強い反ブラジル感情を引き起こす。一九二九年にウォール街大暴落が起こったとき、ブラジル政府は夢よもう一度とばかり、在庫調整で価格の好転を図るが、奇跡は二度起こらず、ブラジルは経済危機に陥る。その結果、ブラジルでは反米ポピュリズムが高まり、一時は枢軸国側に好意的な政権さえ登場する。第二次大戦の危機が迫ると、アメリカは対ドイツを考慮して中南米諸国との間で「環アメリカコーヒー協定」を締結してコーヒー価格の安定を図り、戦後は、対ソ連用の「国際コーヒー協定」を締結して、中南米の共産化を防ごうとする。コーヒーは政治と連動する世界商品となったのである。
こうして、冷戦時代には日本の食管制度にも似たコーヒーの安定体制が敷かれるが、それは「安いがまずいコーヒー」を流通させるという弊害を生み出し、「高くてもおいしいコーヒー」を求める声の高まりとともに、スペシャルティコーヒーを誕生させる。
コーヒーの歴史とは「茶色い貨幣」の歴史であると認識させてくれる好著である。
ALL REVIEWSをフォローする