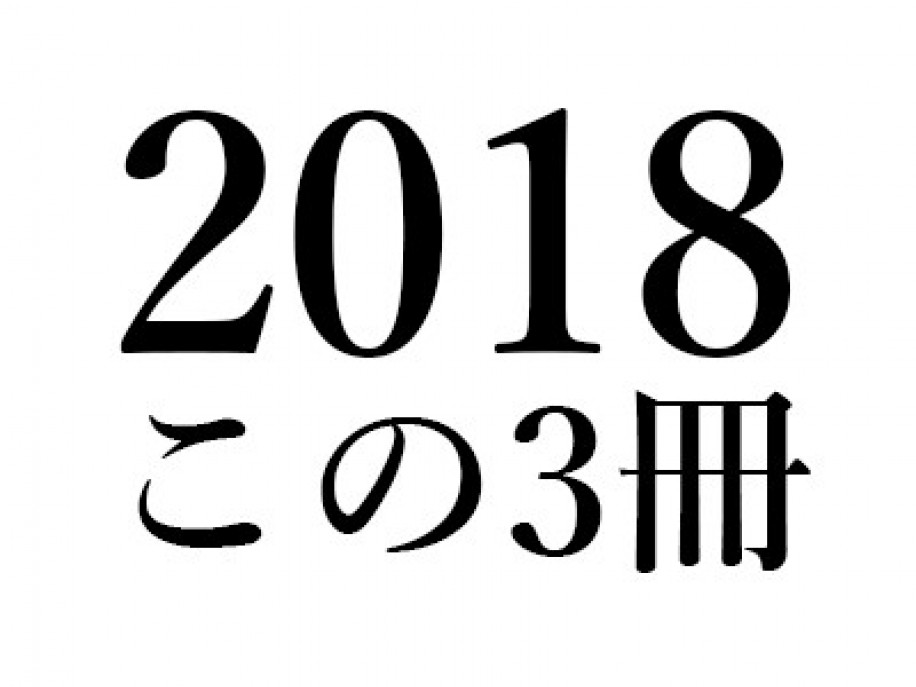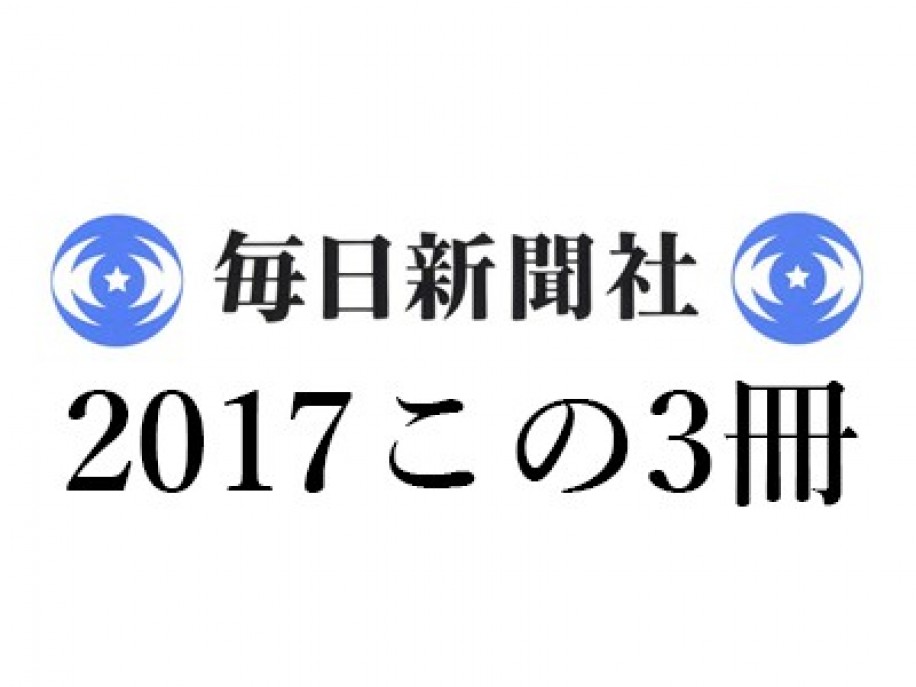書評
『一八世紀 近代の臨界』(ぷねうま舎)
極めて周到な統一的構想
ちょっと珍しい二人を組み合わせてテーマとしたエッセー集である。ディドロは一七一三年生まれ、モーツァルトは一七五六年生まれ、亡くなったのはさして違わないから、なるほど同時代人ではある。片やパリを拠点とするフランス啓蒙(けいもう)主義の驍将(ぎょうしょう)、片やウィーンを中心として活躍したドイツ語圏の天才作曲家、なるほどモーツァルトには「パリ」と名付けられた交響曲(K297)もあり、二度もパリを訪れてはいるが、パリで送った長くはない生活は、いずれも幸せからは遠かったはず。タイトルを見ただけで、そもそも両者に、どのような接点が見いだされるのか、不審とともに、それだけで興味が湧く。なお、「エッセー集」と書いてしまったが、それが折々に書かれた文章を集めただけ、という印象を与えたら、評子の本意ではなく、まして著者の本意ではないはず。本書は極めて周到な統一的構想の下で纏(まと)め上げられた、書き下ろしの書物に匹敵する内容であることをお断りしておきたい。
序章という形で置かれた文章で、読者は度肝を抜かれる。扱われる具体的テーマのほとんどは、「寅さん」なのだ。そう、あの「私、生まれも育ちも・・・」の寅さんである。著者は、寅さんから、様々な問題を引き出す。「読む」ことの反復・蓄積・集中あるいは「結ぶ」こと。そして、その反対概念としての「ほどき」。全巻を貫く基礎概念、メタファー、贈与、共生、自己組織化などが、手品のように、寅さんから導かれる。
そして第一部は、著者の最も得意とするディドロ論、とりわけフランスでの著者の博士論文のテーマ『ラモーの甥(おい)』を中心に、想像の(創造の)翼を広げるだけ広げる論述が展開される。通称『ラモーの甥』は、作曲家ラモーの実在の甥(彼も一応音楽家ということになっている)を一種カリカチュアライズした「彼」なる人物と、「私」というまあ良識派の哲学者との対話という形で書かれたディドロの作品である。と言っても、生前刊行されず、ゲーテがドイツ語訳を造ったことで逆にフランスで注目されるようになった不思議な運命の下にある著作であった。
「彼」と「私」は言わば「ゴーロワ」的(陽気、猥雑(わいざつ))なるものと「クルトゥワ」的(文明的)なものとの対比のメタファーを担っているともとれるが、著者はそこから漱石の『明暗』論、イギリスの小説家サミュエル・リチャードソン論、あるいは精神医学の泰斗レイン論など、縦横無尽の「博論」(この言葉は、普通博士論文の略語であり、著者も本書でその意味で使っているが、ここでは「博引」あるいは「博捜」と同じ意味で評子が造語してみた)のさじ加減は驚嘆するほかはない。
その空気を引きずりながら、第二部で、著者の筆はモーツァルトへと進む。育った環境からすれば、クラシック音楽への著者の深い造詣は、疑うべくもないが、失敗した作曲家ラモーの甥と、神童モーツァルトを重ねながら展開される立論の数々の面白さは、読んで味わって戴(いただ)くほかに術(すべ)はない。
最後に置かれた災害被災者の「哀(かな)しみ」への共感に発する、夭折(ようせつ)のディヌ・リパッティとクララ・ハスキルという二人のピアニストの間の情感のやりとりの再現、モーツァルトの「イ短調ソナタ」を題材にしたこの件(くだり)、とりわけディヌの才能を前にしたクララの絶望的な呻(うめ)きは、ピアニストとしての名声をあれだけ恣(ほしい)ままにしたクララにして、と思うと、魂を揺すぶられるような感に打たれる。巻をおいてしばし凝然とした。
ALL REVIEWSをフォローする