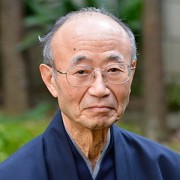書評
『大仏再建―中世民衆の熱狂』(講談社)
重源と時代の激動描き出す
パリのエッフェル塔、ニューヨークの自由の女神に匹敵する構築物を日本国内に探すとすれば、それは東京タワーなどではないだろう。かけ値なしにその任に耐えうるのは奈良の大仏をおいてほかにはないのではないか。国家の威信、民衆の熱情、そして文明の輝きにおいて、その三者からは共通の香りが立ちのぼってくるからだ。周知のように奈良の大仏は聖武天皇の天平年間に創建されたが、治承四年(一一八〇)の源平合戦のさなか、平重衡による南都の焼き打ちにあって焼亡した。朝野はあげて大仏の再建をのぞみ、その一大国家事業のプロデューサー、すなわち「大勧進職」に任ぜられたのが俊乗坊・重源(ちょうげん)であった。
武士の家に生まれたかれは醍醐寺で出家し、きびしい修験の行をつんで中国の宋に渡ること三度、「入唐三度聖人」と称された。その豊かな国際感覚と政治力、群を抜く組織力と不屈の意志を買われて、大仏再建という巨大プロジェクトを牽引(けんいん)する頂点に立ったのである。ときに六十一歳。以後大仏殿の落慶供養までの十五年間、言語に絶する困難をかいくぐって超人的な活動をつづけた。
時代は平家一門が壇ノ浦に亡び、頼朝が奥州の藤原氏を滅ぼして鎌倉に幕府を創設する転換期にあたっていた。重源は京都に後白河法皇や九条兼実を訪ねて工作する一方、鎌倉の頼朝の助力をえて政治・経済上の便宜をえ、大仏の鋳造と大仏殿の建設を軌道にのせていった。周防の地(山口県)に用材を求め、職人集団を組織するとともに阿弥陀(あみだ)信仰にもとづく独自の同行・同朋(どうほう)集団をつくりあげて、民衆のあいだに大仏信仰の火を燃えあがらせていった。
著者のまなざしはそのうねるような歴史の推移を目くばりよく堅実に追い、政治と文化と宗教のネットワークが大仏再建という目標にむかってどのように統合されていくのかを生き生きと蘇(よみが)らせている。近ごろ珍しい手ごたえ確かな歴史記述である。
ALL REVIEWSをフォローする