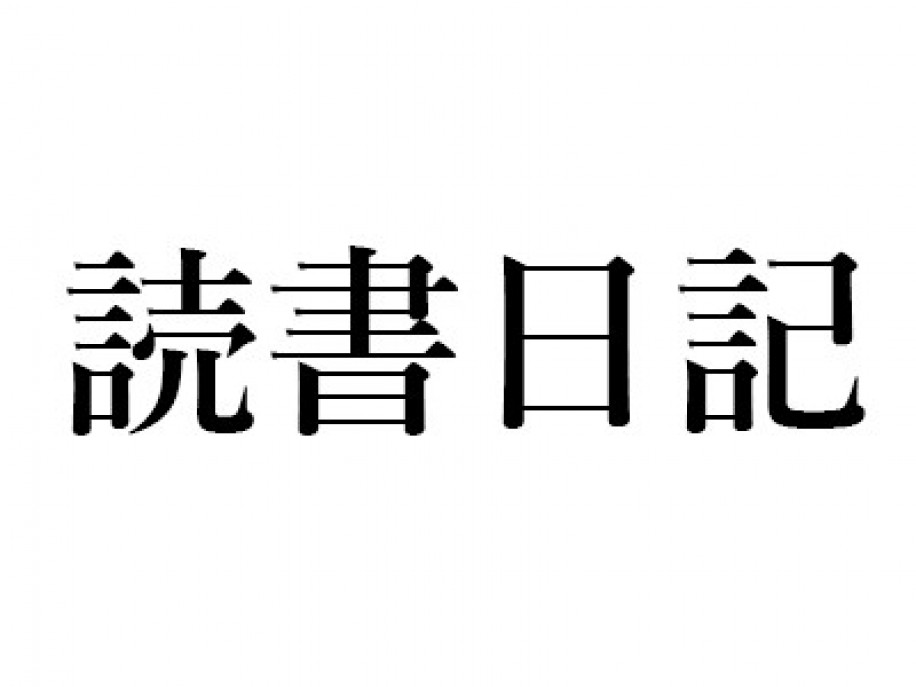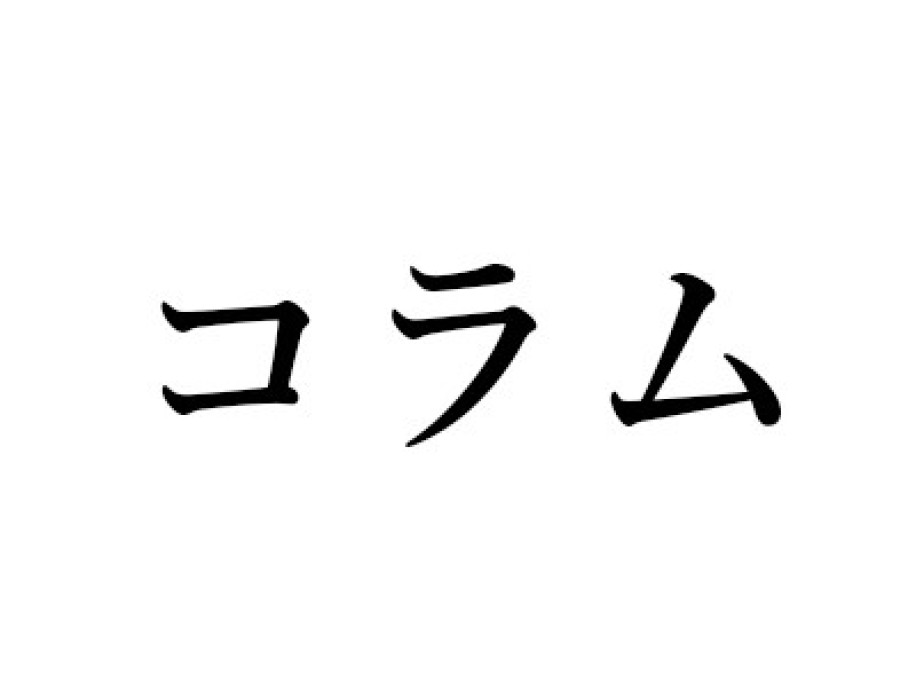書評
『真っ白でいるよりも』(集英社)
「細部を書かんか細部を!」
六月の第二日曜の暑い夕方、フランスオークス、着飾った女性たちの社交の場としても知られる通称エルメス杯も終わり、人々が帰りはじめた頃、競馬場出口の近くで、ぼくは老婆と若い女性のカップルを見た。ふたりとも、とてつもなく派手なオレンジのドレスを着ていた。若い方はどう見てもモデルで、背は高く、申し分なく美しい。年老いた方は少なくとも七十歳には達しているだろう。歩くのも覚束ない。そして、見事な白髪の上に置かれた、沢山の花と騎手たちの写真をあしらった豪奢な帽子!この日集った女性の中で目立つことNo.1のレディは、文句なくその老婆だった。
ゆっくりと出口に向かい、緑鮮やかなシャンティイの森の中に静かに消えていくふたりを眺めながら、ぼくはぼんやりといろんなことを考えていた。いや、正確にいうなら、あまりにも強烈な印象だったのでなにかを考えようとしたが、なにを考えたらいいのかわからなかったのだ。
ああ……。ぼくは思った、ここにいるのが谷川俊太郎さんだったら、なにかとても重要なことを詩で考えることができたのに!
なぜ詩を読むのか。
ぼくにとって、いちばんの理由は「なにかきちんとしたことを考えられる」からだと思う。
もちろん、小説や批評やエッセイを読みながらでも、なにか別のものに触れながらでも「なにかを考える」ことはできる。けれど、ぼくは、詩を読んでいる時、自分がいちばん「考える」ことに近づいているような気がする。それはたぶん、詩という表現が人間の「生の考え」、別の言い方をするなら「思考」にもっとも密着した形式だからだろう。詩を読むということは、他人の「考える」現場を直に覗き見ることだ。そして、そんな風に考えることができるのかと驚き、その時はじめて自分も「考える」ということをやってみたいと思うのである。
「細部を書かんか細部を!」本を読みながら彼女は叫んだ
誰の小説だったかは忘れたが表紙はモンドリアンそっくりで
ぼくらはソファに互い違いに寝ころんで本を読んでいたのだ
ぼくは男ってのはときに人生を要約したいという
止み難い欲求に駆られることがあるんだとかなんとか言って
ほら〈生きた愛した死んだ〉っていうのは誰の墓碑銘だっけと
水をむけたが彼女は猫みたいに唸っただけだった
そこでぼくは煙草に火をつけ心の中で自分に言った
細部ってのはリアルタイムのテレビ中継みたいなものさ
退屈っていやこんなに退屈なもんはない
せめて十年ぐらいの単位で人生を俯瞰してみたらどうだい
たとえ疲れて元気がなくてすっかりめげているにしても
そういう自分がユーモラスに見えるってこともある
すると彼女が言った「観念にはユーモアってもんがないね」(詩集『真っ白でいるよりも』より「川」、集英社)
同じようなことを小説で書けるし、エッセイでも書ける。けれど、印象はこの詩の方が遥かに強い。なぜなら、ここで俊太郎さんは人生の「細部」の描き方を教えてくれるからだ。細かくたくさん書くことと「細部」を一瞬のうちに描くことはまるで違うのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする