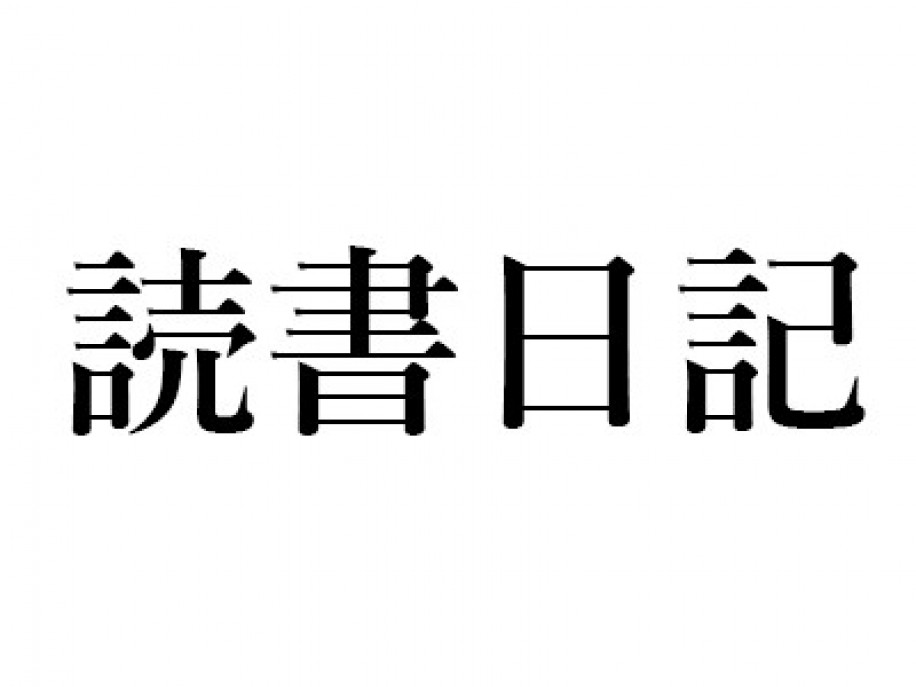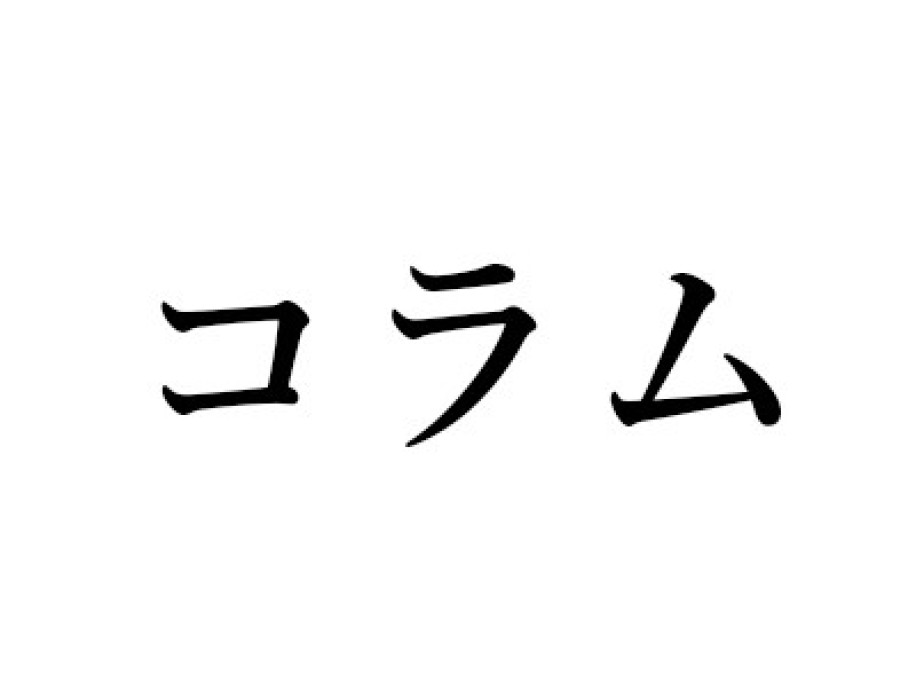書評
『永瀬清子詩集』(岩波書店)
性別の「らしさ」を結果として生み出す声
一九〇六年二月、岡山に生まれた永瀬清子が詩人を志したのは、一九二三年、十七歳のとき『上田敏詩集』を読んだことがきっかけだという。その後、佐藤惣之助に師事し、宮澤賢治の『春と修羅』に出会ってから、「シュールやモダニズムを必要としていない」(「自筆年譜」)言葉で、地に足のついた日常と、人も自然もない「あの極めて高い所に泛(うか)んでいるもの」(「貴方の手で」)へのまなざしに支えられた世界を、焦ることなく丁寧につくりあげていった。谷川俊太郎の選になる本書を通読すると、男と女の役割と立場や地位の格差を前提とした日常に、時代の制約を感じざるをえない。同時に、現代においてもほとんど変わっていないのではないかと嘆息させられもする。結婚、出産、戦争を経て岡山で農地を耕し、季節ごとにめぐってくる仕事に追われるなか、永瀬清子はこの不自由と正面から向き合いつづけた。
一九四〇年に刊行された初期の詩集『諸国の天女』で、彼女は「詩をかく日本の女の人は皆よい。」(「流れるごとく書けよ」)と記した。日々の生活を背負い、なんの名誉もなく、「台所の仕事にもせいだして/はげしすぎる野心ももたず/花を植ゑたり子供を叱つたり」しながら、それでも詩を書く。だれのためでもない、自分のために。
「あらゆることを詩でおもひ/あらゆることを詩でおこなひ/一呼吸ごとに詩せよ。」(同)
諦めや従順の表明ではない。ここには外からは見えない矜恃の焰が静かに燃えている。どんな風も、どんな雨も、どんな理屈の「梳(くしけず)り」も、内なる詩の焰を消すことはできない。五十七歳にして、生活のために県庁勤めをはじめてからも、呼吸に等しい詩の命が消えることはなかった。
一九八一年に行われた谷川俊太郎との対談のなかで、永瀬清子は男女の違いを認めて、自分の「人間が堅苦しい」のは「男性的な部分が多いからじゃないかしら」と語りつつ、「女というよりも先に、『わたし』ということがあるのです」と冷静に語っていた。
分析ではなく一種の備忘と観察の場として、彼女は詩と散文のあいだを縫う「短章」を多く残している。そのなかの一篇で、「ある作品にむかって女らしくあれと注文するのはしばしば無駄であり無理である。」(「女らしさ」)と記した。作品を作品たらしめるのは作家の質であって、男だから、女だからではない。「けれどもすぐれた作品は個性として生きている。生きている故に性別をもっている。」(同)
永瀬清子の詩から聞こえてくるのは、性別の「らしさ」を結果として生み出している声である。この声の調整に「私」は心を砕いてきたのであり、それがあったからこそ、距離の取り方がむずかしかった夫との関係をその死後に見直し、思いやりのなさそうに見えた言動の意味を理解できたのだ。
「私が愛のことばに飢えるように/彼もそれが要るのだ、朝顔の蔓に支柱がいるように。/彼が朝顔であることを誰が癒せようか。」(「女の戦い」)
朝顔を朝顔として受け入れるやさしさと、その本性は変えられないのだとする沈着さの共存。生のなかで一本の支柱になりうるものとしての詩の可能性を、こんなふうに示してくれた人はいない。
ALL REVIEWSをフォローする