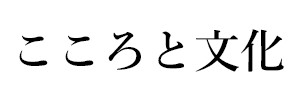書評
『アルツハイマー病の謎―認知症と老化の絡まり合い―』(名古屋大学出版会)
「アルツハイマー型認知症(=AD)エピデミック」の時代、一筋縄ではいかない認知症と老化の問題をどのように読み解くか
本書第1章冒頭で引用された北米の研究者の発言によれば、2050年までに、世界のアルツハイマー型認知症(以下ADと略す)患者数は1億1500万人を越えるとのことである。確かに21世紀は「ADエピデミック」の時代と言われる。なかでも日本は、圧倒的スピードで超高齢化社会に移行しつつある「モデル社会」で、テレビをつければ、(高齢者の交通事故を含む)老人問題や(入所施設選びまで含む)介護をテーマにする番組が目白押しである。そしてこれらの背後には、ADをはじめとする認知症の姿が影のように浮かび上がり、視聴者は自らの、あるいは介護が必要となった親世代の今後へ不安を募らせることになる。医療人類学者マーガレット・ロックが書いた本書『アルツハイマー病の謎』は、2012年末までの研究データをもとに、2013年に刊行された原著の翻訳である。しかし論じられる内容は今日読んでも一切古びたものではないことに驚かされる。話題は、ADの研究史、軽度認知障害(MCI)、バイオマーカー、アミロイドカスケード仮説、若年性認知症、遺伝とアポE4型遺伝子、ゲノムワイド関連解析(GWAS)との関連、エピジェネティックス、そして「埋め込まれた身体(embedded bodies)」等…と広範な領域に及ぶ。
20世紀初頭にアロイス・アルツハイマーが発見した、特定患者の脳に見られるアミロイド斑と神経原線維変化。そうした神経病理学的研究を皮切りに、今日まで連綿と続く原因物質の解明とその蓄積を防ごうとする研究。それに関係する遺伝子やバイオマーカーの探究。創薬やその挫折。ロックは、世界の一線で活躍する研究者へのインタビューを通じてこれらを紹介していく。アミロイド仮説は現在においても本疾患の核心に至るための基礎であり、予防や治療に通じるものであることを読者は知ることになる。ロックは医療人類学者であるが、ADの歴史や、それに引き続く本疾患の医学研究、神経病理学、遺伝子研究を扱う章の記載は生彩を放ち、豊富な図表等もあいまって、すぐれたメディカルライターでもあることに気づかされる。
そして本書のテーマである、副題でも示されている、認知症と老化の絡まり合いが論じられる。結局のところ加齢によってリスクが高まっていくADとは、何なのか。アミロイドの蓄積がはたして真の原因なのか。そうした単一の病因を求めるモデルでとらえられるものなのか。ADと単なる老化とはどこが違うのか。遺伝的な影響があるとして、それは時計仕掛けのようにある時点での発症が決まるものなのか。ロックはこれらの問題に、ひとつひとつ向き合いながら答えを求めようとする。そして読者は、はからずも遺伝研究の最前線、脳神経や加齢研究の最新理論、人間の身体が環境との間でくりひろげる一筋縄ではいかないいくつもの不可思議な現象に直面することになる。
本書を読むと、一般の読者でも、あるいは臨床や介護に携わる者にとっても、有用で刺激的な視点に誘われるだろう。評者にとって、とくに第4章で登場するAPOEε4遺伝子の話題は、その複雑な内容を平易な日本語で読むことでやっと理解が及ぶものになった。
つい最近(2018年6月)、日本でも広く処方されている抗認知症薬が、フランスでは保険適用から除外されることになったという新聞記事が出て、驚かされた。副作用の割に効果が低いという理由だからであるという。ADをめぐる領域は、今後もこうした複雑で流動的なものになっていくのだろうか。なお表紙や最終章に、ADになりながら表現活動を続けたW・ユターモーレンが描く自画像が数枚掲載されている。この画家に注がれたロックのまなざしも感動的である。多くの思索と余韻を読者に与えるお薦めの一冊である。
[書き手]江口重幸(えぐち・しげゆき)
1951年生まれ。精神科医。東京武蔵野病院。
ALL REVIEWSをフォローする