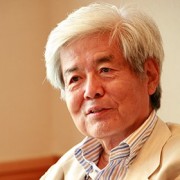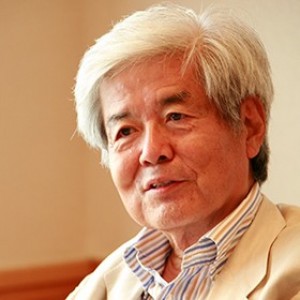書評
『「あの世」と「この世」のあいだ ――たましいのふるさとを探して』(新潮社)
切実な思いが生んだ書物
あの世もこの世も、老人には懐かしい言葉である。実質的な内容を欠くという意味で、じつはほとんど死語ではないか。生死はもっぱら個人のものとなり、直葬、家族葬は半数を超えた。あの世、つまり死後の世界はもはやないというしかない。この世つまり世間もしだいに具体的な形を消して行き、グローバル化したネット空間だけが生き残る。
著者は日本の田舎を訪ね歩く。「人と人、人と自然との豊かなつながりをいまだ保っており、死者や神々への信仰はその間に満ち満ちている」、そういう世界がそこには残っているのではないか。だからたとえば宮古島であり、与論島であり、八丈島である。でも思い直してみると、本土にも島というしかない場所も多い。能登や伊豆は半分は島である。そうした場所を訪ね、「客観的な分析ではなく、共鳴による理解がしたい」と著者は思う。
大学院生の頃、私は野生動物を調べていた。対象である動物を「科学的に」記述することを続けながら、最後に書いたことがある。動物という対象を最終的に人が理解できるとしたら、それは理屈ではなく、共鳴というしかない、と。私の恩師はその文章を校閲し、「共鳴」を赤線で囲い、引き出し線の先に「合掌」と書いてくださった。むろん精神科の患者さんに共鳴するとしたら、それは危険なことでもある。
あの世とは「ふるさと」ではないか。著者はそう感じる。人はしばしばそこへ戻りたいと思う。水俣の海に見える小島、そこはかつて葬送の場所だった。現在でも瀬戸内に埋葬の場所と新たに決めている小島があるという。現代人の心の奥底にも、その気持ちが眠っているのであろう。単に目の前から死者を消そうという、機能的な意味だけではないのである。
遠野を訪ねて、著者は書く。妖怪や怪異についても、現代人は機能的な解釈をしようとする。それは違う。むしろ「現在の事実」だという柳田国男の言葉を引く。「そこで出会う不思議なものたちは、自然と人間のつながりそのもの」なのである。私も水木しげると対談をしたときに、「妖怪って本当にいるんですかね」と問われて、往生したことがある。かつては河鍋暁斎、昭和では水木しげるの妖怪が、あれだけ人を引き付けるのは、それがだれの心にも棲(す)むからである。意識が理性に頼って作り上げた都市の中で、人の心は邪魔になるだけであろう。だからコンピューターが人を置き換えるという、バカなことが起こり、論じられるのである。
北海道を訪ねた著者は、現代のアイヌの孤独について語る。これはいまやまさにグローバルに生じていることである。自然から切り離され、伝統の意味が失われた世界で、アイヌであるとはどういうことか。既成宗教はそれをもちろん満たさない。
読了して思う。切実な思いから書かれた書物であり、それが過激に至らず、極めて健康な思想を生み出している、と。人は0・2ミリの受精卵として生じる。数十キロの成人の身体は、すべて田畑あるいは海や川の物質を寄せ集めて作られている。その意味で身体は自然そのものだが、都市社会の「自分」はそのすべてを意識から消し去り、自分を自分という独自の存在とみなし、母なる自然を「環境」などと呼び捨てる。こうした異常な世界はいずれ崩壊するしかない。
最後に著者は「自分は何を書きたかったのだろう」と自問する。その答えは「魂のふるさと」であった。
ALL REVIEWSをフォローする