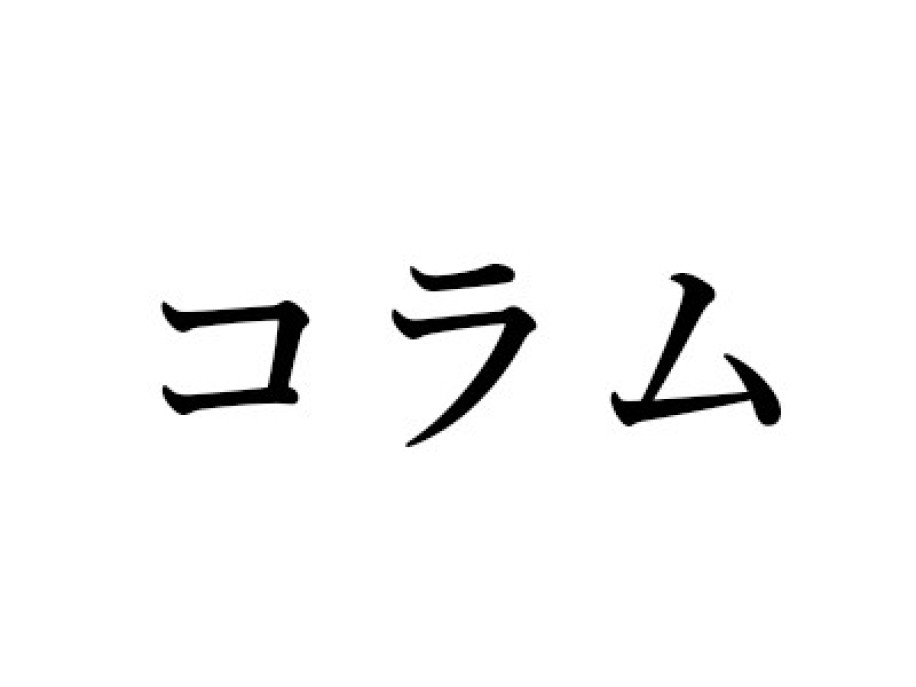書評
『東大生はどんな本を読んできたか―本郷・駒場の読書生活130年』(平凡社)
学生読書文化百三十年史
『東大生はどんな本を読んできたか』を読む
二〇〇六年の全国大学生一万人余の調査によると、読書時間ゼロと回答した学生が三人に一人。平均読書時間も一九七一年には百八分(一日)だったのが、七〇年代に急減し、今では三十分を割っている。かつては大学生といえば読書人とされたのに、今や「無」読書人に成り下がってしまった。どうしてなのだろうか。
本書(永嶺重敏『東大生はどんな本を読んできたか――本郷・駒場の読書生活130年』平凡社新書、二〇〇七年)は、東京大学をフィールドに、学生の読書を百三十年もの時間幅でとらえた。百三十年前といえば、大学南校や開成学校などのプレ東京大学時代である。そこから、明治十年代の東京大学時代、帝国大学時代、明治三十年からの東京帝国大学時代、そして今に至る東京大学時代へとたどっていく。
これほど長い時間幅から見た学生読書文化史は本書が初めてで、それだけでもすごい。しかも、学生はどんな本を読んでいたかだけでなく、古本街や図書館の利用、東京学生消費組合赤門支部の読書運動など、読書を支える周辺文化も多くの資料から発掘し、読みものとして楽しい。
昭和戦前期の学生消費組合のドル箱は講義プリント(学生の講義ノートを謄写印刷したもの)で、組合の図書売り上げの四割を占めていた。こんなくだりを読むと、今の学生の単位のための一夜漬け勉強も、昔の学生とそう変わらないと妙に安心したりする。
しかし、一九七〇年ごろまでの大学生は今と比べれば、難解な本をはるかに多く読んでいたことは確かである。著者はそうした逝きし日の学生の読書熱の背後に、「教養主義文化」や「マルクス主義的な読書モデル」「全集モデル」「寮での読書共同体」が控えていたと見る。読書は “孤読”ではなく、“共読”だったというのだ。
読書離れを学生個人の問題とするのではなく、仕掛けが不足しているからだととらえているところが鋭い。そして、読書マラソンや朗読会、読書会を盛んにすることなどを提案している。
学生の文化史という魅力的な研究ジャンルを切り開いた力作である。
初出メディア
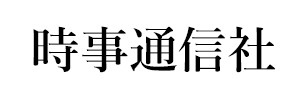
時事通信社 2007年11月25日
ALL REVIEWSをフォローする