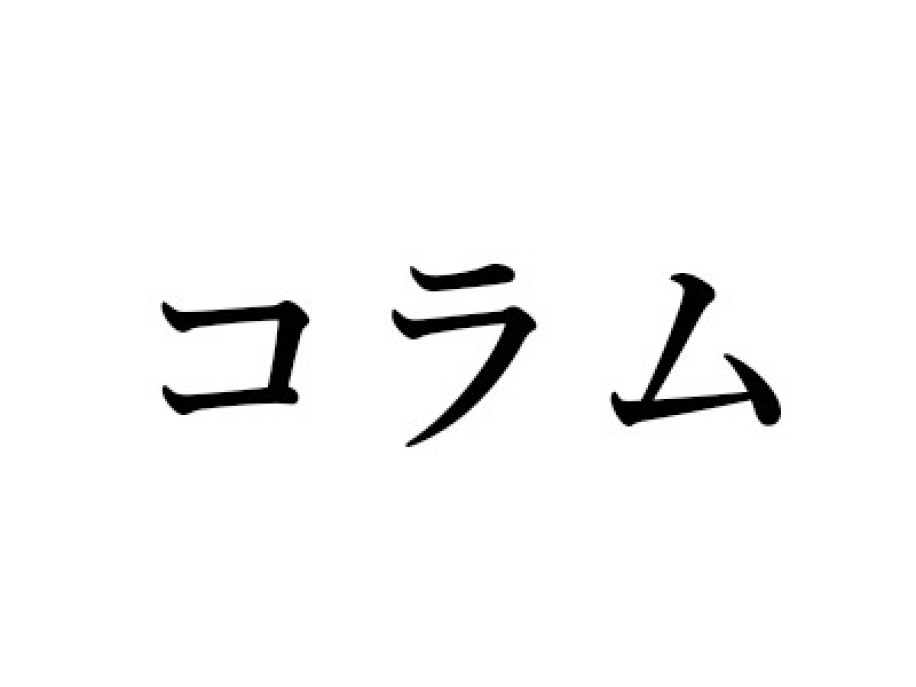書評
『ファントマ幻想―30年代パリのメディアと芸術家たち』(青土社)
電波のように遍在する幻
本書はその副題が示すとおり、一九三〇年代のパリで離合集散を繰り返した芸術家たちの横顔に、メディアとの関わりを通じて光をあてた、刺激的な文化史である。この時代におけるメディアとは、サイレントからトーキーへと移行しはじめた映画であり、またそれ以上に、無線通信から発展し、報道やルポルタージュを経てあらたな形式を模索していた、ラジオという媒体を意味する。
一九三三年十一月、『ファントマ哀歌』と題された番組が、フランス全土に放送された。著者はこの番組の制作スタッフのなかに、思いがけない四人の芸術家の名前を見出す。作曲には、ナチスの迫害を逃れ、パリを経由してアメリカに渡ろうとしていたクルト・ワイル、声と演出にはメキシコへ旅立つ前のアントナン・アルトー、テキストにはシュルレアリスム運動と袂をわかっていたロベール・デスノス、音楽編集にはキューバから亡命してきたアレホ・カルパンチエール。
強烈な個性をもつ彼らをとりまとめたファントマとは、いったい何者なのか。ファントマは、一九一一年、ふたりの大衆小説家の共作によって生まれた、長大な連続活劇の主人公である。変幻自在、けっして正体を明かさない稀代の犯罪者。原著の表紙や挿し絵はもとより、詩人らによる讃歌や映画によって、ファントマ自身のイメージを増殖し、「複製芸術時代」を具現する存在となる。電波のように遍在する幻としてパリの神話を強固にしつつ、同時に人々の目を外へ、アメリカへと開かせたのだ。
著者は盟友たる悪漢を追う私立探偵さながらの愛と執念をもって、この幻を追う。幻を見た四人は、やがてファントマ同様、人生を変えていくだろう。ひとりは華やかなブロードウェイに、ひとりは孤独な精神病院に、ひとりはレジスタンス運動を経て強制収容所に、残る一人は、南米を代表する大作家の道に。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする