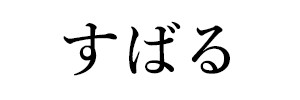書評
『文学の贈物―東中欧文学アンソロジー』(未知谷)
「青いへそ」の幻
激しい動乱を生き、また現在も生きつづけている東中欧諸国について、私たちはどの程度まで理解を深めつつあるのだろうか。未曾有の紛争を契機として情報は増えているけれど、皮肉なことに、そのぶん真偽の境界も曖昧になっている。正しさの基準は、誤りの基準がそうであるように個々ばらばらなのだから、複雑な歴史のからみあいをすべての民族の立場から公正に把握することは、ほぼ不可能に近い。にもかかわらず、いくつかの国名が地図から消える時代にあって、いかなるデータよりも信用に値する不変の基準を私たちは有している、と言えるのではないか。右と左を決定し、東と西を裁断する偏狭な視点ともイデオロギーとも無縁な、裸の人間がくっきりと浮かびあがる地平。すなわち、大陸に寄り添う島国の人間がなかば忘れかけているような、生の拠り所としての「文学」である。
ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリア、セルビア、クロアチア。東中欧文学アンソロジーとしてまとめられた本書には、十六世紀から現代にいたるまで、総計三十二人の訳者の手によって選出された三十二人の文学者の作品が収められている。ルネサンス期の大詩人とノーベル賞詩人がならび、二十世紀のエッセイのあとに十九世紀の詩がならぶという編年体をとらない自在な構成が、「文学の贈物」と呼ぶにふさわしい書物をもたらした。テーマも豊富で、あからさまな政治寓話に偏らないのが好ましい。
チェコのモラヴィア地方に生まれた詩人ヤン・スカーツェル(一九二二―八九)が、「青いへそについての小さなエッセイ」と題した一文でこんなことを書いている。少年の頃、モラヴィアでチェコ人に出会うのはとても珍しく、彼の村では、ボヘミア出身の人間はみな青いへそを持っていると信じられていた。ところが夏休みを過ごすためにプラハから男の子がやってきて、水浴びをするため川辺で服を脱いだところ、へそは青くなかった。チェコ人とモラヴィア人はおなじ民族なのだった、と。
ここに紹介された諸作品は、たぶん国と国のあいだを結ぶ「青いへそ」の迷信を解く手だてになるだろう。「青いへそ」とは、いわば偽りの境界線である。ただし、私たちは「青いへそ」を現出させる言葉に対しても疑念と同等の信頼を寄せなければならない。本当の裏の嘘、嘘の裏の本当。この恐るべき背理もまた「贈物」のひとつなのだから。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする