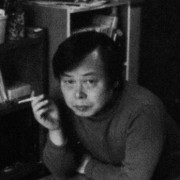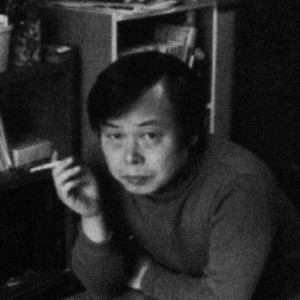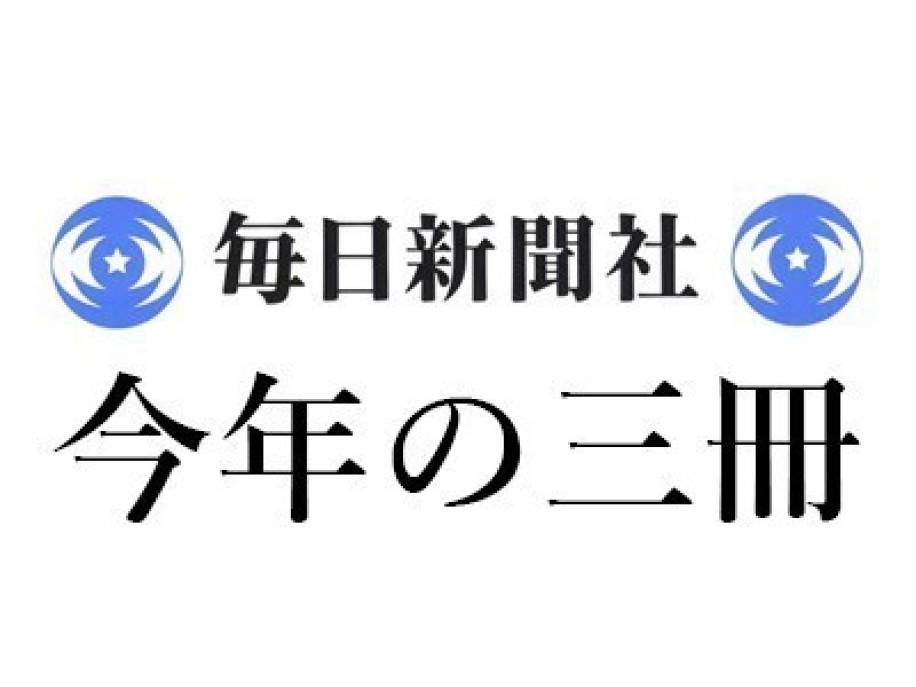書評
『ルーマニア・マンホール生活者たちの記録』(中央公論新社)
母胎であり墓でもあるこの地下世界
ルーマニアの首都ブカレストのマンホールに冷戦後孤児が群れをなして住んだ。十代から二十代も前半のいわゆるチャウシェスクの子どもたち。チャウシェスクの人口増加政策で急増した子だ。独裁政権崩壊後、国家の拘束を脱した子どもたちが街にあふれた。親に棄(す)てられた子、家出してきた子。ブカレストの厳冬は零下二十度になる。地下のマンホールにもぐれば温水パイプのおかげで冬でも十五度はある。糞尿(ふんにょう)の悪臭が気にならなければ、住み心地はそう悪くない。マンホールの闇は巨大な母胎だ。そこのダンボール製寝台で孤児たちはシンナーに酔う。もう外へ出ていく気はない。孤児の保護施設や学校があっても、「俺(おれ)は本当はここが気に入っている」とある少年。シンナーで現実と隔絶した彼は、あたかも生まれてきた事実を取り消したいとばかりに、この生ぬるい地下世界を母胎とも墓とも心得ているようだ。
マンホール生活者には被差別民ロマ(ジプシー)が多い。彼らは外の世界ばかりかここでも集団暴行にあう。暴行を避けるために、わざと自分の腕にナイフで傷をつけ、大量の血をひけらかして難を逃れたりする。
国外に出稼ぎに行こうとする者もいる。若夫婦と子ども三人で国外脱出を謀る一家。亭主はバンク(一種の風刺小咄(こばなし))が得意で、一家には笑いが絶えない。さすがはイヨネスコを生んだ国。悲惨のなかにも人びとは道化役者のようにのほほんとしている。
ルーマニアはローマ帝国滅亡後、旧植民地としてスラブ圏の只中(ただなか)でしぶとく生きのびた。これからどこへ行くのか。ちなみに少子高齢化のわが「経済大国」とは正反対でいて共通の悩みがある。こちらでは中高年の青テント生活者が水平に拡散する。あちらでは年少者が垂直に地下にもぐる。わが国でも昭和ヒトケタ世代あたりまでは、佐野美津男『浮浪児の栄光』の焼け跡の現実を目のあたりに体験した。若いレポーターはときにルーマニアの現実への距離感のとり方にとまどうが、独特のユーモア感覚で巧みにバランスをとり戻している。
朝日新聞 2003年7月20日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする