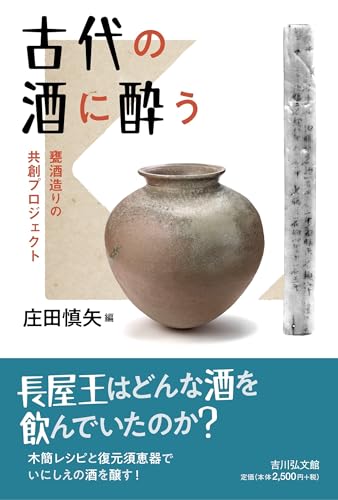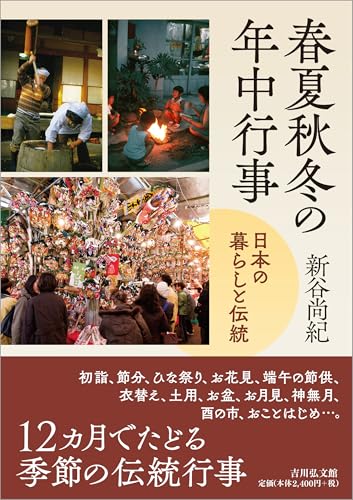前書き
『考証 東京裁判: 戦争と戦後を読み解く』(吉川弘文館)
空前絶後の裁判
極東国際軍事裁判。東京の市ヶ谷で開催されたこの裁判は、一般には東京裁判と呼ばれている。日本が行った侵略戦争や残虐行為に関して、国家指導者たちの責任が追及されたのである。一九四六年五月三日に開廷、一九四八年一一月一二日に刑の宣告が行われている。アメリカ、イギリスなど、欧米諸国を中心とする11か国が、東条英機(とうじょうひでき、元首相・参謀総長・陸軍大臣)以下28人の被告人(公判中に3人が病死などで免訴)を裁くという形式で裁判は進んだ。弁護側と検察側が提出し、裁判所が受理した証拠は3,915通、出廷証人は419人に及んでいる(東京裁判ハンドブック編集委員会編『東京裁判ハンドブック』)。審理の過程を記した「速記録」も、英文で49,858ページという長大な記録となった。東京裁判は、膨大な証拠・証言を駆使して、近代日本の歩みそのものを議論の俎上(そじょう)に載せるものだった。現在を生きる私たちが、この東京裁判を考えることにはどのような意味があるのだろうか。また、裁判から何を学び取る必要があるのだろうか。まずはこの点について、近代日本の戦争の経緯やその被害について、ごく簡単に整理しながら考えておきたい。
戦争と暴力の時代
日本の近代は、戦争と暴力の時代であった。日本は、明治の幕開けとともに近代国家を志向してひた走った。一九世紀後半から二〇世紀前半、当時の世界は、欧米列強が植民地などの支配地域の維持・拡大を目論む、帝国主義の時代である。こうした大きな世界史の流れに、日本は合流してゆく。「大日本帝国」という、その名が象徴しているように、日本もまた、「帝国」を志向するアジアでも随一の軍事大国へと変貌していった。一八九四年には日清戦争が勃発、二〇世紀に入って間もない一九〇四~〇五年には、日露戦争が展開される。朝鮮、台湾などに対する植民地支配の開始、第一次世界大戦への強引な参戦など、日本は「帝国」への歩みを確実に進めていった。日清戦争、日露戦争、そして第一次世界大戦への参戦と、わずか20年ほどの間に、ほぼ10年ごとに対外戦争が繰り返され、その間に植民地支配の体制が確立してゆく――。明治期から大正期にかけての日本がいかに戦争に明け暮れていたのかがわかる。戦争と暴力は、その後もやむことはなかった。帝国日本の歩みは、満州事変、日中戦争、そしてアジア太平洋戦争と、東アジア全域を巻き込む戦争へと連なっていった。
近代日本の戦争と未曽有の被害
戦争や支配には、加害と被害の問題が付きまとう。一九三〇年代以降、日本の植民地支配や戦争による被害は加速度的に拡大してゆく。もちろん、戦争にもルールがある。たとえば、日本も批准していた、「陸戦の法規慣例に関する条約」(一九〇七年)の付属書は、「俘虜は人道をもって取扱わるべし」と定めており、占領地での略奪なども明確に禁止している。それにもかかわらず、日本の戦争でも、多くの被害(被害者)が生じていた。住民や捕虜の虐殺、女性に対する性暴力、家屋の破壊など、「被害」といってもその形態はさまざまである。
アジア太平洋戦争の被害の規模は、どのようなものだったのか。戦闘・戦闘後の混乱や資料の散逸などもあり、被害の実態を正確に把握することは困難だが、各国政府の公式な発表などに基づくと以下のような死亡者の数が浮かび上がる(歴史教育者協議会編、大日方純夫・山田朗・早川紀代・石山久男著『日本社会の歴史 下 近代~現代』)。
日本 310万人以上
朝鮮 約20万人
中国 1000万人以上
台湾 3万人あまり
フィリピン 約111万人
ヴェトナム 約200万人
タイ 詳しい数値は不明
ビルマ 約15万人
マレーシア・シンガポール 10万人以上
インドネシア 約400万人
インド 約150万人
オーストラリア 1万7744人
連合軍将兵・民間人・捕虜 約6万数千人(上記のオーストラリアの死者約8千人と重複)
なお、よく知られているように、日本の死亡者数「310万人以上」のなかには、朝鮮人、台湾人の軍人・軍属約5万人が含まれている。また、中国の「1000万人以上」という数値は、いわゆる「十五年戦争」期全体での死亡者数である。人間の生命の重みを数値だけで測ることはできないが、日本以外の他のアジアの人びとが、戦争の最大の被害者であったということは、覆すことのできない事実だということがわかる。
生き残ることができても、身体や心に重大な傷を負わされた人びとや、その遺家族にまで戦争の傷跡が深く刻印されているケースもあった。戦争の被害は一度で終わることはない。時には時間と世代を超え、人びとの身体と心に刻印されてゆく。すでにみた日本の戦争の死亡者数は、その「被害」の氷山の一角でしかない。
不可視化された被害
戦後、東京裁判やBC級戦犯裁判(アジア太平洋各地で捕虜虐待などの残虐行為を行ったとされる現場の指揮官、将兵の責任が問われた)など、連合国による戦犯裁判では、南京事件(一九三七年一二月)や日本軍による捕虜虐待など、戦時中は日本国民に伏せられていた数々の戦争犯罪の事実が明るみに出た。戦犯裁判の効果の一つは、事件や被害の一端を見えるようにすること、すなわち可視化である。しかし、被害者による告発や、日本の戦争責任を問う声はいまもやまない。一九七〇年代から二〇〇〇年代にかけて、実に89件にも及ぶ戦後補償裁判が行われている(二〇一〇年一月現在の件数。内海愛子『戦後補償から考える日本とアジア』)。
一九九一年一二月、3人の韓国人元日本軍「慰安婦」が日本政府の謝罪と賠償を求めて、東京地裁に提訴している。元「慰安婦」の金学順(キムハクスン)は、NHKのインタビューに対してこう応えている。「日本軍に踏みつけられ、一生を惨めに過ごしたことを訴えたかったのです。日本や韓国の若者たちに、日本が過去にやったことを知ってほしい」(吉見義明『従軍慰安婦』)。日本の敗戦から40年以上の時間が経過しての「告発」だった。日本社会では、「慰安婦」の存在は知られていても、その被害の実態は長く不問に付されてきた。「業者が連れ歩いていた売春婦」、これが当時の日本政府や日本社会の認識だったのではないだろうか。日本軍「慰安婦」制度が、国内法と国際法の双方に違反するものであったこと、そして何より、被害者の人権を幾重にも踏みにじるものであったことが、この後の研究や市民運動のなかで指摘されてゆくことになる。戦後、「慰安婦」問題は長らくその実態に焦点があてられず、いわば「不可視化」されてきたのである。
二〇〇〇年、東京の日本青年館で行われた、「日本軍の性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」は、「東京裁判の再審理」との位置づけが与えられていた。東京裁判が充分に裁かなかった問題を追及する――、それがこの法廷の問題意識の一つであったといえよう。著者も、東京裁判に提出された性暴力に関する資料を収集・分析する共同研究に参加したことがあるが、検討で明らかになったのは、性暴力を追及するための証拠・証言の圧倒的な少なさであった。性暴力の問題が、審理で重要な争点になった形跡はなかった。男性中心の裁判は、「慰安婦」問題をほとんど無視している。それが率直な感想だった(以上、吉見義明監修/内海愛子・宇田川幸大・高橋茂人・土野瑞穂編『東京裁判―性暴力関係資料』)。
東京裁判では、「平和に対する罪」(侵略戦争の共同謀議・計画準備・開始・遂行。「A級犯罪」とよばれる)、「通例の戦争犯罪」(戦争の法規慣例違反。「B級犯罪」)、「人道に対する罪」(戦前、戦中の一般住民に行われた殺人、殲滅(せんめつ)、奴隷化、追放、その他の非人道的行為など。「C級犯罪」。東京裁判では事実上問題にならなかった)の三つの法概念が適用されている。こうした規範にのっとりながら、東京裁判は、日本の戦争責任をどのように裁いたのか、あるいは、いかなる事件を不問に付したのか。なぜ、被害者の声や姿が「不可視化」されてしまったのか。女性国際戦犯法廷は、こうした問題を改めて問い直す必要があるということを、示すものであった。「慰安婦」問題に限らず、私たちが暮らす社会に、戦争や暴力を容認する構造や、歴史認識・戦争観がありはしないか。東京裁判の再検証は、こうした現在の私たちの在り方そのものを考え直す意味を持つのだと考えられる。
東京裁判を読み解く視点
膨大な被害を生んだ日本の戦争を、東京裁判はどのように裁いたのか。戦後の世界や日本で、戦争の被害のうち、何が看過され不可視化されてしまったのか、その一端を、東京裁判をめぐる一連のプロセスから具体的に描き出す。これが本書の目的である。だが、膨大な関係史料を読み解くには、確固たる視座が求められる。数ある現代史の研究テーマのなかでも、東京裁判ほど検討材料が豊富なテーマは珍しい。日本の国立公文書館で数千冊の戦犯裁判に関する記録が公開されるなど、現在、閲覧できる資料は際限なく拡大している。以下、東京裁判の検討に際して、著者が重要だと考えている視点(点検ポイント)について、少し踏み込んで記しておきたい。
第一に、日本軍の残虐行為、戦争犯罪を生んだ根本原因について、どこまで追及のメスが入れられたのか、という問題がある。なかでも、他のアジアの人びとに対する差別の問題は重要である。日中戦争に従軍し、中国人の刺突訓練(初年兵など、戦場経験の浅い者に、中国人の住民や捕虜を小銃につけた銃剣で突き殺させる訓練のこと)に参加した経験を持つ、近藤一はこう回想する。「2名の無抵抗の中国人を刺し殺しても、『たかがチャンコロを殺したに過ぎない』という意識しかないわけです。軍隊だけの教育でそうなったのではなく、小学校からの教育の積み重ねで、中国に対する差別意識があって、それに行動が対応していったのです」(内海愛子・石田米子・加藤修弘編『ある日本兵の二つの戦場』)。元陸軍省法務局長の大山文雄(おおやまあやお)も、戦後の法務省の聞き取りのなかで、戦争犯罪多発の原因の一つに、中国人に対する「蔑視の気持」を挙げている(法務大臣官房司法法制調査部「大山文雄氏からの聴取書」一九六三年一〇月一日、北博昭編『東京裁判―大山文雄関係資料』)。
東京裁判を検討するには、こうした差別意識の問題、さらには、暴力の行使を容認・当然視する、帝国主義・植民地主義・レイシズムといった考え方、発想そのものを議論の俎上に載せる必要がある。本書では、東京裁判の審理が、こうした「発想」とどのような関係にあったのかという点を、詳しく検討していきたい。
第二は、日本の行った戦争をどのように位置づけ、認識するのかという戦争観の問題がある。東京裁判では、日本と連合国、そして時には被告人の間で様々な戦争観が衝突している。日中戦争やアジア太平洋戦争は自衛なのか侵略なのか、戦争の責任は陸軍と海軍のどちらにあるのかなど、東京裁判の一連のプロセスでは、日本の戦争責任やいわば「歴史認識」をめぐる深刻な対立が生じている。当時の被告人や法廷全体が、日本の戦争をどのように捉え、評価したのかを検討することは、現在の歴史認識問題や、先に触れた不可視化された戦争被害の問題を考える上で、不可欠の材料を提供することにもつながる。
以上、二つの視点を重視しつつ、「東京裁判の前史→検察側・弁護側の裁判準備→審理の過程→判決→サンフランシスコ平和条約の調印」という、これまであまり体系的に論じられたことのない一連のプロセスを、諸史料を読み解きながら再検証してゆきたい。
[書き手] 宇田川 幸大(中央大学商学部准教授)
ALL REVIEWSをフォローする