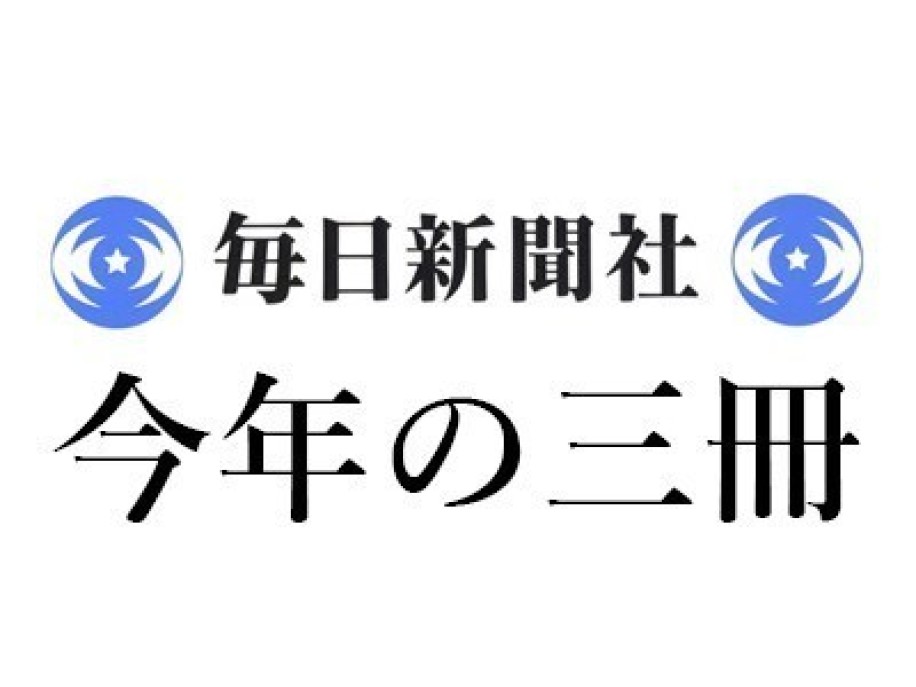書評
『茗荷谷の猫』(文藝春秋)
あんまり例のない、面白い趣向の小説だ。
時代は江戸の終わりから東京オリンピックの昭和三十九年前後まで。場所は巣鴨に始まり千駄ヶ谷に終わる、二十三区内の九か所――。時と所を変えて九つの東京物語が語られてゆく。それぞれの人生は、時に当人も知らないままに交錯している。まるで淡い色で描かれたいくつかの円が、重なり合ったり離れたりして、不思議な色あいの、不規則な水玉模様を生み出しているかのようだ。
第一話は、武士の身分を捨てて植木屋になり、新種の桜「染井吉野」を作り出した男と、その妻の話。第二話は明治に入っていて江戸は東京になっている。何もかも西洋化に向かってゆく中で、黒焼の秘薬作りにのめり込んでいる男の話。どちらも何かもうひとつ割り切れない印象――謎のようなものを残す。
この小説は一種の奇人伝のようなものなのかなと思って読み進んでゆくと、第三話は大正の終わり頃になっていて、茗荷谷の、庭にザクロの木がある家で、夫と共におだやかに暮らしている女の話だ。絵を描くことが好きで才能もあるらしいということ以外、特に奇抜なところはない女。奇人伝ではないことがわかる。けれど、そんな平凡な暮らしの中にもやがて奇妙で不穏な気配が漂ってくる。
九つの話は、そんなふうに淡い謎を残しながら連鎖してゆく。江戸の植木屋の妻の思いは、時代を超え、場所を変えて、ひょっこりと別の話の中で蘇る。茗荷谷のザクロのある家の夫もまた、別の話の中で「踏みはずし」た人生を生きている。謎がようやく明かされてゆくわけだが、決して明かされ切ることはない。不思議な気分は残されている。いや、むしろ濃くなってゆく。そこがいい。人生それ自体が割り切れず、不可解なものなのだから。
この『茗荷谷の猫』(平凡社)の著者は一九六七年生まれ。どうやら女の人らしい。九つの物語のあちこちに古書好き(東京史と幻想文学)であることがうかがわれる。昔の東京はこうだったああだったというウンチクを傾けるのが好きというのではなく、昔の東京を今ここにあるものとして全身で感じとりたいという思いが強い人なのだろう。「夢みる力」が強いんですね。だからこうして、まぼろしを小説に仕立てあげられた。二葉亭四迷『浮雲』、内田百閒『冥途(めいど)』、江戸川乱歩『赤い部屋』などが物語の中に巧妙に取り込まれていて、時代色や、あやしい気分を深めている。
私が最も好きなのは、九つの話の中で異例のおかしみと恐怖? にあふれている第五話『隠れる』。どこまでも気儘(きまま)に暮らしたいと願いながら、人間関係のドツボにはまる男の悲喜劇。「やっ、筑前煮の鍋か?」の一言に、私は大笑い。
【この書評が収録されている書籍】
時代は江戸の終わりから東京オリンピックの昭和三十九年前後まで。場所は巣鴨に始まり千駄ヶ谷に終わる、二十三区内の九か所――。時と所を変えて九つの東京物語が語られてゆく。それぞれの人生は、時に当人も知らないままに交錯している。まるで淡い色で描かれたいくつかの円が、重なり合ったり離れたりして、不思議な色あいの、不規則な水玉模様を生み出しているかのようだ。
第一話は、武士の身分を捨てて植木屋になり、新種の桜「染井吉野」を作り出した男と、その妻の話。第二話は明治に入っていて江戸は東京になっている。何もかも西洋化に向かってゆく中で、黒焼の秘薬作りにのめり込んでいる男の話。どちらも何かもうひとつ割り切れない印象――謎のようなものを残す。
この小説は一種の奇人伝のようなものなのかなと思って読み進んでゆくと、第三話は大正の終わり頃になっていて、茗荷谷の、庭にザクロの木がある家で、夫と共におだやかに暮らしている女の話だ。絵を描くことが好きで才能もあるらしいということ以外、特に奇抜なところはない女。奇人伝ではないことがわかる。けれど、そんな平凡な暮らしの中にもやがて奇妙で不穏な気配が漂ってくる。
九つの話は、そんなふうに淡い謎を残しながら連鎖してゆく。江戸の植木屋の妻の思いは、時代を超え、場所を変えて、ひょっこりと別の話の中で蘇る。茗荷谷のザクロのある家の夫もまた、別の話の中で「踏みはずし」た人生を生きている。謎がようやく明かされてゆくわけだが、決して明かされ切ることはない。不思議な気分は残されている。いや、むしろ濃くなってゆく。そこがいい。人生それ自体が割り切れず、不可解なものなのだから。
この『茗荷谷の猫』(平凡社)の著者は一九六七年生まれ。どうやら女の人らしい。九つの物語のあちこちに古書好き(東京史と幻想文学)であることがうかがわれる。昔の東京はこうだったああだったというウンチクを傾けるのが好きというのではなく、昔の東京を今ここにあるものとして全身で感じとりたいという思いが強い人なのだろう。「夢みる力」が強いんですね。だからこうして、まぼろしを小説に仕立てあげられた。二葉亭四迷『浮雲』、内田百閒『冥途(めいど)』、江戸川乱歩『赤い部屋』などが物語の中に巧妙に取り込まれていて、時代色や、あやしい気分を深めている。
私が最も好きなのは、九つの話の中で異例のおかしみと恐怖? にあふれている第五話『隠れる』。どこまでも気儘(きまま)に暮らしたいと願いながら、人間関係のドツボにはまる男の悲喜劇。「やっ、筑前煮の鍋か?」の一言に、私は大笑い。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする