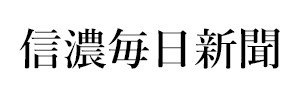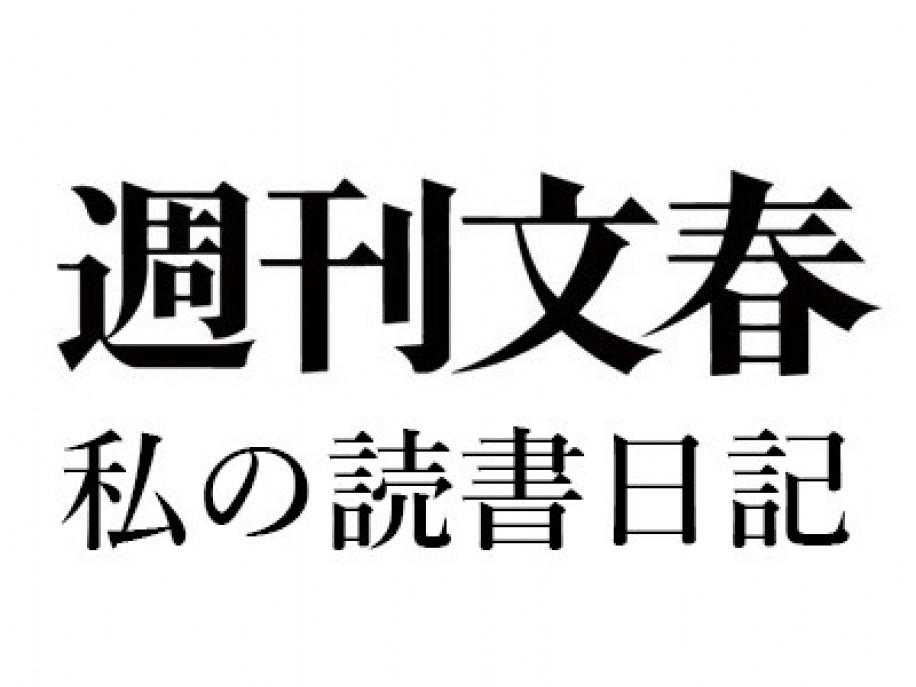書評
『牛車で行こう!: 平安貴族と乗り物文化』(吉川弘文館)
平安貴族のリアリティー実感
牛車(ぎっしゃ)の車種とそれにふさわしい身分・階層。牛車のスピード。他人と同乗する際のルール。現代生活に限りなく不要な平安貴族のための実用情報のオンパレードだというのに、本書を読んでいる間中、私は日頃の読書体験とはまったく別種の興奮を覚えていた。漠然と理解していたことのディティールが、掌(たなごころ)を指すがごとく明らかになっていく感覚は、都で書かれた物語やエッセーを山ほど取り寄せ、想像を逞しくしてはいるけれど、貴族の生活も檳榔毛(びろうげ)の車も実見したことがない、地方在庁官人の夢見がちな娘に、都市文化の映像資料が与えられ、「これが!『源氏物語』のあの場面の!」と興奮しているかのようだ。学生に「唐車(からぐるま)はベンツ、檳榔毛車(びろうげのくるま)はクラウン、網代車(あじろぐるま)は私が乗っているアクアだ」と説明している著者も、同様の心情を抱いているに違いない。
たとえば現代の自動車とその文化を、読者にいちいち説明しながらストーリーを進める小説家がいないように、平安時代(~中世)の物語や絵巻物の中に登場する牛車は、あるシチュエーションに対して、なぜその牛車が用いられるのか、解説は付されない。
だが牛車の種類と身分の対応関係が理解できていれば、「源氏物語」で、前東宮妃という貴い身分の六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)が、光源氏の正妻・葵の上の一行から侮られ、辱めを受けたのは、素性を隠すため、その立場にふさわしからぬ「網代のすこしなれたる」車に乗って祭見物に出かけたことが理由だとわかる。あるいは和泉式部と忍ぶ恋の仲であった敦道親王が、素性を隠すため、牛車を「女車のさまに」設えたとする「和泉式部日記」の記述に接して、内部が見えないよう、簾(すだれ)の内側に布の下簾を掛け、また簾の下から女性の衣の袖や裾をのぞかせる「出衣」で偽装したのだな、とピンとくる。
自動走行車の実用化が目前に迫った21世紀の日本で、それでも古典のページを繰る者が、「牛車」というメディアを通じて実感する、千年前の政治や恋のリアリティーの、なんと切実でみずみずしいことだろう。
[書き手] 橋本 麻里(はしもと まり・公益財団法人永青文庫副館長)
ALL REVIEWSをフォローする