書評
『変貌する清盛―『平家物語』を書きかえる』(吉川弘文館)
“おごる平家”を検証する
「平家物語」は、日本の物語文学史上、最高傑作の一つといわれる。そこから派生した文学、芸能作品は、中世以降、現代に至るまで膨大な数に上る。古代王朝政治が滅び、源平合戦の争乱期を経て中世の幕が開くまでの、この壮大な歴史ドラマを知らない人は、まずいない。そこに描かれた平清盛のイメージも、多くの人が共有してきた。主人公の清盛は、成り上がった末の「おごれる人」であり、権力をほしいままにして、王法をないがしろにしたり、南都(奈良)を焼き打ちにするなどの「悪行」を重ね、天罰とも思える熱病にかかって死んだ、というものだ。やがて、あれほどの栄華を誇った平家も、源氏に滅ぼされる。
そうした「おごる平家」を象徴する「悪いやつ」としての清盛像は、どのようにして創られたのか。
著者は、平家物語を軸に、清盛と同時代の日記や文学に記された清盛を探り、もう一つの清盛像を浮かび上がらせる。
例えば、「十訓抄(じっきんしょう)」には、部下に対して思いやりと気配りを見せる清盛が記され、「愚管抄(ぐかんしょう)」には、寛大で包容力があり、双方の調和を取る清盛が描かれる。
また九条兼実の日記である「玉葉(ぎょくよう)」は、平治の乱(1159年)以後の清盛を好意的に描く。しかし、清盛が79年にクーデターを成功させて権力を掌握した後、兼実の筆は、清盛に対して嫌悪に満ちたものになっていくという。
ついで著者は、「平家物語」の中の清盛を詳しく分析。さらに、中世後期の謡曲や幸若舞曲で平家物語が大衆化していき、清盛の「悪行」も変貌していくことを記す。また近世演劇(浄瑠璃・歌舞伎)で、清盛の人間的悪行ぶりが誇張されていったことを論証する。
それだけではない。近代以降、国定教科書や研究書、また吉川英治の「新平家物語」ほか小説の中で、清盛像がどう変貌してきたかを述べる。研究書ではあるが、読み物のごとく面白い。
[書き手]高橋 千劔破(たかはし ちはや・文芸評論家)
初出メディア
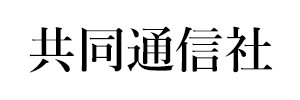
共同通信社 2011年4月
ALL REVIEWSをフォローする



































