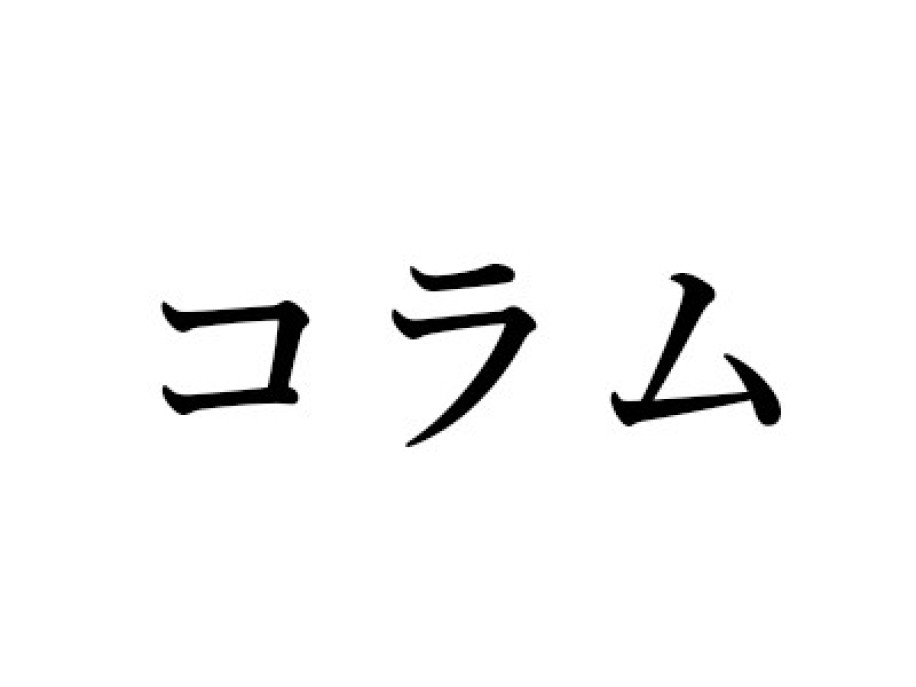書評
『子どもの涙』(高文研)
少年の自己形成史
いまも時折、散逸をまぬがれて本棚や押入に残っている古い本を手にとってみることがある。落書きや手垢に汚れたページを繰っていると、子どもの頃の歓びや哀しみの感情までが胸底でざわざわと騒ぎ始める。
同世代の異性が何を読んだか知りたくて手に取ったが、徐京植(ソキョンシク)『子どもの涙』(柏書房)はむしろ本の思い出を手がかりにした自己形成史であり、心にひびく上質な文体でつづられている。
一九五一年、京都に生まれた。自転車屋の丁稚から身を起こした父と、西陣に子守に出た文字の読めない母。在日朝鮮人の家庭では、子どもたちが本を読んでさえいれば喜んだ。本は遠い存在で、書店の方が小学校に出張してきた。「世界じゅうの子どもが読んでいる」講談社版世界名作全集の思い出。『揚子江の少年』を「よすえの少年」と読んで兄にバカにされたこと。差別に出会ったとき、心を支えてくれた『飛ぶ教室』の「泣くこと厳禁!」ということば……。ああ、そんな本があった、とわたしの記憶もたぐり寄せられてゆく。
しかし母国ではない国での「出世」への親の期待は「読むべき本」という強迫観念を生み、通読できなかった『魔の山』は思春期のコンプレックスになる。一方、太宰治に自分に似た「いやな奴」の臭いをかいだのは、名門中学に入った著者が、「わたしはお上品な中産階級のなかに潜り込むことができたことを内心では喜んでおり、いざというときには自分にとってかけがえのない人々を裏切るのではないか」と自己不信を抱いたことによる。
この亀裂は在日朝鮮人に固有の経験かもしれず、それをもたらしたのは日本の植民地支配である。卓球で「アッ、汚いぞ。朝鮮カットやないか!」という級友の言葉を、わたしは身の縮む思いで読んだ。
兄弟身内のことで泣きたい気分にさせられることが、まあ何回かは、あった。けれどもそのたびに「本是レ同根より生ズルヲ……」と曹植七歩詩が心に蘇ってきてしまう。そうしてそういう自分自身が、いつもちょっと笑えるのである。
『三国志』に夢中だった兄たち徐俊植、徐勝らは韓国留学中に捕らわれ、著者は苛酷な救援の日々を「魯迅」と共にすごす。
本書は内に問うた誠実な書評集ともいえようし、理想主義を冷笑する今日の日本で、清冽な読後感を与えてくれる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする