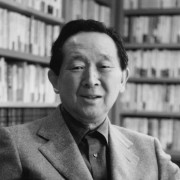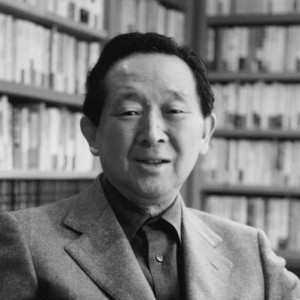書評
『くっすん大黒』(文藝春秋)
一年ほど前に出た町田康の小説『くっすん大黒』を読んだ(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1998年)。題名がピンと来なかったし知らない作家なので、この作品がドゥマゴ文学賞、野間文芸新人賞を受けたと聞いても何となく書架に積んでおいた。しかし、現代詩人会のゼミナールで〝詩と散文のあいだ〟というような題で彼がねじめ正一と対談し、私がその司会をすることになったので、俄(にわか)勉強で読んだのである。私の手もとにあったのは昨年十一月の終わりの第九刷だったから今ではもっと部数も伸びているに違いない。
読みはじめてすぐ、もっと早く読まなかったのを後悔した。この作品は現代社会を少しも観念的ではなく自由な語り口で痛烈に批判しているのである。彼ののびのびした筆にかかると、必死に働いている人間の、あわれでユーモラスな姿が浮かび上がってくる。彼の批判は決して大上段に振りかぶったり「寸鉄人を刺す」といった類(たぐい)のものではない。むしろ温かいのだ。「僕は駄目な人間だ、駄目なんだ」と言いながら、読者にはその駄目な男の方が自然に人間的に生きているように見えてくる。ねじめ正一の場合もそうだったが、『高円寺純情商店街』『赤チンの町』などを読むと、彼をかつて詩に駆り立てたなにかがあって、その心を失っていない場合は散文に変わってもそれは様式の移動に過ぎない場合があるのだと教えられるような気がするのだ。詩だけを書いていても詩心が衰え、俗物になってしまう人もいるのだから。
町田康にとってはパンクロックミュージックも、詩も小説も同じことをやっているという意識のなかで創られているのではないだろうか。そのことによって彼は創造的なのである。
読みはじめてすぐ、もっと早く読まなかったのを後悔した。この作品は現代社会を少しも観念的ではなく自由な語り口で痛烈に批判しているのである。彼ののびのびした筆にかかると、必死に働いている人間の、あわれでユーモラスな姿が浮かび上がってくる。彼の批判は決して大上段に振りかぶったり「寸鉄人を刺す」といった類(たぐい)のものではない。むしろ温かいのだ。「僕は駄目な人間だ、駄目なんだ」と言いながら、読者にはその駄目な男の方が自然に人間的に生きているように見えてくる。ねじめ正一の場合もそうだったが、『高円寺純情商店街』『赤チンの町』などを読むと、彼をかつて詩に駆り立てたなにかがあって、その心を失っていない場合は散文に変わってもそれは様式の移動に過ぎない場合があるのだと教えられるような気がするのだ。詩だけを書いていても詩心が衰え、俗物になってしまう人もいるのだから。
町田康にとってはパンクロックミュージックも、詩も小説も同じことをやっているという意識のなかで創られているのではないだろうか。そのことによって彼は創造的なのである。
初出メディア
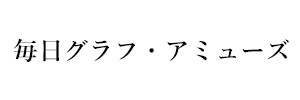
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1998年6月
ALL REVIEWSをフォローする