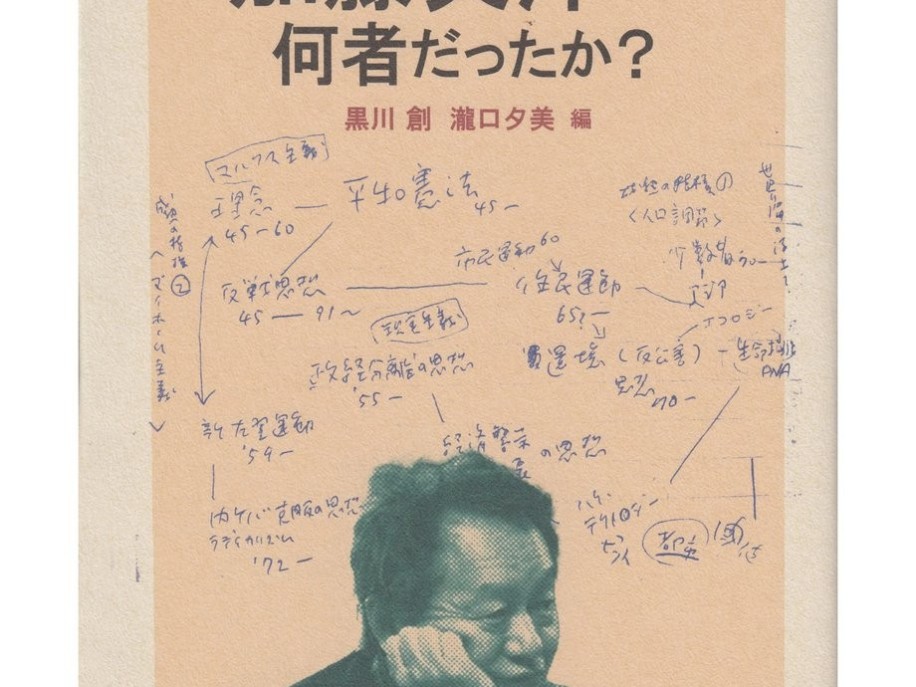書評
『珍説愚説辞典』(国書刊行会)
無用なる努力
世の中には四種類の読書がある。「役に立つ面白い読書」「役に立つがつまらぬ読書」「役に立たなくて面白い読書」そして「役にも立たずつまらぬ読書」。このうち、私がもっとも愛好するのは三番目の「役に立たなくて面白い読書」である。その典型として、この『珍説愚説辞典』を紹介する。亀は卵をじっと見つめて孵すという。(ジャン・モケ)
本当のキスをすると細菌が死滅するほど熱くなります。(S・L・カツォフ博士)
とまあ、こんな調子の珍卓説が、鬱然たる森のごとくに集められている大奇書だ。全部で3500項目に及ぶ大冊な本で、しかしこんな無意味なる本をまた、五年もかけて翻訳した(実際訳すのは大変だったろうなあ、なにせ何を言ってるのかさっぱり分からない仏語の駄洒落だのフランス人の仲間落ちだの項目が夥しい)高遠さんという人もじつに驚くべき物好きである。この本には日本人などは猿同様と断言するような言説が引かれていて、一読三憤というものだが、それを愚説と認めているのだからまあ良しとしよう。ただ、フランス人の僻(へき)でどうも理に落ちるというか、よほど欧州の神学・哲学・歴史などに通暁していないと何が面白いのかさっぱり分からない説が大半で、フランス文化にほとんど興味の無い人にはさして面白からぬものとも思われる。
さて、本書には「英国の文学は、一顧だに値しない」というアントワーヌ・ド・リヴァロルという人の言説が引かれているが、しかし、というべきか、それゆえに、というべきか、もしこれをイギリス人が編纂したならば、本書よりも百万倍面白い読み物ができたであろうに、そこが実に惜しい。
初出メディア

スミセイベストブック 2004年6月号
ALL REVIEWSをフォローする