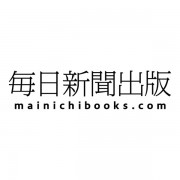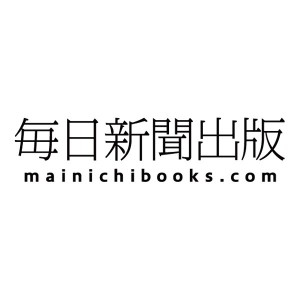本文抜粋
『公文書危機 闇に葬られた記録』(毎日新聞出版)
「森友・加計学園」「桜を見る会」「検事長の定年延長」――安倍政権による権力の乱用が指摘されたこれらの問題に共通しているのは、検証に必要な記録が十分に残されていない点だ。首相官邸や中央省庁の内部では、なくてはならない記録がどのように隠ぺいされ、闇に葬られていくのか。本書は、これまで知られていなかったその手口と実態について、首相経験者ら元政府高官や20人近い現役官僚らへのインタビュー、情報公開制度を駆使した「調査報道」の手法によって明らかにするものである。
本書のもとになった毎日新聞のキャンペーン報道「公文書クライシス」は2019年末、優れたジャーナリズム活動を顕彰する早稲田大学の第19回「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」を受賞している。
ご紹介するのは、本書の第八章「官僚の本音」からの抜粋である。
1週間後。霞が関にそびえるビルの上層階に向かった。広い個室に通され、名刺をわたして来意を告げると、幹部は困ったような顔をした。
そこで、この幹部が首相と重要案件で面談した際の「打ち合わせ記録」がつくられていない事実を伝え、証拠となる資料をテーブルの上にすべらせた。
しばらく沈黙が続いたあと、「オフレコが条件だ」と言って、わたしたちの質問に答え始めた。
──首相と面談した際の「打ち合わせ記録」をつくっていない理由は。
「打ち合わせ記録をつくるかどうかは、人によると思うが、そもそも、あまりつくるという発想がない」
──発想がない?
「議事録をとっておくような正式な会議であればつくるでしょう。それ以前の報告や打ち合わせを、いちいちという言葉はややあれですが、記録をつくって公文書としてとっておくという話にはならないのではないか」
──公文書管理法やガイドラインでは記録を残すことになっている。
「そういうルールができたのは、ここ10年ぐらいでしょ。若い職員はわからないが、わたしの若いころからの慣習からすると、そういうものを残しておくという発想がない。最後に決まったものがあればいいんじゃない」
──公文書管理法やガイドラインにしたがえば、最後に決まったことが書かれた記録だけでなく、政策立案の過程を検証できる記録を残さなくてはならない。
「政策の過程はものすごく、毎日のように変わる。ポイント、ポイントでとっておけばいい話。固まったところさえ残っていればいい。過程のなかで総理などといろいろやりとりはあるかもしれないが、それを公文書として残しておく発想は正直いってないね」
[書き手]毎日新聞取材班・大場弘行
本書のもとになった毎日新聞のキャンペーン報道「公文書クライシス」は2019年末、優れたジャーナリズム活動を顕彰する早稲田大学の第19回「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」を受賞している。
ご紹介するのは、本書の第八章「官僚の本音」からの抜粋である。
官僚の本音
わたしたちは、新聞の首相動静にもたびたび名前が出る、ある省庁の次官級幹部に面会のアポイントを入れた。1週間後。霞が関にそびえるビルの上層階に向かった。広い個室に通され、名刺をわたして来意を告げると、幹部は困ったような顔をした。
そこで、この幹部が首相と重要案件で面談した際の「打ち合わせ記録」がつくられていない事実を伝え、証拠となる資料をテーブルの上にすべらせた。
しばらく沈黙が続いたあと、「オフレコが条件だ」と言って、わたしたちの質問に答え始めた。
──首相と面談した際の「打ち合わせ記録」をつくっていない理由は。
「打ち合わせ記録をつくるかどうかは、人によると思うが、そもそも、あまりつくるという発想がない」
──発想がない?
「議事録をとっておくような正式な会議であればつくるでしょう。それ以前の報告や打ち合わせを、いちいちという言葉はややあれですが、記録をつくって公文書としてとっておくという話にはならないのではないか」
──公文書管理法やガイドラインでは記録を残すことになっている。
「そういうルールができたのは、ここ10年ぐらいでしょ。若い職員はわからないが、わたしの若いころからの慣習からすると、そういうものを残しておくという発想がない。最後に決まったものがあればいいんじゃない」
──公文書管理法やガイドラインにしたがえば、最後に決まったことが書かれた記録だけでなく、政策立案の過程を検証できる記録を残さなくてはならない。
「政策の過程はものすごく、毎日のように変わる。ポイント、ポイントでとっておけばいい話。固まったところさえ残っていればいい。過程のなかで総理などといろいろやりとりはあるかもしれないが、それを公文書として残しておく発想は正直いってないね」
[書き手]毎日新聞取材班・大場弘行
ALL REVIEWSをフォローする