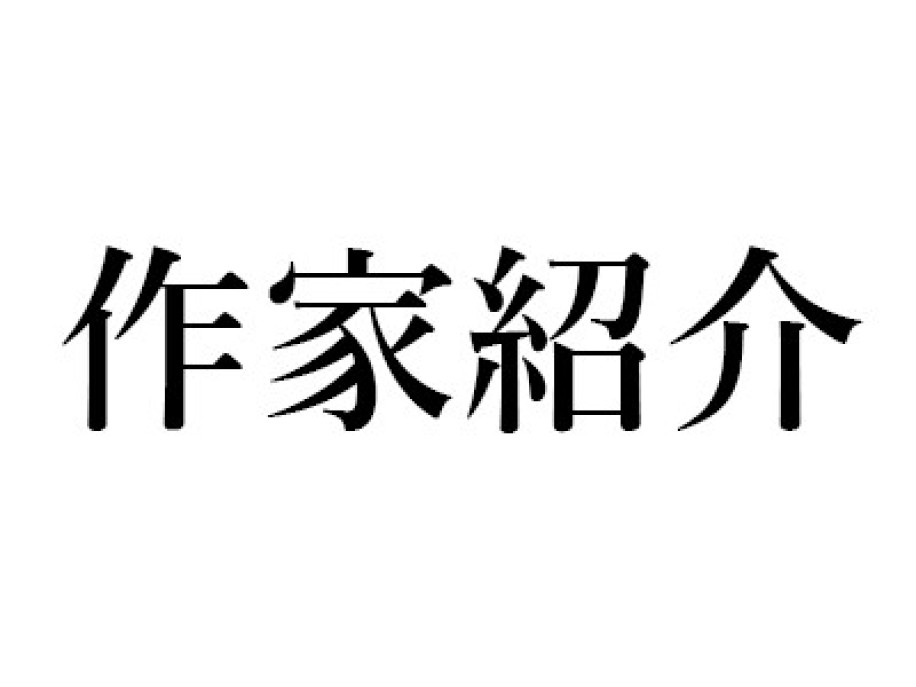書評
『大学病院で母はなぜ死んだか』(中央公論社)
環境劣悪、現代の奇怪な「城」
著者は新聞社の特派員で、世界を渡り歩き、現在はワシントンにいる。奥さんはガイジンである。そういう情況だから、日本へ帰ることは稀になる。だが老いた母親はひとり日本にいるのだ。心配ではあるが健康ならば、それほど気にはかからない。ある夜、東京から国際電話が入った。どうも癌らしい。すぐにかけつけたい。でも仕事は放棄できない。まずは遠隔操作のようなかたちで、ワシントンから日本へ電話を入れ、もどかしい思いでつてを辿り、母親の入院を準備する。物語は、そこからはじまる。現代のビジネスマンなら身につまされる設定である。
著者の心情はときには抑制を失するほどで、不安、敵意、怒り、慨嘆が行間にあふれ出る。強い感情が表出されながらも描写は的確で、それは観察力が鋭いからだが、つぎつぎと具体的なエピソードをえぐり連ねていく。読みながら思った。そうか、これは現代の私小説なんだな、と。あまりにも絵空事に淫した書きものが増えると、私小説がよみがえるのだ。とはいえ、本書はノンフィクションであり、すべて実名で綴られている。
母親は、無事に大学病院に入院することになった。だが大学病院はどうしてこれほど劣悪なのか。高い差額ベッド代を取るのに、エアコンもない。トイレは狭く、汚い。著者は「何十年も前に通った区立の小学校の、古い木造校舎の便所を思い出し」た。経済大国のはずなのに。患者はまるで収容所の囚人のようだ。
不吉な予感は、しだいに母親の病態を覆っていく。連日、検査を受ける。息子は医師にどんな具合ですか、と情報を求めたい。廊下で医師を待ち声をかける。「重大な手術の説明」も、「廊下での立ち話」になる。集団回診が「マーチの行進のように」病室を蹂躪する。患者の人権など、どこ吹く風である。そして機械的に、患者や家族の了解を得ずに抗癌剤が投与される……。さながら大学病院は現代の奇怪な「城」なのであった。
ALL REVIEWSをフォローする