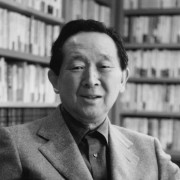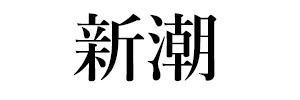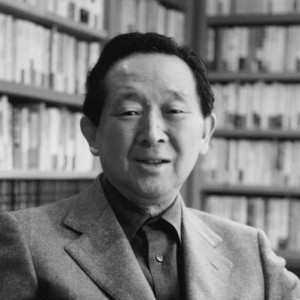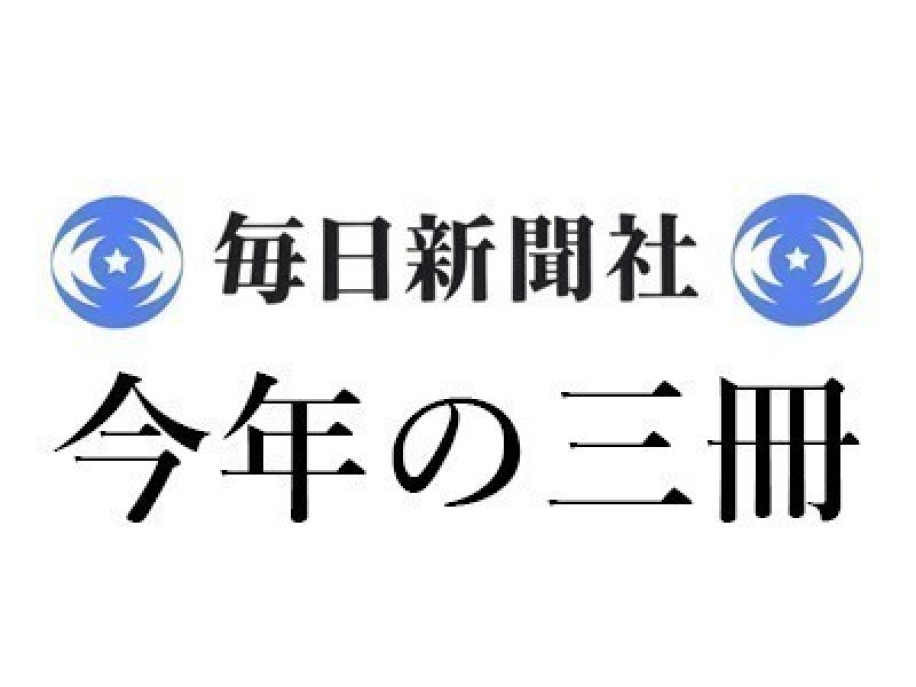書評
『わが小林一三―清く正しく美しく』(河出書房新社)
いわゆる阪急文化圏に生れた作者にとって、これはまさしく「わが小林一三」伝である。つとめて主観を押え、事実に則して記述した結果が、かえって阪田寛夫氏の目を通った個性的な作品を構成したところに、この本の魅力がある。
小林一三という人物は、経営者の立場にもある私にとって、常に気にかかる存在であった。彼ぐらい、自らの発想に忠実で通念に妥協しなかった実業家はいなかったと思われるからである。
みみず電車と悪口を言われた箕面電車からはじまって阪急電鉄にまで成長させた私鉄の経営も、沿線開発の手法も、見事に再建を果した東京電燈の社長としても、小林一三はその当時の経営感覚からは突出していて、彼がどのようにしてその独創性を周囲の人々に理解させ、決して上質な人ばかりではなかった財界人の妨害を排除して事業を推進したのかは、凡百の経営書では決して解明しきれないことのように私には思われた。
読みはじめる前の私の不安は、そのように強い性格を持った経営者と、どちらかと言えば地味で、静かに読者の共感に訴えてくるスタイルを持った阪田氏との取組みが、どのような結果を生むか、という点にあった。経営者の言動は現実世界における効果を考慮しているから、文学的リアリティからは遠い場合が多いのである。その俗な計算を取り除き、諸々の言動の奥に隠されている姿を描き切る作業を、阪田氏がどのように行ったのかが、私にとっては大きな関心事でもあった。
通読して、阪田氏はその課題を、全く氏の固有の手法によって成し遂げたように思う。氏はあくまでも資料に忠実であり、前後矛盾している小林一三の発言や日記、回想録についても、敢えて推測を混えずに使っている。その結果、小林一三の姿がより一層リアルに表現されている。
なかでも、宝塚歌劇がどのような思想的文脈のなかで構想され、いくたの試行錯誤を重ねながら、一種の国民演劇と呼べるものに発展していったかの叙述は、作者が興味を持っていた分野の事柄であるとしても詳細を極めていて説得力がある。また、戦争のための統制的な経済体制が進む時代に、たまたま商工大臣に任命されてからの悪戦苦闘ぶり、自由主義経済を貫こうとして破れ、後に「大臣落第記」を書いた身の処し方に現れている潔さと稚拙さとは、読者に小林一三の眼光の鋭さと膚のぬくもりとを同時に感じさせずにはおかない。独創的事業の創立者に、完全で超人的な姿を求める崇拝者には不満が残るかもしれないが、阪田氏は作家としての批評精神をいささかも曇らせることなく生身の小林一三を描き出しながら、しかもその目は対象に向って暖かく注がれている。
彼は二つの〝幕間〟で自らの感想を語ることで、その他の部分は伝記として書いているが、むしろその伝記の部分に、材料の取捨選択と配列に際して働いている作者の虚構構築の効果が示されていることは興味深い。
作品であるからこそ、巧まずして一人の独創性に富んだ経営者の生涯を描き得た事実は、文学というものの秘密を開示している。
ドキュメントやルポルタージュこそ真実を伝えるものであり、文学作品は虚構であるからして絵空事に過ぎないという、マスメディア時代における通念に対する力強い反証がここにはあると思われる。
小林一三という人物は、経営者の立場にもある私にとって、常に気にかかる存在であった。彼ぐらい、自らの発想に忠実で通念に妥協しなかった実業家はいなかったと思われるからである。
みみず電車と悪口を言われた箕面電車からはじまって阪急電鉄にまで成長させた私鉄の経営も、沿線開発の手法も、見事に再建を果した東京電燈の社長としても、小林一三はその当時の経営感覚からは突出していて、彼がどのようにしてその独創性を周囲の人々に理解させ、決して上質な人ばかりではなかった財界人の妨害を排除して事業を推進したのかは、凡百の経営書では決して解明しきれないことのように私には思われた。
読みはじめる前の私の不安は、そのように強い性格を持った経営者と、どちらかと言えば地味で、静かに読者の共感に訴えてくるスタイルを持った阪田氏との取組みが、どのような結果を生むか、という点にあった。経営者の言動は現実世界における効果を考慮しているから、文学的リアリティからは遠い場合が多いのである。その俗な計算を取り除き、諸々の言動の奥に隠されている姿を描き切る作業を、阪田氏がどのように行ったのかが、私にとっては大きな関心事でもあった。
通読して、阪田氏はその課題を、全く氏の固有の手法によって成し遂げたように思う。氏はあくまでも資料に忠実であり、前後矛盾している小林一三の発言や日記、回想録についても、敢えて推測を混えずに使っている。その結果、小林一三の姿がより一層リアルに表現されている。
なかでも、宝塚歌劇がどのような思想的文脈のなかで構想され、いくたの試行錯誤を重ねながら、一種の国民演劇と呼べるものに発展していったかの叙述は、作者が興味を持っていた分野の事柄であるとしても詳細を極めていて説得力がある。また、戦争のための統制的な経済体制が進む時代に、たまたま商工大臣に任命されてからの悪戦苦闘ぶり、自由主義経済を貫こうとして破れ、後に「大臣落第記」を書いた身の処し方に現れている潔さと稚拙さとは、読者に小林一三の眼光の鋭さと膚のぬくもりとを同時に感じさせずにはおかない。独創的事業の創立者に、完全で超人的な姿を求める崇拝者には不満が残るかもしれないが、阪田氏は作家としての批評精神をいささかも曇らせることなく生身の小林一三を描き出しながら、しかもその目は対象に向って暖かく注がれている。
彼は二つの〝幕間〟で自らの感想を語ることで、その他の部分は伝記として書いているが、むしろその伝記の部分に、材料の取捨選択と配列に際して働いている作者の虚構構築の効果が示されていることは興味深い。
作品であるからこそ、巧まずして一人の独創性に富んだ経営者の生涯を描き得た事実は、文学というものの秘密を開示している。
ドキュメントやルポルタージュこそ真実を伝えるものであり、文学作品は虚構であるからして絵空事に過ぎないという、マスメディア時代における通念に対する力強い反証がここにはあると思われる。
ALL REVIEWSをフォローする