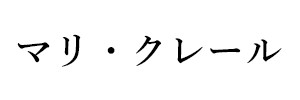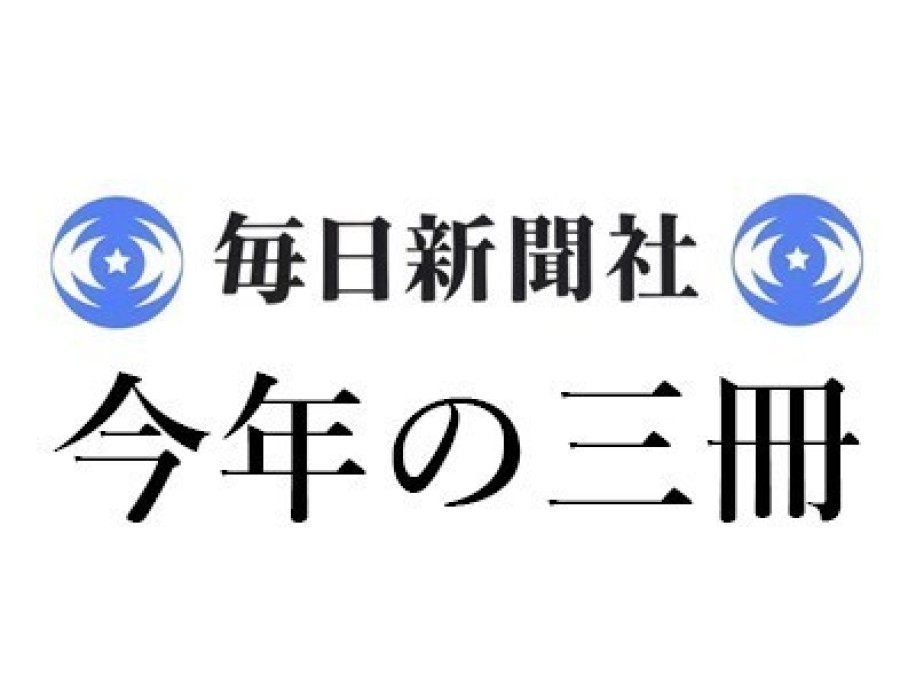書評
『同時代人サルトル』(講談社)
ふだんさまざまな若い人たちに接していて痛感するのは、彼らがほとんどサルトルを読まなくなったということだ。実存主義という言葉もその内実も知らない。関心がない。
ぼくらの学生時代の雰囲気からすれば、考えられないことだ。たしかに時代が変わった。ほぼワン・ジェネレーションが経過している。一九六九年には安田講堂「落城」、七〇年に三島由紀夫の自決、七二年には浅間山荘事件があった。このあたりから時代は急速に転回した。八〇年代のポストモダン・ブームが拍車をかけた。軽薄短小などという便利な言葉も出た。吉本隆明がファッション・モデルよろしく女性誌などに登場し、いまやばななのお父さんという認知を得るにいたった。ことあるごとにサルトルの名前をもちだしていた大江健三郎はそのサルトルが拒否したノーベル賞を受けた。文化勲章が、そのかわりにコケにされた。
こうした時期に、本書が刊行された(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年)。いいタイミングだともいえるし、反時代的だともいえる。いずれにせよ、誰かが書かなければならなかった、そんな気がする。もちろん、著者はぼくより八歳年上であり、経験の内容も経験への構えもちがう。しかしそんな差を乗りこえて、本書は訴えかけてくる。それは著者がサルトルをまさしく「同時代人」としてとらえ、著者の生きた時代と思想の歩みとに重ね合わせるように、とはいえ決して無闇に興奮することなく、いわば暖かい距離をおいてこの稀有の人物とその業績を見つめ直しているからだ。
著者は本書をこういう言葉で始めている。うまい書き出しだ。この言葉にすなおに共感できるのは、しかし一部の世代だけだろう。ぼくもサルトルを読んだ。大学の心理学科から美学科へ転科しようとするとき、主任教授にその理由を説明しなければならず、そのときぼくはサルトルの心理学批判の議論を引き合いに出した。『想像力の問題』あたりが頭にあったのだと思う。すると教授は、サルトル? と訊き返した。あとから知ったのだが、彼はサルトル嫌いで有名だったのだ。もちろん、そんなことで転科が拒否されたわけではない。いまでもはっきり覚えているのは、嫌悪とも怪訝ともつかぬ面持ちで訊き返されたとき、なにか恥ずかしさみたいな感情がぼくの心をよぎったことである。ぼく自身サルトルに対しては曖昧な、あるいはアンビヴァレントな気持ちでいたのだろうと思う。「ちょっぴり胸が熱くなる」という著者の言葉は、ぼくのそういう思い出にもつながってくる。そういう個人史的なことを語らせてしまうようなところが、本書にはある。それこそがサルトルの、実存主義の意味かもしれないのだが。
とはいえ、本書の叙述は堅実である。それはとりわけ「政治思想の視座」の章に明らかである。徹底的に個人の意識の問題として出発した実存主義が社会に大衆に政治に関わらねばならなくなったとき、サルトルがいかに苦闘を余儀なくされたか、その仔細を追う著者の筆致は著者自身の生とほぼ完全に同調しているように生彩に富んでいる。
「大衆との懸隔をうけいれることが誠実さのあかしだという知の宿命を、サルトルは政治の地平でも生きぬこうとしたのだった」という著者の認識は、たぶん著者自身が身をもって体得したことではなかったか。
このことは「知識人の孤独」という章でも確認されるだろう。一九六六年秋に来日した折のサルトルの言動の奇妙な違和感、それはまだ高校生だったぼくも記憶しているが、それを著者は「場ちがいな深刻さにつきまとわれているように見えた」という。その印象から出発しつつ、著者は「いかがわしく、無力で、孤独な知識人」を論じる。フランスと日本との不可避的な差異を見すえつつ、「いま知の普遍性に生きようとするものに要求されるのは、現実との距離をはかりつつ、孤独をさりげなく自然に生きることであるように思われる」と書く。こういう言葉は、「さりげなく」見えて、実は誰もがいえる言葉ではない。静かな迫力が伝わってくる。それが感じられなければ、本書を読む意味はないだろう。
ちょっと不思議に思ったのは、『聖ジュネ』や何篇かの戯曲を採り上げた文章が、いささか祖述めいた様相を帯びていることだ。著者がこれらの作品をいかにも好んでいることは伝わってくる。好きだからこそ、なのだろうか。政治や知識人の問題における著者の犀利な批判意識が美や芸術の問題に対してどういう内在的関係をとるのか、いまひとつつかめないという印象を受けた。これはサルトル自身についていえることだったのかもしれない。
実存主義を死語にしてはならない。本書は、そのためにも読まれていい問題的(プロプレマティック)な好著である。
【この書評が収録されている書籍】
ぼくらの学生時代の雰囲気からすれば、考えられないことだ。たしかに時代が変わった。ほぼワン・ジェネレーションが経過している。一九六九年には安田講堂「落城」、七〇年に三島由紀夫の自決、七二年には浅間山荘事件があった。このあたりから時代は急速に転回した。八〇年代のポストモダン・ブームが拍車をかけた。軽薄短小などという便利な言葉も出た。吉本隆明がファッション・モデルよろしく女性誌などに登場し、いまやばななのお父さんという認知を得るにいたった。ことあるごとにサルトルの名前をもちだしていた大江健三郎はそのサルトルが拒否したノーベル賞を受けた。文化勲章が、そのかわりにコケにされた。
こうした時期に、本書が刊行された(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年)。いいタイミングだともいえるし、反時代的だともいえる。いずれにせよ、誰かが書かなければならなかった、そんな気がする。もちろん、著者はぼくより八歳年上であり、経験の内容も経験への構えもちがう。しかしそんな差を乗りこえて、本書は訴えかけてくる。それは著者がサルトルをまさしく「同時代人」としてとらえ、著者の生きた時代と思想の歩みとに重ね合わせるように、とはいえ決して無闇に興奮することなく、いわば暖かい距離をおいてこの稀有の人物とその業績を見つめ直しているからだ。
サルトル、とつぶやくと、いまもちょっぴり胸が熱くなる。
著者は本書をこういう言葉で始めている。うまい書き出しだ。この言葉にすなおに共感できるのは、しかし一部の世代だけだろう。ぼくもサルトルを読んだ。大学の心理学科から美学科へ転科しようとするとき、主任教授にその理由を説明しなければならず、そのときぼくはサルトルの心理学批判の議論を引き合いに出した。『想像力の問題』あたりが頭にあったのだと思う。すると教授は、サルトル? と訊き返した。あとから知ったのだが、彼はサルトル嫌いで有名だったのだ。もちろん、そんなことで転科が拒否されたわけではない。いまでもはっきり覚えているのは、嫌悪とも怪訝ともつかぬ面持ちで訊き返されたとき、なにか恥ずかしさみたいな感情がぼくの心をよぎったことである。ぼく自身サルトルに対しては曖昧な、あるいはアンビヴァレントな気持ちでいたのだろうと思う。「ちょっぴり胸が熱くなる」という著者の言葉は、ぼくのそういう思い出にもつながってくる。そういう個人史的なことを語らせてしまうようなところが、本書にはある。それこそがサルトルの、実存主義の意味かもしれないのだが。
とはいえ、本書の叙述は堅実である。それはとりわけ「政治思想の視座」の章に明らかである。徹底的に個人の意識の問題として出発した実存主義が社会に大衆に政治に関わらねばならなくなったとき、サルトルがいかに苦闘を余儀なくされたか、その仔細を追う著者の筆致は著者自身の生とほぼ完全に同調しているように生彩に富んでいる。
「大衆との懸隔をうけいれることが誠実さのあかしだという知の宿命を、サルトルは政治の地平でも生きぬこうとしたのだった」という著者の認識は、たぶん著者自身が身をもって体得したことではなかったか。
このことは「知識人の孤独」という章でも確認されるだろう。一九六六年秋に来日した折のサルトルの言動の奇妙な違和感、それはまだ高校生だったぼくも記憶しているが、それを著者は「場ちがいな深刻さにつきまとわれているように見えた」という。その印象から出発しつつ、著者は「いかがわしく、無力で、孤独な知識人」を論じる。フランスと日本との不可避的な差異を見すえつつ、「いま知の普遍性に生きようとするものに要求されるのは、現実との距離をはかりつつ、孤独をさりげなく自然に生きることであるように思われる」と書く。こういう言葉は、「さりげなく」見えて、実は誰もがいえる言葉ではない。静かな迫力が伝わってくる。それが感じられなければ、本書を読む意味はないだろう。
ちょっと不思議に思ったのは、『聖ジュネ』や何篇かの戯曲を採り上げた文章が、いささか祖述めいた様相を帯びていることだ。著者がこれらの作品をいかにも好んでいることは伝わってくる。好きだからこそ、なのだろうか。政治や知識人の問題における著者の犀利な批判意識が美や芸術の問題に対してどういう内在的関係をとるのか、いまひとつつかめないという印象を受けた。これはサルトル自身についていえることだったのかもしれない。
実存主義を死語にしてはならない。本書は、そのためにも読まれていい問題的(プロプレマティック)な好著である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする