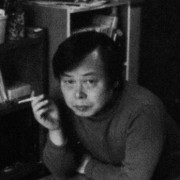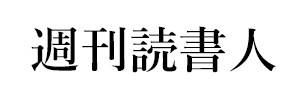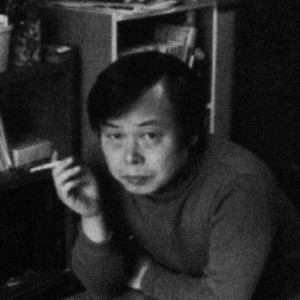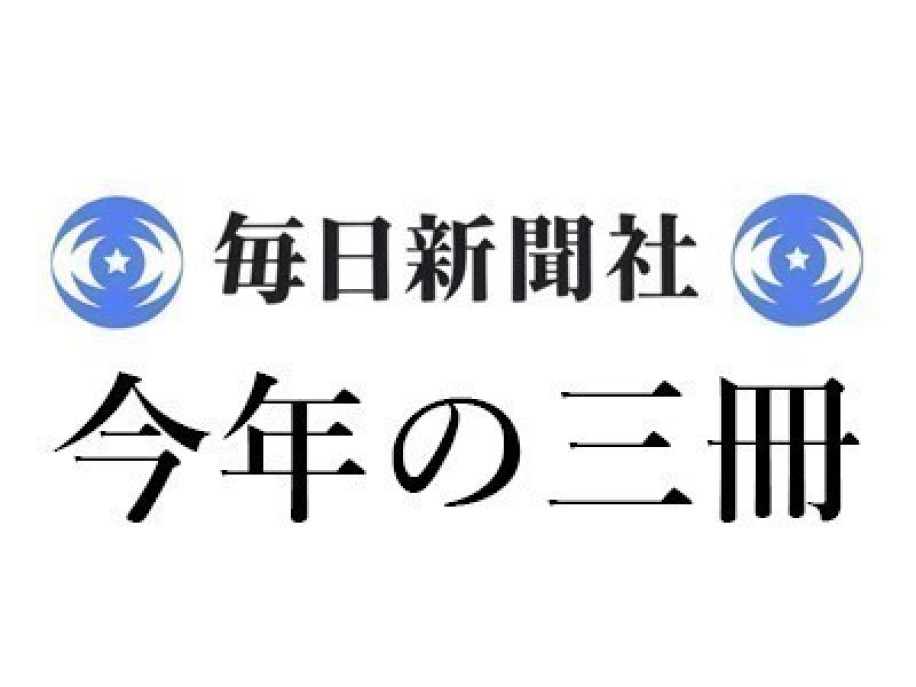書評
『薔薇と無名者―松田政男映画論集』(芳賀書店)
失業革命家の詩的体験 書かれざる本のための断片的注記
私事に亘るが、本書の冒頭に収められた「壁のなかの沈黙」という文章の一節を読んである私的感慨を禁じえなかった。それは松田政男が高校二年生の活動家として板橋のスラム街に出没するくだりなのだが、じつをいえばたまたま当時私も同じ高校に在学していたのである。むろんマックス・スチルネルあたりに熱を上げていた私などには、高校細胞が突然分裂して下駄ばきの両者がはり合いをしている光景に接しても、なにがなんだかさっぱりわけがわからなかったのだが、おそらく松田政男はそういう私の理解を絶する世界のなかにその後急速に没入していったらしい。ある日高校の庭から忽然として姿を消し、十数年ほどして再会したときには「死霊」の首猛夫を髣髴とさせるたえず動いてやまない永久運動機械のような陰謀家の面魂で出現し、あまつさえあれよあれよというまにおびただしいアジ文書から映画、ジャズの評論を書きまくってついに二冊目の評論集を編んでしまっている、といった具合なのである。この本を通読してえた印象も右の消息と無縁ではない。通常の意味での書物というより、これはある書かれざる本のための欄外注や本文補遺の集成といった趣きを呈している。いわば本体はここにはなく、松田政男が闇にも無名者の空間にも第三世界にもことよせている行動の世界にあって、しかも書かれた文章はそこからの啓蒙的なメッセージというよりは、風雲と冒険をはらむ、書かれていない、書くことの不可能な世界に向って下降していく断片的な注記にほかならない。断片性は行動家の文章の特権である。それゆえに彼は、ときにはパンフレテールの汚名をむしろ嬉々として甘受しているような風情さえあるようだ。
本来なら私は、たとえばこの本の第五部に見るような左翼スコラ学流的な煩瑣なポレミズムが性に合わない。けれども仔細に眺めてみればこの論争調は、左翼官僚的な用語法にもかかわらず、じつは権力意志の実体や官僚組織の背景をほとんど欠いている「失業革命家」の、詩的体験(「内なる第三世界」と彼はいう)以外の何物にも根さしていない発言であることが納得されるのである。権力意志の実体を欠いているから家父長的な重みがない。官僚組織の背景がないからきたるべきものへの計画性がない。そういう合いの手が入ることは必定であろうが、しかし重みや計画性をもちまわる政治主義者には絶対に知ることのできない永劫に回帰する「いま」のみを生きるロマンチックな行動家に、いまさらそんなことをいったところでどうなろうか。「ボードレールがかれの世界から追放する星々こそブランキにおいて永劫回帰の舞台になるものだ。」といったのはワルター・ベンヤミンである。だいいち、「赤い翼も持たず、青い翼も持たず、ましてや、雲のように純白な肉体などをいささかも所有していないとしても、天使はやはり天使である。」などという文句でアジテーションをはじめる左翼官僚なんて見たこともない。
ALL REVIEWSをフォローする