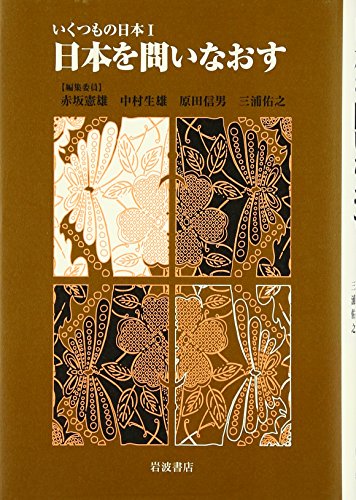書評
『日本美術史』(放送大学教育振興会)
二つの転換期に着目、個性的な評価も
テキストを書くのは難しい。多くの書物は、あるテーマにそって構想を立て、調べてグイグイ書いてゆけば、それでよいのだが、教科書ともなると、全体をわかりやすく過不足なく叙述することがまず求められるからである。しかし、学問や研究が進んでいる領域においては、それを個人の仕事で行うのは容易ではなく、それぞれの専門家に頼んで結局は分担執筆になってしまう。また個人でやったとしても、得意な領域と不得意な領域との叙述のギャップはいかんともなしがたい。
そんなところから日本美術史のテキストを個人で書いた本書を見たとき、大いに興味がそそられた。原始美術から現代の美術までを一貫した視点で見てテキストを書くのはとても困難だろうと考えたからである。しかし手にとったときに感嘆してしまった。よくここまで書けたものかと。
著者の専門は近世絵画史である。このことは重要である。彫刻史や工芸史から美術史全体を見通すのは大変な作業であり、また近世が専門ならば前近代の美術史を把握して、近代への転換を常に考えざるをえないからである。
しかしテキストには枚数の制限があるもので、しかもこれは放送大学のテキストということから、十五章にまとめねばならない。テキストには制限があるからこそ、凝縮した叙述が可能という側面もあるのだが、このことは何ともつらい。
そうした各種の制限のもとで書かれた本書であるが、全体の流れを的確にとらえ、作品の解説も著者の見た目を大事にしつつ、これまでの研究をよく咀嚼し、最新の成果を盛り込んでおり、きわめて上質の本に仕上がっている。
著者がとくに力を入れたのは十二世紀の院政期の美術であり、十八世紀を中心とした近世の美術である。それぞれ美術史の大きな転換期に相当する。古代の美術から中世の美術へと大きく転換してゆくのが前者の時期であり、中世後期からはじまった美術の流れが近世の美術に帰結して、やがて近代の美術へと転換するのが、後者の時期である。
面白いのは、「高校の日本史の教科書に採用されているような、しばしば不正な古い通説ではなく」とか、あるいは『鳥獣人物戯画』について「漫画の祖先のようにいうのは、鑑賞形態の違いを無視した比喩以上の意味を持たないだろう」と指摘するような辛口の寸評である。
これらの評価そのものが正しいかどうかは、やや問題はあるにしても、これが叙述に刺激をあたえて、教科書臭さを打ち消している。
いうまでもなく、著者がどんな作品を重視してとりあげ、それをどう位置づけているのかがいちばん興味深く、読者にとっては意中の作品がどう評価されているのか見るのが楽しみになろう。
ただ美術史の本といえば、作品のカラー写真が命ともいうべきであるにもかかわらず、残念なことに本書には一点もそれがない。
しかしそれはテレビ放送で見て補うことになろう。本書は放送大学のテキスト用として編まれたものである。カラー写真のない美術書を読んで、作品を想像しながら、テレビを見るのもまた新たな楽しみ方である。
楽しみといえば、著者は一昨年に話題となった辻惟雄著『日本美術の歴史』(東京大学出版会)に文献案内を書いており(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2008年)、お持ちの方にはその本と本書を見比べるという楽しみもあろう。
【新版】
ALL REVIEWSをフォローする












![正解がない時代の親たちへ 名門校の先生たちからのアドバイス[エッセンシャル版]](https://m.media-amazon.com/images/I/411xtqUxpxL._SL500_.jpg)