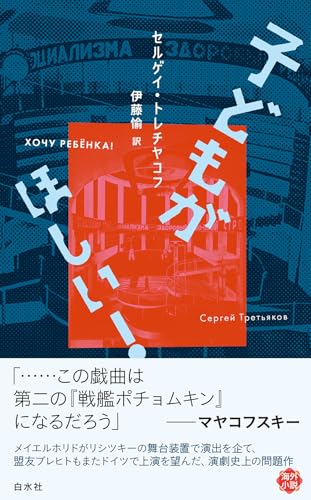書評
『外套・鼻』(岩波書店)
彼はいったいどこから来たのか?
貧しい小役人アカーキイ・アカーキエヴィチはうだつのあがらない、職務に忠実な痔疾持ちの独身男だ。仕事というのが書類の筆写で、時には作成ずみの書類の動詞を一人称から三人称に置きかえるだけだったりする。しかし、彼はこの写字の仕事に全身全霊を打ちこんでいる。意地悪する同僚にむかって、「かまわないで下さい! 何だってそんなに人を馬鹿にするんです?」と一種異様な響きの、何かしら人の心に沁みいるような声で抗議する。彼は靴底をへらさないために、爪先立ちで家路をたどる。彼は街のようすに注意を払ったことがない。何かに驚かされて立ち止まっても、いったい自分が往来のまん中にいるのか、引き写した文章の途中にいるのかわからないほどだ。
彼の着ている外套はぼろぼろでみんなの嘲笑のまとだ。ながい間に何度も修繕に出し、つぎをあててきたが、今度ばかりは修繕屋もサジを投げる。こうしてついにアカーキイは新しい外套を仕立てることになる。
新しい外套が仕立てられてゆく。裁縫師の一針一針に彼の心はあやしく燃えあがる。しかし、やっとできあがり、はじめて袖に腕を通した夜、暗いさびしい広場の端で口髭をはやした、人間の頭ほどもある大きなこぶしの男に外套を奪われてしまう。悲しみのあまり彼は死に、幽霊となって市中を徘徊する。
ゴーゴリの『外套』だが、この粗筋(ストーリー)は僕にはあくまで表面上のものに思える。もうひとつの隠された筋がありそうだ。
死んだ農奴の名簿を集めてひと儲けを企む男の物語『死せる魂』もそうだが、ゴーゴリの世界はどこか決定的に歪んでいる。物語の展開する時と場所は具体的なロシアの村やペテルブルグといった街で、登場人物たちもごくありふれて現実的な役人や町人、農民なのに、ただ一人、主人公だけがどこか違う。通常、物語の人物たちも我々と同様に父親と母親がいて、母親の胎内から生まれた人間だということは疑いない。童話や神話であってもこの確信は揺らがない。しかし、ゴーゴリの主人公にあってはこの一点が限りなく疑わしく、あやしくなる。『死せる魂』のチチコフやアカーキイ・アカーキエヴィチ、彼らはいったいどこから来たのか?
読み手に与えるこの疑惑と不安こそ歪みの正体だ。
アカーキイはいったいどこから来て、どこへ行くのか。それを明らかにしてみたい。
さて、この物語の隠された筋とは、アカーキイが新しい外套を着るというところになく、まるで売れなくなった女性タレントみたいに、彼が古い外套を脱いでゆく過程にある、と外套の裏をひっくり返して考えてみる。彼が脱ぐ決心をするまでにほぼ半分以上のページが費やされているのだから根拠は十分。
アカーキイは悲しみのあまり幽霊になるのではなく、もともと歪んだ暗い世界から派遣された幽霊だったのでは? 自分が往来の中にいるのか、書き写した文章の途中にいるのかわからない、といった彼の役人生活の奇妙な送り方をみよ!
彼は現世でまとった仮装をひとつひとつ脱いでゆく。新しい外套の消失は、彼が幽霊という本来の裸の姿に決定的に還ってゆくことを意味する。幽霊にもどったアカーキイは、彼を助けようとしなかった高官の外套を奪い取ると地上から完全に姿を消す。しかし、市中ではまだ時折幽霊出没の噂が立つ。そいつは口髭をはやし大きなこぶしをしている。この幽霊はアカーキイのアンチテーゼ、つまりアカーキイの外套を奪った男なのだ。物語は奇妙な円環を閉じ、いっそうぐいっと歪む。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする