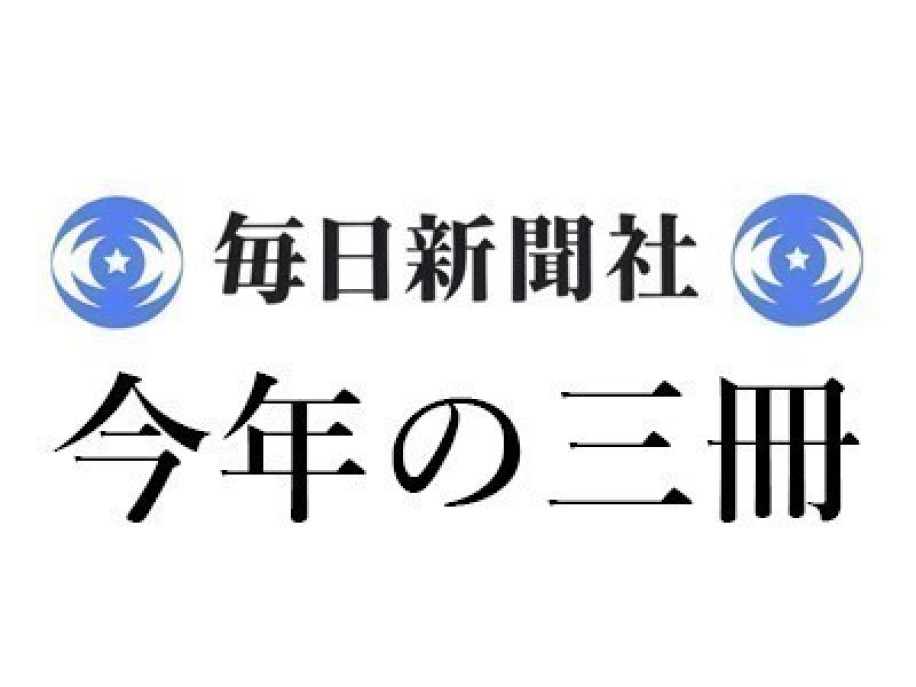書評
『聖家族』(新潮社)
圧倒的に強い、個を越えたものたち
まず、冒頭。物語が立ちあがる。この上もなくシンプルに。なにしろ最初の章(というか、1、と数字で区切られた空間に)は、一行しかないのだ。部屋はわずかに三畳あまりの広さしかない
というのがその一行で、ここからすべてが始まる。壮大で鮮烈で、緊密で筋肉質で、仰天の連続である長い長い物語のすべてが。
わずかに三畳あまり、のその部屋には、狗塚(いぬづか)羊二郎という男がいる。死刑囚であるその男の元に、祖母らいてうからやさしい手紙が届く。らいてうにははくてうという名の祖母がいる。はくてうには、シラキジという名の祖母がいる。狗塚家は、東北のある土地に、代々続く名家なのだ。三人称も一人称も、二人称をも駆使して、時間も空間もひたすら広げ、暴走と言いたいほどのスピードで、発熱しそうな緊密度を維持したまま語られるこの小説を、要約することは無論不可能なのだけれど、ごく大雑把(おおざっぱ)に言うと、死刑囚羊二郎がその独房に至るまでに、兄と二人でたどった軌跡――ビビッドなロード・ノベル――が一つの軸としてある。そこに、幾人もの祖母たちの語る狗塚家の歴史――というのはすなわち妄想の(と著者の言う)東北の歴史――がかぶさり、必然的に日本の歴史が語り直される。また別の必然として、兄弟の父親である不思議な男の、偏執的かつ情熱的な行動もつぶさに追われる。さらに、らいてうの孫であり兄弟の妹であるカナリアが、いずれ祖母たちの一人となるべき一羽の鳥(実際は勿論(もちろん)人間です)として、物語をくっきり横切って飛ぶ。
圧倒的なのはイメージの奔流。たとえば、馬の腹に頭をつっこんで死んだ男と、そばで遊んでいてそれを見た幼児、の場面が私は好きだ。馬たち、犬たち、天狗(てんぐ)たち、女たち。ここには個を越えたものが確かに描かれていて、それは、連なる鳥居や車窓を流れる風景とも響き合い、捕えられないもの、去っていくもの、けれど確かに存在するもの、として、小説を鮮烈に貫いている。それがほんとうに、ただ、美しい。
あちこちに埋め込まれた方言の豊かさも、読む愉(たの)しみをいや増してくれる。男たちの、女たちの、子供たちの、声。それもまた個を越えたものとして、深く耳に残る。上手なのだ、文字にする東北弁が。また、もう一つ私が好きなのは、ごくごく短い場面しか与えられない登場人物たちで、たとえば仙台の駅にいた大学生、山形の横断歩道に居合わせた人々。他にもたくさんいるのだが、ほとんど名前も与えられていない彼ら彼女らが、この小説に欠くべからざる存在であることが、そもそもこの作家の小説観の正しさを証明していると思う。私が古川日出男という小説家を信頼してしまうのは、書かれている言葉にさえ身をゆだねれば、きっちりそこに連れて行ってくれるからだ。
個人的に言うと、私はほぼすべての頁(ページ)についている黒いしるしが不気味でいやだったのだけれど、この小説がおもしろいことは確かだ。すみずみまで力が漲(みなぎ)っていることも。こんなものが書けるなんて信じられない。読み終ったとき、私は言葉のパンチドランカーになった気がした。狗塚兄弟が異様なまでに体を鍛えているように、古川日出男は異様なまでに言葉を鍛えているのだろう。
どうでもいいことだけれど、この本を読んで以来、「地図」という文字を見ると、「地獄図(ジゴクエ)」の略語に思えてしまって困っている。
ALL REVIEWSをフォローする