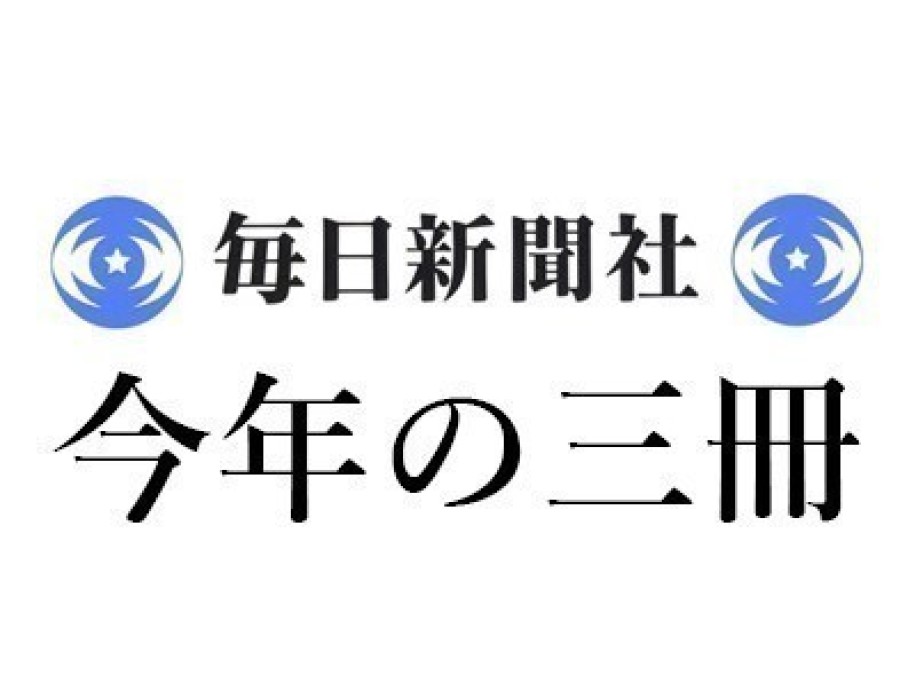書評
『宗教VS.国家』(講談社)
『レ・ミゼラブル』で知る19世紀フランスの世相
フランスで起きたスカーフ事件を記憶している人はまだ多かろう。公立中学校でイスラームの女子生徒がスカーフをかぶったまま教室に入ろうとしたところ、はずすようにいわれ、それを契機に大論争になったという事件である。フランスには宗教に対して「寛容さ」がないのかと思って、そのままに見過ごしてしまったのは私一人ではなかったろう。
日本で世界人権宣言五十周年のポスターに、ノーベル平和賞を受賞したマザー・テレサの姿が大写しになっているのを見たヨーロッパ人が、「カトリックと人権というのは何か関係があるのか」と怪訝(けげん)な顔をしたという。
これを聞いてすぐに事情がわかる人はどれだけいようか。残念なことに私もすぐにピンとこなかったのである。
この二つにはフランスの政教分離をめぐる長きにわたる対立と論争があったことを著者は解き明かしてゆくのだが、その際に小説を素材にして丹念に分析を加えてゆくところに本書の最大の特徴がある。
小説を文学的に読むのではなく、小説を率直に読んでみることにより、生きた人間たちの心情や生活を見つめてゆきたい、と著者はいう。ついつい小説というと、文学批評の面から論じることが多いが、そうした方法から取り上げるのではない。
なかで主な素材になっているのが、ヴィクトル・ユゴーの名作『レ・ミゼラブル』である。これがフランス十九世紀の世相を知る最良の手引きとなる本であったとは、これまで気にもとめずに読んできたのであった。
文学作品が時代を知るうえで欠かせないテキストであると私も思い、分析を加えてきたことはあったが、なるほど、その分析の展開を見てゆくと、この小説はカトリックと政治との対立を考えるうえで重要な素材であることがわかってきた。
フランス革命から二十世紀初頭の「ライシテ」こと政教分離の法令が出されるまでの時間軸を経(たていと)に、『レ・ミゼラブル』に描かれた人物や教会の動きなどを緯(よこいと)にして、教会を政治から解き放ち、国家や教育へのカトリックの影響を退けてきた歴史的動きを明快に叙述している。それは本書の副題にある「市民の誕生」の歴史でもあった。
カトリックや共和政の動き、そしてまたプロテスタントやフリーメーソンの活動など、様々な勢力が目指した運動を著者は巧みに描き分けて、十九世紀のフランスの世相を明らかにしている。
とりわけ政教分離を積極的に進めた政治家ジュール・フェリーの動きを重点的に追い、精細に描いているのが興味深かった。市庁舎や小中学校の壁に「自由・平等・博愛」というフランス革命の標語が刻まれるようになったのは、彼のお陰だったという。
かのスカーフ事件には、宗教が教育に入り込むのを拒否してきた歴史の流れがあり、ヨーロッパ人のつぶやきには、マザー・テレサのような修道女がカトリックの先兵となって政治や教育に大きな影響をあたえてきた経緯のあったことがよくわかった。
ともすれば安易に政教分離を考えやすい日本の事情を思うとき、多くの参考になろう。神仏習合と寺檀制度が、明治維新期の廃仏毀釈令によっていとも簡単に切り捨てられ、やがて国家神道へと突き進んできたのが我が国であった。だからこそ、靖国問題も起きるのであろう。そんなことを思わされた一書である。
ALL REVIEWSをフォローする