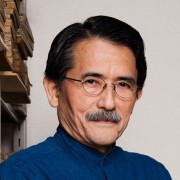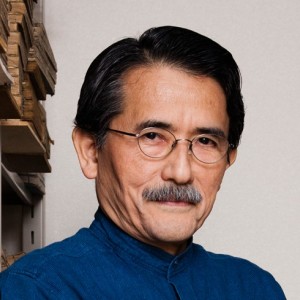書評
『カラー版 知床・北方四島―流氷が育む自然遺産』(岩波書店)
今、北の海に起っていること
あの北の海のラッコの、のんびりと海に遊ぶ姿はいかにも可愛い。ラッコは、かつて英米の密猟者によって乱獲され、ほとんど絶滅に瀕したのだが、ソ連の手厚い保護策によって、やっと回復しつつある。ところがラッコは、皮下脂肪が少ないので大量のエネルギー補充を必要とし、ために一頭あたり、末端価格にして数千万円分ものウニや蟹を年間に食べてしまうのだそうである。
生態系の保存と共生ということの難しさを、私はこの本で知った。
一方、その蟹については、蟹籠という漁具、すなわち小魚を餌にした「アリ地獄に似た落とし穴のような構造」の道具で獲るといい、それで乱獲した密猟者が、たとえば「根室のカニ祭り」を当て込んでは海中に浮かべておいたりする。が、取り締まりが来ると、籠のブイの綱を切って逃げてしまうので、「やがてかごの中で共食いが始まる。さらに死臭につられて他のカニが引き寄せられ、命を落としていく。カニかごは海底に沈んだまま永久にカニを死に追いやり続ける」のだという。能天気にタラバガニなどを食べている陰で、じつはこんなことが起っていて、しかもその蟹籠は日本製なのだそうだ。
この本は、北方四島、知床海域でおきている多くの憂慮すべき事態に強く警鐘を鳴らしている。安いタラコやカニを単純に喜んでいてはいけないことを知るべきである。その安さの背後には、暗黒の密猟者たちが暗躍しているかもしれないのだ。
単なる海洋資源についての警告にとどまらず、もっと大きな自然の循環ということを、多様で周到な例を挙げて教えているこの書、誰もが一読して「考えて」欲しいと思う。
初出メディア
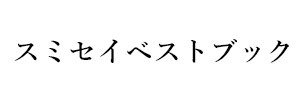
スミセイベストブック 2008年10月号
ALL REVIEWSをフォローする